正の数・負の数の計算に入る前に、「3000円の支出」を「−3000円」と表記することを勉強します。
さらに、それを発展させて、「『−3年前』はどういう意味?」という言葉遊びのようなことを学習します。
ここでは、結局$3-(-3)=3+3$の変換をすんなりできるようにするために、意味づけの学習をしています。
けれど、これって、わからない子にはわからないのです。しかし、$3-(-3)$が$3+3$になるのを機械的に覚える以外に、言葉でも感覚として持ってもらえたらいいなと思っています。
子どもの表現の中に、いい表現が出てきました。
ここは、先生が解説すればするほど、子どもにとってこんがらがる分野な気がしています。
今回は、子どもの表現を紹介します。
変な日本語を、ちゃんとした日本語になおそう

導入
まず、この導入は、「3年先を$+3$年と表現するならば、3年前を$-3$年」と表現することを学びます。
そして、その後、「大きい」という言葉だけを使って「小さい」を表現するように、片方だけの表現だけしか使わないようにするにはどうすればいいか考えます。
教科書では「『3大きい』を−(マイナス)を使って表現すると、『−3小さい』と表記する」との記載でざっくり終わっています。
ここで、子供たちの受け入れられない子は、『なんで?』と思考がシャットアウトしてしまうのです。
(私は、大学の位相幾何 トーラスの同位形を考えるときに、なぜそう考えるのか?と付いていけず、諦めました。)
そのシャットアウトをなんとか引き戻すのが、ここの教師のポイントになってきます。
ポイント
一つやって終わりにしてしまうと、子どもは???で終わってしまいます。
そこで、もう3つ。4つ例示を出してみます。
「『−3小さい』って普通使わないよね。これは数学の言葉です。『−3小さい』の正しい日本語は『3大きい』です。もう少し例を見てみましょう。」
「『−3kg重い』は、『3kg軽い』。『3本少ない』だったら、『3本多い』。では、『−5cm長い』だったら・・・」
このように、いくつか例示をしていきます。
ポイントは、日本語としては「正しくない」ということを強調することです。正しくないから、正しい日本語にしようと生徒は頭で変換を始めます。
そうすると子どもはこんなことを言い始めます。
「ー(マイナス)は、後ろの言葉を逆の意味にする力があるんですね。」
私は、この言葉が出てきた時、とんでもなく嬉しかったです。「どういうこと?」と問い返しました。
そうしたら「だって、『−3大きい』は、−(マイナス)がなくなって、『大きい』の言葉があべこべになって『3小さい』になるんでしょ。ー(マイナス)には、言葉を逆の意味にする力があるんだよ。」
と発言をしました。
みなさんはこの子どもの表現をどう思いますか?
これを使えば「3-(-3)=3+3」になる意味も、「演算のー(マイナス)は、符号のー(マイナス)を逆にする力がある」
という表現で計算も乗り切れると思ったからです。
この意見をクラスのみんなで確認し、言葉の意味でー(マイナス)の意味を掴んでいく授業は終わりました。
実生活の中から(2025.06.04追記)
こんな写真を見つけました。

東京理科大学内にある自動販売機のPOPです。
さて、今まで学習したことを使ってみましょう。
「-4℃冷た~い!」はどういう意味になるでしょう?
これが、東京”理科”大学の中の自販機だから面白いですね。
きっと、夏は、この自販機ではだれも飲み物を買わないことでしょう(笑)
最後に

もちろん、今回の授業は負の数の計算を意味理解するいくつもある方法の一つです。(詳しくは以下の記事をご覧ください。)
計算について色々説明がありますが、今回の方法が、啓林館ではとてもページが割かれています。
ということは、今回の説明が子どもたちにとってわかりやすい考えであると教科書会社からのメッセージと取れます。
今回の授業の考えを軸にしつつ、他の考えに広げていくのがベターかなと思います。
みなさんは、ここをどのように授業をしていますか?
ぜひコメントで教えてください。

過去に、今よりも薄いですが、この分野の教材研究した記事を書きました。合わせてご覧ください。
他にも、いろいろ正の数・負の数の学習の記録が残っています。ぜひご覧ください。





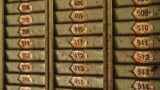
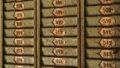

コメント