今日は、素数のお話です。
素数で、毎年生徒から質問されるのが、「なぜ1は素数ではないんですか?」という質問です。
皆さんはどのように答えていますか?説明できますか?
一緒に考えてみましょう。
素数の定義
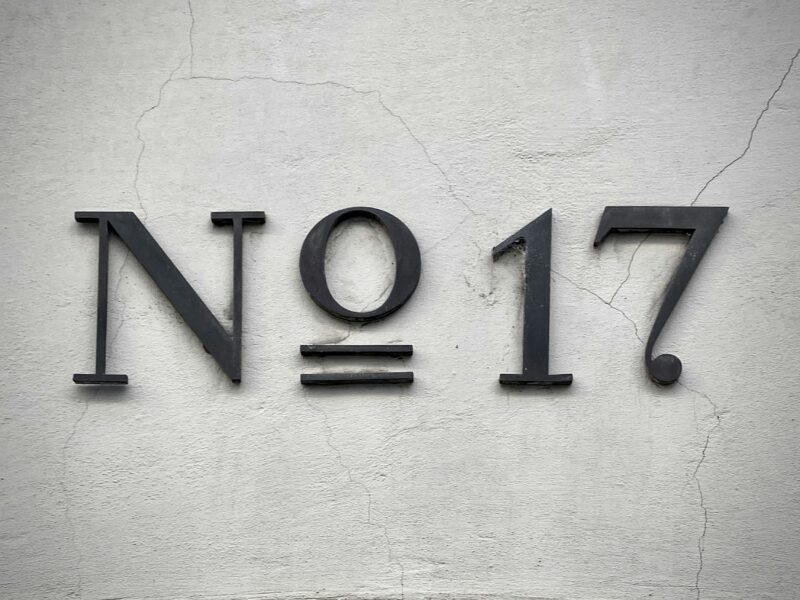
まず、素数の定義を見てみましょう。
私の学校で使っている教科書には以下のように書かれていました。
1とその数のほかに約数がない自然数を素数といいます。
ただし、1は素数に含みません。
ー啓林館.「未来へ広がる数学1」.P48
1行目の「1とその数のほかに約数がない自然数を素数といいます。」だったら、1は含んでもよさそうです。
でも2行目にわざわざ「ただし、1は素数に含みません。」と書いてあります。
なんか、人間が恣意的に1を外した感じがビンビンしますね。
これなんでなんでしょう?
数「1」の取扱いの変遷

歴史的経緯を見てみましょう。
実は、最近まで(1900年くらいまで)「1は素数!」という人と、「素数ではない!」という人で分かれていました。
wikipediaで検索をかけてみると・・・。
1 は素数か?
現代の定義では 1 は素数ではない。歴史を通しても 1 を素数に含めない数学者が多数派であったが、20世紀初頭の環論の成熟まで定義は統一されていなかった。プラトンやアリストテレスを含むほとんどの古代ギリシアの哲学者は 1 を数とさえ見なさず、素数性の考察の対象としなかった。スペウシッポスは 1 を数と見なし素数としたが、当時としては異端であった。この時代には素数を奇数の一部分と考え、2 を素数に含めない数学者もいた(ただしユークリッドをはじめとする多数派は 2 を素数に含めている)。アラビアではおおむね古代ギリシアに倣って 1 は数でないとされた。中世からルネサンスにかけて、1 が数として扱われるようになり、1 を最初の素数とする数学者も現れた。18世紀半ば、ゴールドバッハはオイラーに宛てた書簡で 1 を素数に挙げている(ただしオイラー自身は 1 を素数とは考えていなかった)。19世紀にも少数派だが 1 を素数に含める数学者はかなりいた。ハーディの『A Course of Pure Mathematics』では、1933年に出版された第6版までは 1 を素数に含めているが、1938年の第7版から 2 を最小の素数とするよう改訂されている。レーマー(英語版)の 1 を含む素数表は1956年まで出版された。ルベーグは 1 を素数だと考えた最後の専門的な数学者だと言われている。
1 も素数と定義すると、素数に関する多くの定理で、もとの「素数」を「1 以外の素数」と呼び替える記述の修正が必要になる。例えば 6 の素因数分解は、(積の順序を除いても)
6 = 2 × 3 = 1 × 2 × 3 = 12 × 2 × 3 = 13 × 2 × 3 = …
と無数に与えられることになり、自然数の素因数分解の一意性は「1 を素数に含めると」成り立たなくなる。エラトステネスの篩においては、1 も素数とすると、1 の倍数(すなわち他のすべての数)を消去し、残った唯一の数 1 を出力するので機能しない。さらに、1 以外の素数でのみ成り立ち、1 では成り立たない様々な性質がある(例えば、自然数とそれに対応するオイラーのφ関数や約数関数の値との関係など)。20世紀初頭までに 1 は素数ではなく「単数」という特別な分類に属するという見方が一般的になった。
ーwikipedia「素数」より
とのこと。
そもそも1を数の仲間に入れてもらえなかった時代があるのがびっくり。不遇の時代があったのですね。
そして1を素数に入れるのか入れないのかが決まったのもここ200年以内の話。
結構最近ですね。
「実は最近まで、素数が1に入るという人と、入らないという人がいたんだよ」と伝えるだけでも、数学もルールが変わるんだとハッとする生徒がいるかも知れません。
こういうルールが変わった話をすると、掛け算割り算の順序の話も子どもが「なるほど~」となるかもしれませんね。(詳しくは以下の記事をご覧ください)
中学生への説明

ただ、wikipediaの説明をしてもナンノコッチャと生徒はなってしまうでしょう。
具体的な話をしてあげましょう。
素因数分解の一意性
そこで、私は「素因数分解の一意性」を説明します。
素因数分解の一意性
2以上の整数は、順番の違いを除いて、1通りの方法で素因数分解できる。
という考え方です。
例えば、12を素因数分解(素数だけを使っての掛け算で表して)して見ましょう。
$12=2^2×3$
と表すことができますね。
もし、「1」を素数で入れてしまったら、こんな表し方も可能です。
$12=2^2×3×1$
$12=2^2×3×1×1$
$12=2^2×3×1×1×・・・$
と1をいくつでもつなぐことができます。
これだと、扱いがすごくめんどくさいですよね。
なので、1を素数に含めないという説明をしています。
エラトステネスの篩ができなくなる
wikipediaにもあるとおり、1を素数とするとエラトステネスの篩の計算もできなくなります。
詳しくはここには取り扱いませんが、啓林館の教科書には、素数の導出方法として載っています。
ここと絡ませながら話をすると、1を素数に入れると困ったことになることに生徒が気づくかもしれません。
最後に

今回は、なぜ素数に1を含めないかを説明しましたが、「1を素数に含めても」記述が少し面倒になるだけで、数学的に大きな問題が生じるわけではありません。
だからこそ、1900年ぐらいまで、素数に1を入れる派と入れない派で別れていました。
結局は素数に1を入れないほうが都合がよいとなりました。
そんなことを触れながら、授業をするだけでも、面白いと感じる生徒はいるのではないでしょうか?
ここの分野の授業、どういうふうにしていますか?ぜひコメントで教えて下さい!

素数をテーマにした授業案も記事にしています。合わせてご覧ください。
今回のような数学の歴史的経緯についても、いろいろ記事にしています。こちらも合わせてご覧ください。
参考文献・参考HP
参考文献
参考HP


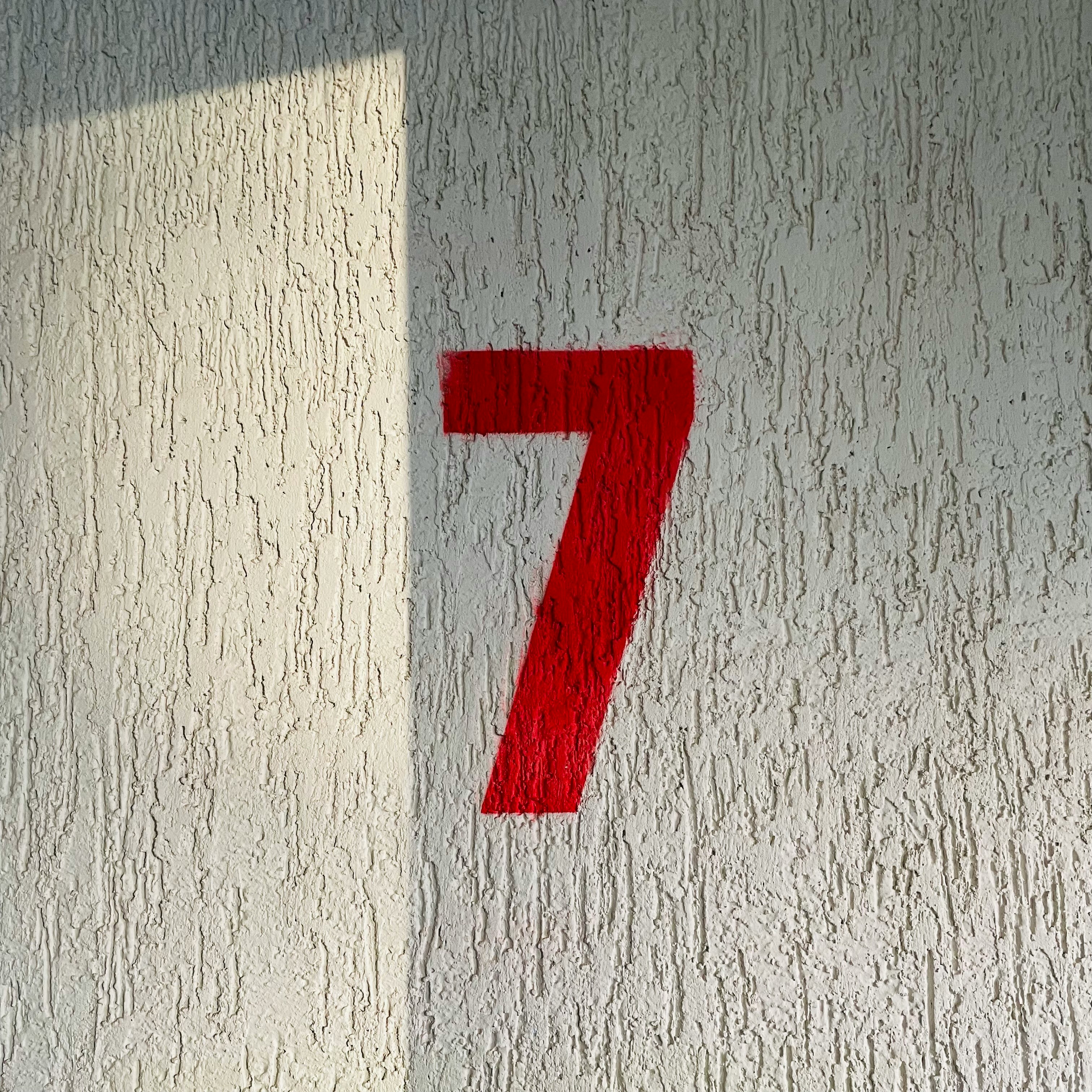








コメント