今年1年かけて、リーダー研修という研修を受けています。
その中の一つの柱として、授業について、検証改善できるように教育実践論文の書き方のレクチャーを受けています。
自分の自治体は、実は、教育論文は毎年書くのがマスト(今はそれほどでもないですが)でした。
なので、結構身近だったのですが、他の自治体の先生に聞くと、論文を書いたことがないという先生がほとんどでした。
最近はそういう文化も少なくなっているんでしょうか?
実は、教育論文の書き方を知っているだけで、授業の組み立て方や見方がわかるようになります。
一緒に勉強をしていきましょう。
教育実践論文の章立て

まず、教育論文の章立てを見ていきましょう。
これを知ることで、教育論文には、どのようなことが記述されないといけないかがわかります。
- 主題設定の理由
(1)生徒の実態
(2)学習指導要領の関連や、現代の教育の潮流、保護者の願い、学校の研究目標など
(複数ある場合は、(2)(3)と続けていきます) - 目指す児童生徒像
- 研究の仮説と手立て
(1)仮説
(2)手立て
(3)検証方法 - 授業の実際
(1)第1時間目(手立て1を用いて)
(2)第5時間目(手立て2を用いて) - 考察
(1)手立て1の有効性の検証
(2)手立て2の有効性の検証
(3)課題
このようになります。
「1. 主題設定の理由」で、児童生徒の実態を提示し、現在の教育状況を鑑み、目指すべき児童生徒の方向性を提示する。
「2. 目指す児童生徒像」で、端的に、児童生徒像を提示する。
「3. 仮説と手立て」で、目指す児童生徒像に近づけるために、どんなことをするのかを記述する。
「4.授業の実際」で、手立てを講じた授業の様子を記述する。
「5.考察」で、全体を俯瞰し、手立ての有効性を検証します。
長くて難しいと思うかもしれませんが、これは「指導案」の書き方と一緒です。
「児童生徒観」で、今の児童生徒の実態を書く。
「教材観」で、その教材の系統性を書く(これは教育論文には書きません)。
「指導観」で、児童生徒観、教材観から、どのような工夫をして授業を実施するかを書く(ここが仮説と手立ての部分になります)。
指導案は、公開する授業の流れと講じる手立てを書きますが、その時間に講じた手立ては、同単元の他の時間でも活用をするはずです。
単元全体の授業の様子を書くのが、研究論文になるのです。
研究計画の立て方
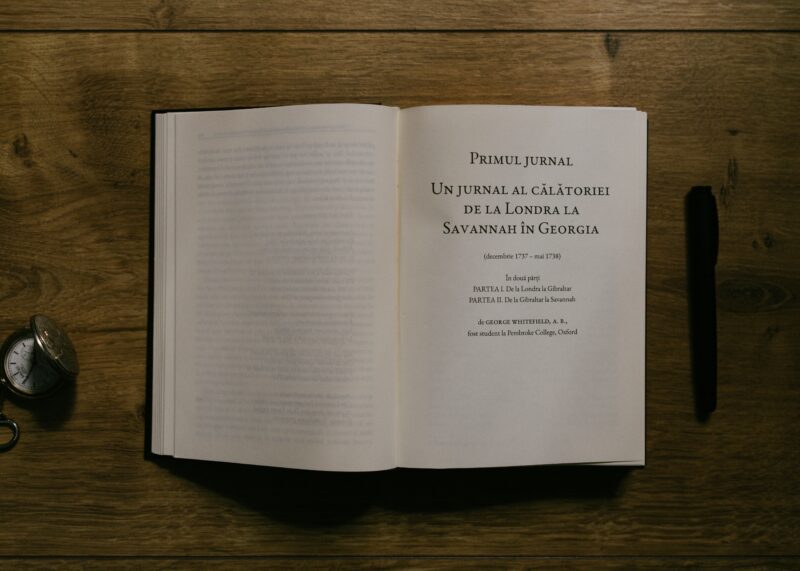
よく、授業を全部実施してから、研究論文にまとめるという方もいますが、お勧めしません。
思いつきでやって、授業をすると、単元を通しての指導ができにくく、体系的に論文にまとめられないからです。
だからこそ、章立ての「1.主題設定の理由」から「3. 研究の仮説と手立て」を授業実施前に、しっかり詰めておく必要があります。
その具体化の方法を今から説明します。
児童生徒の実態を把握する
まずは、児童生徒の実態を羅列していきます。
例えば、数学分野だとこんな感じになります。
- 計算問題は意欲的の取り組むことができる
毎日の1分計算トレーニングでは集中して取り組み、計算量を増やすことができている。 - どうやって解けばいいか全くわからないと、すぐに諦める面がある
- 友達と、答えの確認の時間を取ると、積極的に話す姿がある
この羅列の中から、目指す児童生徒像を設定していきます。
目指す児童生徒像の設定
児童生徒の実態をもとに、目指す児童生徒像を具体化していきます。
ただ、児童生徒像の設定には、実態だけでなく、「社会の潮流(学習指導要領)、校内研究や学校目標、児童生徒や保護者の要望(この項目は特別支援などで考えることが多い)」を元になどから具体化していきます。
特に以下の三つを意識して目指す生徒像を書いていきます。
- 「教科領域・場面等(研究対象)」
- 「具体的な手立て(研究のポイント)」
- 「目指す児童生徒像(結果の予測)」
上記の児童生徒の姿から、目指す児童生徒像を「中学校数学科○年(××を通して)対話的に学ぶ生徒」と仮にしておきましょう。
対話的に学ぶ生徒にするにはどうすればいいかを次の章「研究仮説の書き方」でブラッシュアップして、もう一度目指す児童生徒像に入れます。
研究の仮説の立て方
さて、先ほど目指す児童生徒像を「中学校数学科〇年(××を通して)対話的に学ぶ生徒」としました。
対話的に生徒が学ぶようになるには、教師が授業内で工夫を凝らさなくてはいけません。
この工夫が「研究の仮説」となります。
例えば、「最初の問題提示を、前時の学習を振り返りながら提示すれば、対話的に問題を解くだろう」
「問題提示の場面で、どんな数学的知識を使うか整理すれば、対話的に問題を解決をするだろう」
という仮説を立てます。
重要なのは「対話的に」学ぶために、「授業(単元)のどの場面で、どんな手立てを講じれば、(目指す生徒像)になるのか」の仮説を立てます。
仮説に備えるべき条件
仮説の文言は、こんな感じになります。
「□□において △△すれば ☆☆になるだろう」
| □□において | △△すれば | ☆☆になるだろう |
| 場・学習活動など | 問題把握・手立ての工夫 | 期待できる子どもの変容 |
| 「主題」よりも研究対象を絞り込む | △の部分:具体的、独創的に問題点等を改善する | 目指す児童生徒像が実現できる |
仮説で述べた手立てを、実践レベルで、具体的に述べましょう。
△の部分がどれだけ具体的になっているかが肝です。
主題を完成させよう
さて、以上から、手立てを加えた主題をもう一度書いてみます。
「中学校数学科⚪︎年 既習の学習と比較することで、対話的に学ぶ生徒」
このように書けば具体化してきました。
今回は例示的にやっているので、これでも薄いですが、皆さんが書けば、もっと具体的な主題になると思いまし。
主題と副題の書き方にもいろいろな作法があります。
提出する研究論文の過去データを見て、同じように記述をしましょう。
こんな場合になることが多いです。
<例1>主題 研究のねらい+対象領域
副題 手立て
中学校数学科○学年 対話的に学ぶ生徒
ー問題の提示に手立てを講じてー
<例2>主題 手立て
副題 研究のねらい+対象領域
問題の提示を工夫して学ぶ生徒の育成
ー中学校数学科○学年 対話的な生徒を目指してー
研究構想図を書こう

さて、研究指定校の研究発表に行くと、仮説と手立てを図にしてあることが多いです。
研究構想図といいます。
研究構想図を作ると、以下のようなメリットがあります。
- 研究の全体像、進め方や見通しがもちやすくなる
- 図にすることで、文章よりも伝わりやすくなる
→研究論文や紀要などにも使用できます。
できた仮説・手立てを図に落とし込んでみて、足りない部分はないかをビジュアルでみることで落としが見えてくるようになります。
研究構想図は、以下のようなシートを使っています。
研究構想図これは、研修で教えてもらったフォーマットです。
実際に書くとこんな感じになります。
06-R7研究構想図シート下から読んでいき、「生徒の実態」→「(生徒の実態を受けて)どんな仮説を立てて、生徒の成長を促すか」→「具体的な手立て」→「目指す児童(生徒)の姿」と上に上に見ていくこといなります。
最後に

今回は、教育論文の仮説の立て方に絞って、記事にしました。
最近は教育論文はもちろん、指導案を書かなくなった学校もあります。
もちろん、働き方改革の点では同意です。
けれど、「どんな児童生徒を育てたいか」を考え、「その手立てを講じていく。方法を考える」という営みは、授業として外すことのできない営みです。
逆に研究論文の書き方がわかれば、指導案やの書き方や授業の見方も養われます。
指導案や、実践論文は書かなくても、今回書いたことを頭に描きながら授業をしていきたいですね。
私は、今年の実践の成果ということで、1年に1本は教育実践論文を書くようにしています。
アウトプットをすることで、子どもの成長を客観的に把握できるようになり、来年は、自分はどんな力をつけるといいかなと考えることができるようになります。
もちろん、論文を書くには、インプットも必要になるので、力をつけるにはもってこいなのです。
ぜひ、一緒に、論文を通して日本の教育を盛り上げていきましょう。
教育論文や日々の実践で思っていることを是非コメントください!

こちらでは、論文を書くうえでのポイントを端的にまとめました。合わせてご覧ください。
以前書いた教育論文を一部公開しています。参考になれば幸いです。
指導案の書き方はこちらでまとめています。合わせてご覧ください。

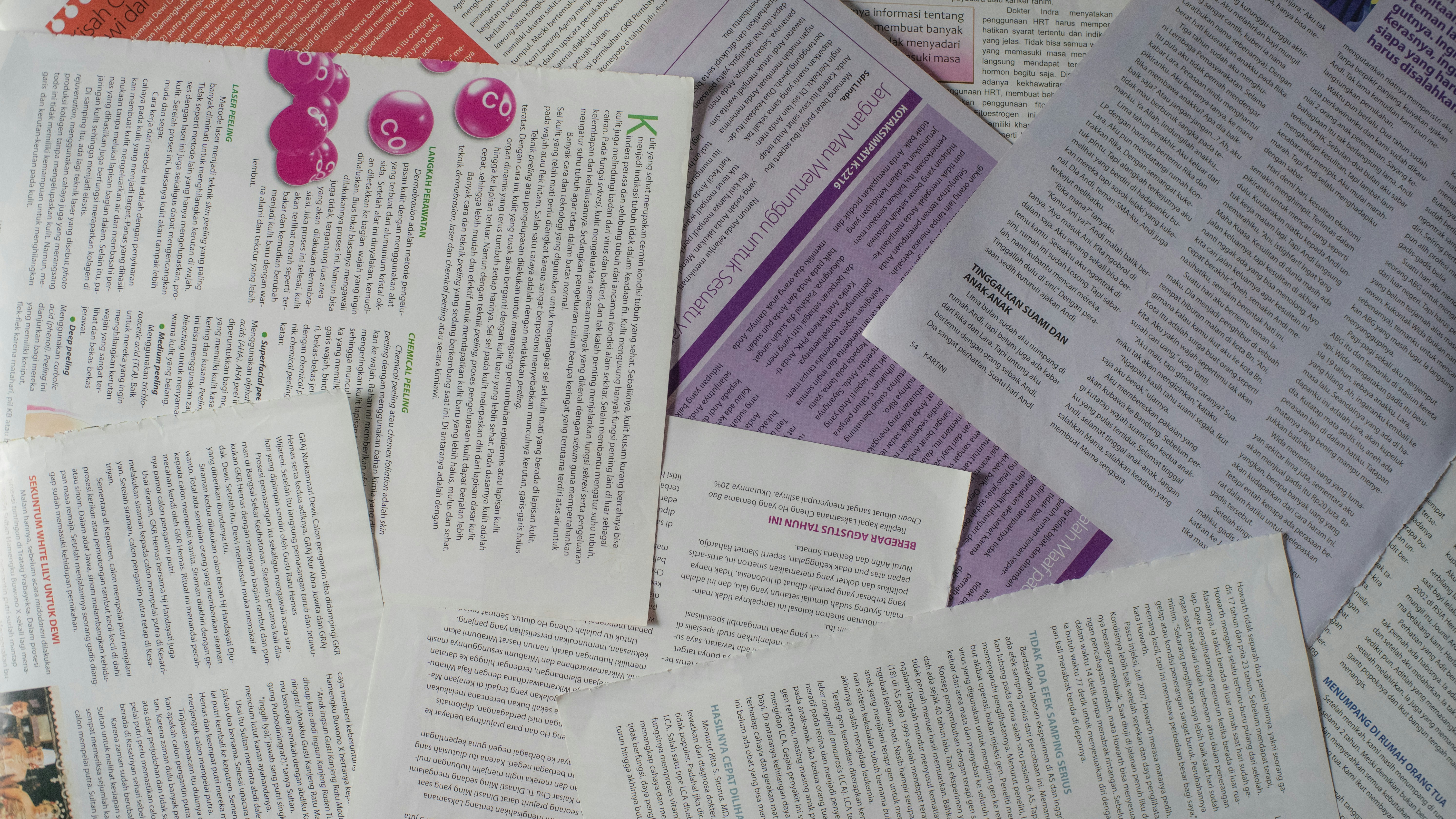






コメント