僕の大好きなPodcast ゆる言語学ラジオで、今井むつみ先生が何度も出演されていました。
そのときは、ふーんとしか思わなかったのですが、地元の図書館に行ったら、今井むつみ先生の本がおすすめということで、受付の眼の前においてあるではありませんか!
これは、読むしかないと思って、借りました。
今井先生は認知心理学者ということで、私達の教育の分野においても、様々な示唆を与えてくれます。
これらの本を読んで、考えたことを書いていきます。
「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?

先生(親御さんでも)が子どもと対峙していて、必ず一度は思うのが、「なんで伝わらないの?」ということでしょう。
数学などの勉強の説明をしても、ピンとこない。
よく、そういうのは、「実生活でその子に経験がない」からだと言われます。
「りんごが2つあります。3つもらったらいくつになりますか?」
りんごをもらうだけなら、誰でもできます。
その中で、数に焦点を当てて、子どもに経験をさせようなんて思う親は少ないと思います。
けれど、数に視点を当てない限り、子どもが数について考え出すことはないのではないでしょうか?
逆に、そんなことを(多くの親のように)教えることもなく、なんとなく普段の会話だけで身につける幼児はすごいのです。
実はこの話は、人工知能の話題の中でホットな話題です。
記号設置問題と言います。
人工知能の「記号設置問題(Symbol Grounding Problem)」とは?
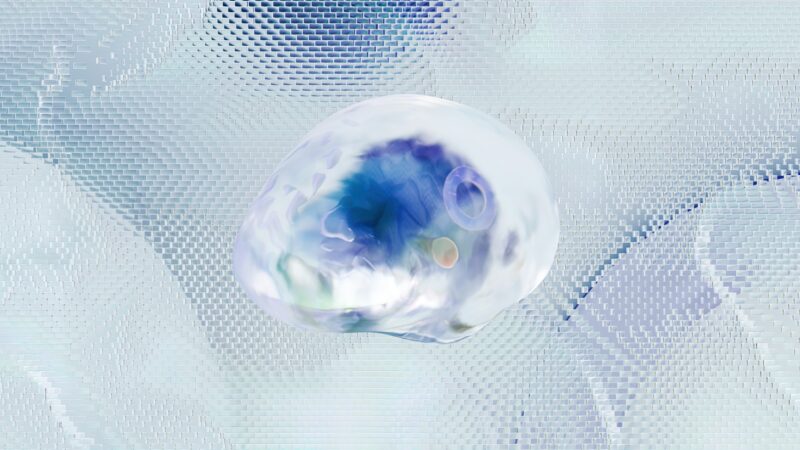
私たちが毎日使う言葉――「犬」「学校」「寒い」など――は、それぞれ現実のものごとや体験と結びついています。
たとえば「犬」と聞けば、犬を見たことや触ったこと、鳴き声やにおいを思い出しますよね。これを「記号(ことば)が意味と結びついている」と言います。
人工知能(AI)は、言葉や数字などの「記号」をたくさん扱います。でも、**AIが本当にそれらの意味を“わかっている”のか?**という深い問題があり、それを「記号設置問題」と呼びます。以下で順を追って説明します。
記号設置問題って何?
記号設置問題とは簡単に言うと:
「コンピュータやAIが使う記号(ことばやシンボル)に、どうやって現実世界の意味(=何を指すか)を結びつけるのか?」
という問いです。
AIは記号同士のルール(たとえば辞書やプログラム)を扱えますが、**その記号が現実の何と対応しているのか(=グラウンドされているか)**は別の問題です。
単に「犬 = 動物」「動物 = 生き物」とつなげただけでは、実際のワンちゃんを“体験”していないAIにとっては意味が空回りすることがあります。
なぜそれが問題になるの?(本質)
コンピュータは「記号の操作(syntax: 構文)」が得意ですが、私たちが感じる「意味(semantics)」は別ものです。
人間は感覚(見る・聞く・触る)や行動(抱っこする・散歩する)を通して言葉に意味をつけます。これに対して、多くのAIはテキストや数字のパターンだけで学んでいるため、言葉と現実世界が直接つながっていないことが問題になります。
この「記号は単に他の記号と関係しているだけで、現実世界に根ざしていない」という点が「記号設置問題」の核心です。
わかりやすい例(身近なアナロジー)
例1:辞書だけで学ぶAI
もしあなたが辞書だけで「犬」を学ぶとします。
辞書の説明は他の言葉で書かれており、その説明もまた別の言葉に頼っています。結局、言葉どうしが巡っているだけで、「実物の犬」を見たり触ったりしていません。これが辞書だけで学んだ「意味の空回り」です。
例2:翻訳ソフト
翻訳ソフトは文章のパターンを学び、正しい単語を選ぶことができます。でも翻訳ソフトが「犬が怖がっている」と言ったとき、本当に犬の気持ちを感じているわけではありません。単語の統計的な使われ方を真似しているにすぎないのです。
誰が言い出したの?(歴史のポイント)
この問題を明確に指摘したのは スティーヴン・ハルナッド(Stevan Harnad) という研究者で、1990年に「The Symbol Grounding Problem」という形で提案されました。彼は「記号どうしの関係だけでは意味は生まれない」と主張しました。
(余談)この問題は、哲学者ジョン・サールの「中国語の部屋」など、他の議論ともつながっています。どちらも「見かけ上の理解」と「本当に理解していること」の違いを問題にしています。
どんな方法で解こうとしているの?(代表的アプローチ)
研究者やエンジニアは、記号設置問題に対していくつかのアプローチを試しています。代表的なものを易しく説明します。
1. 身体を持つAI(エンボディメント)
ロボットにカメラや触覚センサーを備え、実際に世界を感知して動かすことで、記号と言葉を体験と結びつける方法です。
「これが犬だ」とロボット自身が見る・触る経験を持てば、記号が地面に根を下ろす(=ground)可能性が高まります。
2. マルチモーダル学習
テキストだけでなく、画像・音声・動画など複数の情報を同時に学習する方法です。文章と写真をセットで学ぶことで、言葉と視覚情報が結びつきます。
3. 人間との対話・参照学習
人と一緒にものを指して教える(「あれが犬だよ」)ような学習。言葉と実際の対象を対応づける学習方法です。
4. 知覚に基づく表象
心理学では「感覚に基づく表象(perceptual symbols)」の考え方もあり、意味は感覚経験から作られると考えます(専門的な理論は大学レベルになりますが、要点は「意味は経験に根ざす」ということです)。
現代のAI(たとえばChatGPT)と記号設置問題
最近の大きな言語モデル(LLM)は膨大な文章データから言葉の出現パターンを学びます。
そのため「とてもらしく話す」ことはできますが、多くの場合実体験に基づく意味理解を持っているとは言いにくいです。
言い換えれば、LLMは「言葉の使い方はうまい百科事典のような模倣者」ですが、現実の感覚や行動を通して言葉に意味を結びつける能力は限られています。
だから研究者は「視覚やロボット動作を学ぶモデル」と組み合わせる方向で研究を進めています。
よくある質問(Q&A)
Q1:AI(ChatGPTなど)は「意味」を理解している?
A:部分的には「使い方」を学んでいますが、人間のように五感で経験して意味を持っているかは疑問です。多くの研究者は「LLMは意味を模倣している」と表現します。
Q2:ロボットがあれば記号設置問題は解決する?
A:ロボットの感覚があると大きく前進しますが、「見る・触る」だけで完全に解決するかは別の議論です。意味の「深さ」や「主観」をどう考えるかは哲学的問題も含みます。
Q3:この問題はいつか絶対に解けるの?
A:明確な答えはありません。技術的に「よりよい」解決(感覚を取り入れたAI)は進みますが、「本当に理解する」とは何かという定義次第で答えが変わります。
まとめ(要点)
- 記号設置問題は、AIが使う記号に「どう意味を持たせるか」を問う重要な問題です。
- 人間は感覚や行動を通して言葉に意味を結びつけますが、多くのAIはテキストや記号の関係だけで学んでいます。
- 解決の方向としては、ロボットやマルチモーダル学習、人と一緒に学ぶ方法などがありますが、哲学的・技術的な議論は続いています。
- 教室では、辞書リレーや視覚教材を使ってこの問題を体験的に学べます。
学習と実生活を結びつける

ここ最近は、特別支援学級を持つことが多くなりました。
数学に授業では、1〜10を教えることを頑張っています。
そこでは、卵(1パック10個入り)のケースを使って、卵の収まる1つ1つの場所に「1、2、3、・・・」と一緒に数を数えながら、おはじきを入れていったり、卵ケースの中に入っているおはじきを数えさせたりしています。
そうすることで、5の固まりや10の固まりが見えやすくなるようになると思っているからです。
これを、1年(下手すれば中学校3年)かけて、手を変え、品を変え、繰り返し指導をしていきます。
そんなふうに指導を積み重ねることで、やっと身につくわけです。
まさに生成AIが行なっているデータのインプットを、実生活の中で繰り返し膨大な時間をかけて行うわけです。
翻って、普通の授業では、そんなことはしません。
それはある程度、子ども達には、もともとの経験があり、そこを土台として、学習ができるだろうという見立てのもと授業を行なっています。
そこに、こちらが見立てている基礎がないと、結局、子供は理解できないし、お互い困ってしまうというわけです。
単に勉強ができないのは、学力や本人の知的な力だけではなく、生活経験という観点からも見直しをしていく必要がありそうです。
さらに、1〜10が分からなければ、100という数、1000という数は理解が困難になるでしょうし、方程式のような抽象的な学習はますます困難になるでしょう。
昨今では、「自由進度学習」とか「個別最適な学び」という言葉がホットです。
教師として、学校として何を目指すべきなのか、個別最適な授業をすればいいのか、システム的に可能なのかと、考えさせられてしまうワードだなと常々思います。
最後に

この本は、ぶっちゃけすごく難しかったです。
冒頭で紹介したPodcastで、内容は一部ふれていますし、少しは分かっていたつもりですが、それでも難しかったです。
もう少し理解を進めていく上で、今井むつみ先生が鼎談している、「生成AI時代の言語論」を読みました。
光村図書の5年国語の教科書でも「言葉の意味がわかること」として、今井むつみ先生が書き下ろした説明文が載るようになりました。
また、今井むつみ先生は、「算数文章題が解けない子ども達」という本も書かれています。
今回は、生成AIから、学力や学校の在り方についてアプローチしてみましたが、こちらの本も今の学校の在り方を考える上で参考になりそうです。これも読んでみたいと思います。
今回は、取り止めのない話になってしまいました。
というのも、今井先生の持っている疑問は、とても壮大で、さまざまな分野に影響を与えていると考えるからです。
ぜひ、一度手にとって、今井むつみ先生の問題意識をのぞいて見るといいでしょう。
今まで考えなかったような世界が目の前に広がります。
ぜひ感想をコメントで教えてくださいね。

AIについて、いくつか記事にしています。以下は特に今流行りの生成AIの特徴をまとめてみました。
以下の記事では、生成AIを授業で使っています。
ただ、私はICTの利活用も含め、生成AIやタブレットを学習で使うのは懐疑的です。(以下の実践でも、教員が資料提示には使っていますが、子どもは授業内で触っていません)
AIを利用するなら、どんな目的で使うかを考えながら使う必要はありそうです。
用語について
- 記号(symbol):ことばや文字、記号など、何かを表す「しるし」。
- グラウンディング(grounding):記号を現実世界の対象や体験と結びつけること。
- エンボディメント(embodiment):身体(ロボットのセンサーや運動)を通して知識を獲得する考え方。
- マルチモーダル:テキスト・画像・音声など、複数の情報モードを同時に扱うこと。
参考文献・参考HP
参考文献
Audibleに入会すれば、「言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか」を無料で聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!
Audibleに入会すれば、「算数文章題が解けない子どもたち こどば・思考の力と学力不信」を無料で聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!
参考HP














コメント