最近哲学関係の本を読んでいます。
哲学の本というと、その哲学に関する知識を紹介する本が多いです。
不満だったのが、哲学が実生活のこんな所で役に立ったよ!ということを紹介する本がなかったことです。
そんな本がないから哲学って難しい頭でっかちの学問だと言われるのではないか?と思っていました。
そんなときに出会ったのが、苫野一徳先生の「子どもの頃から哲学者」でした。
この本は、作者の苫野一徳先生の少年から青年時代の成長期です。
著者が自分の少年時代を振り返り、哲学を使って自分の行動を分析しています。
また、青年時代には、哲学を知ることで自分はどう変わることができたかを詳しく述べています。
まさに、哲学を知って人生が変わった人のエッセイです。
これを読んでいてドキッとした一説があったので紹介します。
言葉を弄ぶのは危険
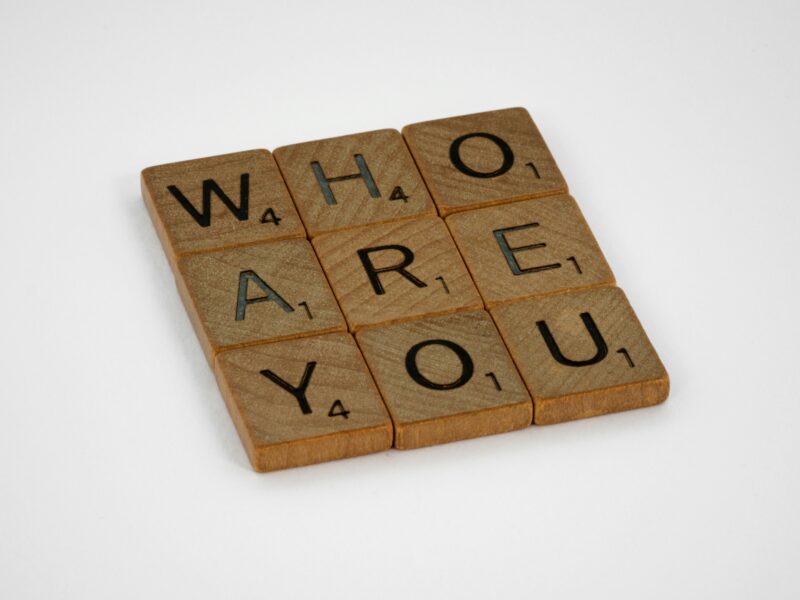
この本を読んでいて、ふーむと思ったのは以下の文章です。
哲学に興味のある若者は、よく、難解でやけにカッコイイ、哲学用語にハマってしまうことがある。「超越論的」とか「存在論的」とか、「世界ー内ー存在」とか「脱構築」とか、専門用語を知ると、それらをもてあそびたくなってしまうのだ。
でも僕の経験からすると、こうした言葉にイカれた人たちの奥は、これらの言葉の本当の意味をよく分かっていない。それもそのはずで、その本当の意味を理解するためには、やはりその前段階の哲学しをちゃんと理解していなければならないからだ。にもかかわらず、そのかっこよさに魅せられた若者たちは、これらの言葉に自分勝手なイメージを乗せて、それでわかったような気になってしまうのだ。
ー「子どもの頃から哲学者 ~世界一おもしろい、哲学を使った『絶望からの脱出』!~」.P190
この言葉を読んで、ふと思ったのが、最近の教育界の流行です。
最近だと、「個別最適な学び」だとか、「自己調整学習」といった言葉をタイトルに冠した教育書がたくさん出ています。
ただ、読んでみると、本当にそうか?と思ったり、これで本当に授業が成立するの?なんて思ったりをしてしまいます。
これはよく教員界隈にある悪口ですが、「教育書を出している先生のクラスは、実は毎年学級崩壊を起こしているよ」なんて言葉も聞かれます。
自分の周りでは教育書を出している先生を見たことないので、実際のところはよくわかりませんが、その先生がやっている実践が、目の前の生徒に合わずに先生のひとりよがりで行われているとしたら、崩壊するのは火をみるより明らかです。
ただ、実践の裏にしっかりとした理論と知見があれば、学級崩壊まではいかないはずです。
Xをみているとそんなことが散見されているように感じます。
自分の失敗から
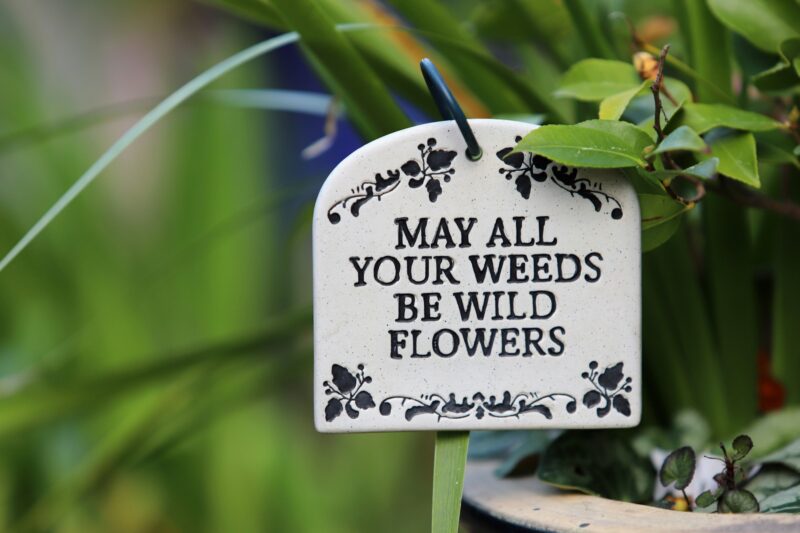
といっても自分も同じ経験をしています。
自分も新人の頃、とにかくやたらめったら筑波大学附属小学校の実践を、焼き増しして行いました。
確かに、今まで見たことない子どもの表情や、ワクワクしながら授業に取り組んでいる様子もありましたが、反面、普通の授業ではありえないくらいの粗末な理解で終わらせてしまった授業もたくさんありました。
結局は、筑波附属小学校の実践に引っ張られるあまり、子どもを置いてけぼりにした授業になってしまったんです。
よく、大学のゼミの先生に「『教育の流行と不易』とはなんぞや?」と問われました。
大学の頃は答えることができませんでした。
今なら少し意味がわかる気がします。
流行は、今だと、「個別最適な学び」とか、「自己調整学習」が当たるでしょう。
不易の部分は、「子どもの成長を願って授業をする。教育をすること。」だと答えます。
以下の記事にも書きましたが、一番大切なのは子どもが成長することです。
それを忘れてはいけないなと感じました。
最後に
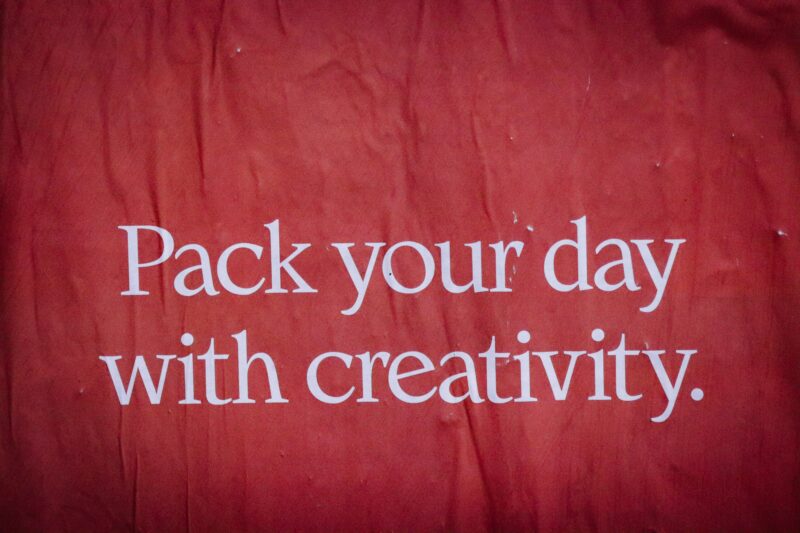
哲学の分野でも、教育の分野でも(ありとあらゆるところで)今流行りの言葉を使って、相手を説得したり、言い聞かせたりする場面に出会います。
でもそれは本質をついていないことが多いのではないでしょうか?
私は最近言葉の一つ一つを気をつけるようになってきました。
自分の理解を正しく相手に伝えるためには、それに裏打ちされた知識が必要だと感じるようになったからです。
というのも、今年、学術論文を提出し、採用されました。
この学術論文は、人類が滅ぶない限り、永遠に記録として残っていきます。
そんな大切な記録が、間違った言葉や理解で後世に知識として継承されると誤解を後世に伝えることになります。
論文の審査の過程(査読と言います)で、審査委員からたくさんの指摘がありました。
自分の理解が甘かったのを痛感すると同時に、もっと知識をつけて、審査委員と渡り合えるようになりたいなと思いました。
また、教員としても、間違った言葉や知識で子どもに迷惑や誤解を与えないようにしないとと改めて思いました。
今回は苫野先生の「子どもの頃から哲学者」を読んで、つい考えてしまったことを記事にしました。
皆さんはいかがでしょうか?そんな経験はありませんか?ぜひコメントで教えてください。

苫野一徳先生の本を他にも読んでいます。感想を合わせてご覧ください。







コメント