みなさんは、自分の勤めている学校の(または、自分が通っていた学校の)校訓って言うことができますか?
体育館の舞台の脇に掲げられていたり、学校の校庭などの脇に石碑が立っていたりするのではないでしょうか?
子どもに「自分の学級の学級目標は何?」と聞いたら答えることができると思いますが、「校訓って何?」と聞かれたら答えられる子ってどれだけいるのでしょうか?
学校では様々なところで目標が掲げられます。
学級目標(学級訓)しかり、生徒会憲章が定められているところもあるでしょう。
もちろん学級目標は大事です。
ただ、校訓もみんなで復唱するのもいいなと最近感じました。
そのエピソードを紹介します。
校訓を唱和しよう

さて、「二番経営 〜組織を支えるNo.2の悲喜こもごも〜」を聞いています。
その中で、松下電器産業(現パナソニック)の高橋荒太郎さんの話が紹介されました。
朝会で、経営の基本方針である「七精神」を唱えていないことで問題になったそうです。
労働組合が反対したから「七精神」を言わなくなったかということでした。
そこで高橋荒太郎さんは、労働組合の幹部のところに行って、次のような話をしました。
「貴重な就業時間の一部を使って、朝会をやり、社訓を唱和しているのは、会社のためではないのです。人間は誰でも完璧にはいかない。日々謙虚に反省しなければならない。良き産業人として、良き社会人として、良き家庭人として、お互いに過ちのないように期そうではないか。これを唱和する瞬間だけでも反省している時間にしようではないか。だから真の松下電器の経営になっていないのです。みんなの反対がないのなら、明日の朝会から復活させたい。」
朝会で、「七精神」の復唱を再開したところ、半年で赤字は解消し、経営が上向いたとのことでした。
さて、学校の校訓の話に戻ります。
今、勤務している学校の校長先生は、入学式や各学期の始業式・終業式で、必ず校訓について触れます。
入学式や卒業式では流石にできませんが、各学期の始業式・終業式では、みんなで校訓を唱和するように促します。
はじめは、生徒も職員も恥ずかしそうにしてきましたが、1年間やってきて、声が出るようになってきました。
校長が唱和を求めてきたときには、自分も恥ずかしい、意味があるかなと思っていました。
松下電器産業の「七精神」も、学校の校訓も、それぞれが体現したいと考えている社員や生徒の姿の理想像を語っています。
もちろん、この姿を体現するのは簡単なことではありません。
理想像に向かって、今の自分を反省し、己を高めようとする姿がとても大事だと感じています。
この反省する時間って、みなさんの学校や学級って取れていますか?
自分も、どちらかというと、学級目標って本当にいるのかな?どうして、毎年作るんだろうなって思っていた次第です。
目標を作ったからって、子どもは変わらないんじゃないかとも思っていました。
けれど、先程紹介した高橋荒太郎さんの言葉を聞いて、たしかにそうだと思いました。
「人間は誰でも完璧にはいかない。日々謙虚に反省しなければならない。良き産業人として、良き社会人として、良き家庭人として、お互いに過ちのないように期そうではないか。これを唱和する瞬間だけでも反省している時間にしようではないか。」
子どもだったら、なおさらです。
教育で大切なのは、教育基本法の第1条にも書かれているとおりです。
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
ー教育基本法 第1条
もちろん義務教育の内に人格の真の完成なんてできません。
そこに向かって己を高め続けることが大切です。
そのための校訓、そのための学級目標なのではないでしょうか?
そして、目標の大切さは、高橋荒太郎さんの言っているとおりです。
ぜひ、この言葉を胸に、新学期の学級目標はもちろん自身の目標を決めていきたいですね。
学級目標の決め方については、こちらに書きました。合わせてご覧ください。
最後に

今回は、学級目標・校訓についてお話をしました。
いろんな教育書や教育雑誌で学級目標の話題が出てきます。

ただ、学級目標は決めて終わりではありません。
決め方のテクニックだけわかって決めていけばいいものではないのです。
決めてからのほうが大変です。
その理想像に向けて邁進してかなければならないからです。
そんな覚悟を教師と子どもたちとで一緒に持って、学級目標を決められれば最高ですね。
そのなかでも、校訓に触れながら学級目標を決められれば、きっと良い方向性が見えることでしょう。

学級目標などの目標についてはいくつか記事にしています。合わせてご覧ください。
参考HP
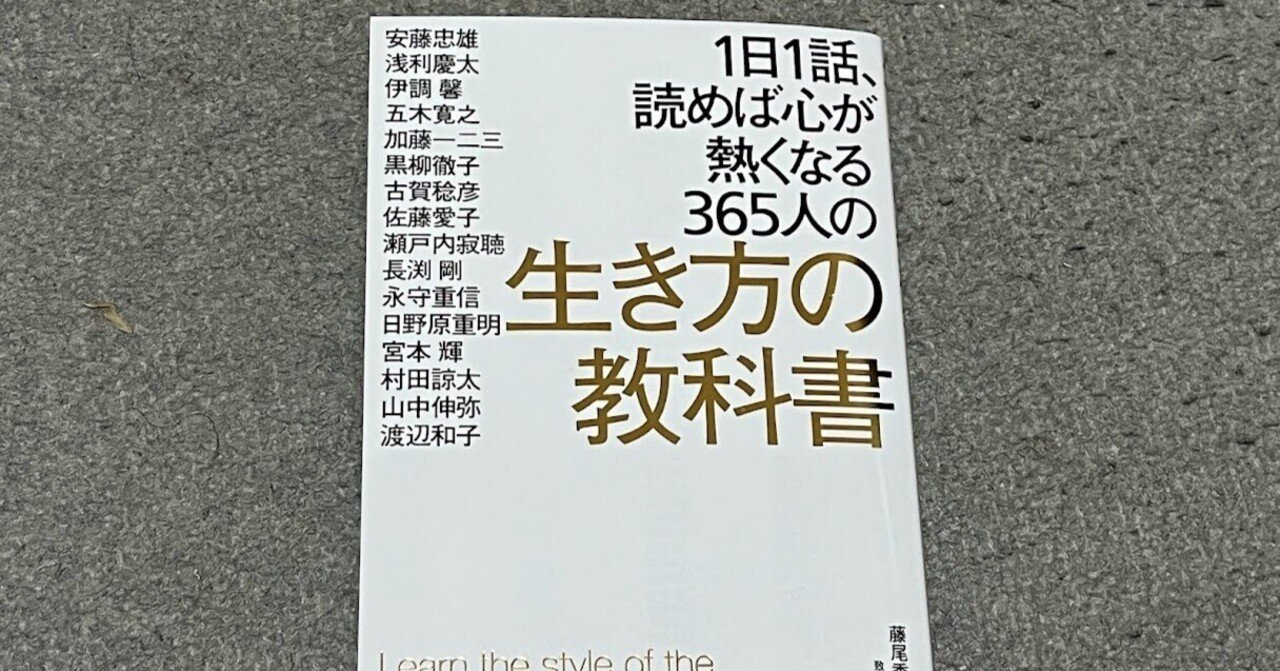







コメント