久しぶりに道徳の授業をしました。
結構楽しくできました。
というのも、日々の生徒の日記に、授業について書いてきてくれた生徒が何人もいたからです。
算数・数学以外にも、道徳の授業記録を残しておくと、いいかなと思って記録を残していこうと思います。
記念すべき第1号です。
2025年11月に実施しました。
あらすじ
宇宙人は、地球の少年「リツくん」を定点観測している。
ある日1人で食堂を訪れたリツくんに、周りの大人たちが各々の職業観について話を聞かせました。
仕事が楽しい人も、楽しくない人もいる。仕事への取り組み方や考え方が多種多様であることを感じた宇宙人は、地球人の仕事はなぜこんなにうまくいっているのか理解できないでいます。
出典:「つむじ風食堂と僕」、筑摩書房、2013
主題名・ねらい
主題名
仕事の面白さとは C(13)勤労
ねらい
大人たちが「働く」ことについてアドバイスをする様子を観察している宇宙人について話し合う活動を通して、勤労の尊さや意義について理解し、自分だったらどうするかと考える態度を育てる。
授業の流れ(T:教師 S:生徒)

導入
T:そろそろ、職場体験ですね。みなさんは、いま、どの職場に行こうか迷っていると思います。
今日は、「仕事」について考えていきましょう。
では、今日の題材「宇宙人」を読みます。
(「宇宙人」を読む)
感想を教えて下さい
T:では、この話を読んで感じたこと、なんでもいいので教えて下さい。
S1:人によって仕事も見方が違うと思いました。
S2:文中で「働いていない人」が出てきました。その人の話を聞いて安心しました。
T:「安心した」と言いましたが、なぜS2君は安心したと思いますか?他の人わかりますか?
S3:職場体験とかが行事であって、仕事というものが目の前に見えるけれど、「まだ仕事のことを深く考えなくていいと言っている」から安心したんじゃない?
T:S2くんそう?
S2:そうです。
「それぞれの人が言っていることで印象に残った部分とそれはなぜかを教えて下さい」
T:いま、S2が「安心した」といったよね。今回の話はこのように、いろんな人がいろんな立場で仕事について話をしています。
もう一度それぞれの人の言葉を読み直して「印象に残った部分とそれはなぜか?」を教えて下さい。
「イラストレーター」の言葉を読んで
S4:イラストレーターの言葉が気になりました。「好きと言っている反面、仕事のキリがない」と言っています。好きという気持ちだけでは、仕事を選んじゃいけないのかな?と思いました。
S3:キリがなく仕事をしていて、嫌いにならないのかな?
「やりたくない仕事をしている人」の言葉を読んで
S5:やりたくない仕事をしている人の話をみて、そういう人は周りにもいると思いました。やりたくない仕事をしている人は楽しいのかな?と思いました。
S6:この人の話を読んで、リアルだなと思いました。
S4:やりたくない仕事をしている人もいて、大人もそういうことを思うんだなと思いました。やりがいがある!みたいな大人の言うことを鵜呑みにしない。
S7:やりたいことのできる人は一部の人だけなんだなと思いました。
「魚屋」の言葉を読んで
S8:昔ながらの技術で、昔と変わらず魚を届ける。新しいものだけがいいってわけじゃないということを思った。
「働いていない人」の言葉を読んで
S9:「仕事のことはまだ深く考えていい」と書いてあったけれど、自分がいざ就職する数年後、世の中は変わっている。考えるのを後回しにしていて、いざ就職するときに、やりたいことができなくなるのが怖い。(今から仕事について考えないといけない)
教師からの問い返し「みんなの意見を聞いてどう思った?」
T:皆さんの意見はよくわかりました。「やりたくない仕事をしている人」これは、それでもなんで仕事をしているのかな?そうだね、お金のためだね。こういうのを「ライスワーク」と言ったりします。逆にイラストレーターみたいに、仕事を生きがいや人生のようにやれていることを「ライフワーク」ということがあります。
さて、今みんなが出てきた意見をみて、どんなことを思いましたか?教えてください。
・・・ここは、意見が出ませんでした。
→待てば意見が出てきたかもしれませんが、時間が残り3分だったので時間切れでした。発問に対して、レスポンスがくるまで時間がかかります。学級風土的にも、自ら手が上がることが少ない学級と聞いています。しばらく、「待つ」ことを大切に、自ら手を挙げられる生徒を育ててみたいと思います。
終末「ふりかえりを書こう」
最後、ちょっと意見が言いにくかったかもだけれど、振り返りに思ったことを書いてくださいね。
終わります。
ふりかえりの記述
- 自分のやりたい仕事、好きな仕事を必ずしもできるかわからないし、仕事を続けていっても違うと思うかもしれない。仕事を選ぶって大変。
- 仕事をする理由は人それぞれで、好きという理由だけで仕事を決めないほうがいいのかもしれない
ワークシート
ワークシート(宇宙人)授業を終えて

この授業は、自分の学校のクラスで、欠員が出たので、急遽、補充で行った授業です。
その中では、子供達は和やかに意見を出してくれたと思います。
担任からは、「なかなか意見が出ないんですよ。」と悩んでいることを聞いていました。
そこで意識したのが、「発表してください」と言ったら、たっぷり待つことです。
「5分までは待とう」という意識でいました。
1分経つと、一人、もう1分経つと、また1人手を挙げました。そこで挙手したことを褒め、意見を発表してもらいました。
待つことで、指名をしなくても、生徒の意見を汲むことができました。
このやり方の根底には、「ネガティブ・ケイパビリティ」という考えがあります。
なので、発問は本当に1つしか考えませんでした。
問い返し発問が盛り上がればよかったのですが、そこは時間切れ(残り2分しかありませんでした)。
ここから生徒を鍛えていくしかないだろうなと思います。
飛び入りにしては及第点の授業にできた面白い教材でした。
また、授業をしたら報告します。


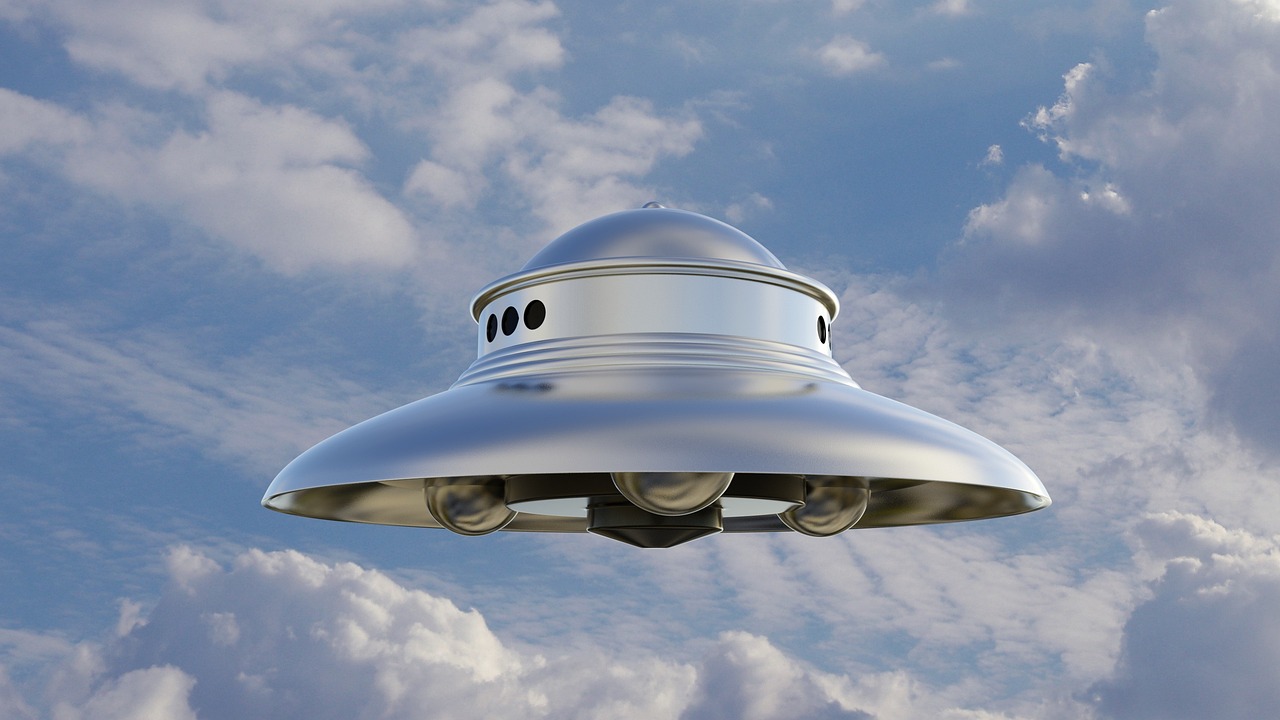




コメント