「主体的で対話的な学び」という学習指導要領の文言のもと、日本の教育は今頑張っています。
ところで、「主体的」な姿と聞いて、どんな姿を想像しますか?
また、自主性という言葉もあります。
自主的な姿はどんな姿でしょうか?
道徳の授業における価値項目でも「自主・自律」という項目があります。
皆さんは、「主体的な姿」と「自主的な姿」と聞いてそれぞれ違いや具体的な姿を想像できますか?
今回「超実践的幸福論」の「#34 独り時間と社交時間。幸せを生む『黄金比』はどこにある?」を聞きました。
その中で、主体性と自主性の違いについて話題に上がりました。
自分って「主体的」「自主的」な姿を区別してあまり考えてこなかったなと思ったのと同時に、学校って主体的とは名ばかりの自主的な姿を子どもたちにずっと求め続けていた。
そこがチグハグしているから、いまだに主体的な姿の話になると、モヤモヤするんじゃないのかなと思いました。
今日は「主体性」「自主性」について詳しく話しながら、子どものあるべき姿を考えようと思います。
裙本さんの考える自主性と主体性

自主性は、昔の優秀な人は自主性がすごかった。
宿題とか、与えられて範囲で自主的に自分の意志で思いっきりやるのが自主性。
主体性は、自分で決めたこと、自分で考えたことを思いっきりやるのが主体性。
今、重要なのは、主体性をもった生徒を育てること。
与えられた教科書の中で自主的に勉強する人は、AIに勝てない。
課題を自分で見つけて、そこになにか繋がりがあるんじゃないのかと考えるのがいま大事なのではないか(という教育の話を聞いた)
主体性は、人生の主導権を握ること。自分で自分の道を作って動いていくこと。
自主性は、決められたレールを自ら歩くこと。
主体性のほうが大事だと思う。
ー13分40秒頃 裙本さんの発言より(筆者意訳)
学校での自主性と主体性の混同
「自主学習ノート」という宿題から考える自主性
学校で、「自主学習ノート」なる宿題が存在する学校があります。
皆さんの学校はありましたか?
私も、自分が中学校時代に自主学習ノートがありました。
やり方は「学校で勉強したことを、家庭で毎日ノート1ページ分やって、それを毎日提出」でした。
自分で学習したことを決めて、家庭で学習しなさいねということなのです。
宿題で提出を求められるものなのに、『自主』学習とはなんぞや?
自分は中学時代に、しばらく(なんか全てが嫌になって)宿題を出していなかった時期がありました。
担任から、「罰として毎日10ページやってだせ!」と言われました。
その時は強制学習ノートなのでは?なんて思いました(笑)
そう思うと「自主学習ノート」って今の時代にそぐわないなとは感じます。
だって、結局やっていなかったら「やりなさい!」と教師からけつを叩かれるわけです。
なんで、自主的な姿に価値が置かれているんでしょうか?
三宅香帆さんの「なぜ働いていると本が読めなくなるのか?」の中に、1970年台の労働観について書いてありました。
そして1970年代に入り、もう一つ企業文化に変化が訪れる。企業内許yいくにおいて「自己啓発」という言葉が使用され始めたのだ。(中略)
要は「自己啓発」しているかどうかー自発的意思で能力をあげているかどうかを、セミナーの出席度や資格の取得度や勤務日数で判断していたのだ。社員の評価項目の中に、「自己啓発」項目を作ることで、現在の能力値ではなく、積極性や協調性という「態度」を企業は評価することができるようになった。
つまりは企業が期待するサラリーマンであってくれるための努力を、社員が勤務時間外に自発的に行うことーそれは「自己啓発」という概念に収斂されていった。
ー三宅香帆.「なぜ働いていると本が読めなくなるのか?」.P133~P134
なるほど、ここまで遡れば、学校で自主学習を奨励する意味もわかります。(自主学習ノートが生まれたのが1970年かはわかりませんが)
要は、1970年代の社会人にとっても自主的に学習をするということは、キャリア形成においてとても大切だったんです。
社会が変わり、学習指導要領の変化があっても、学校現場では、「自主学習ノート」として、そのまま残っていたことが考えられます。
ちなみに、1969年発、1972年施行の中学校学習指導要領の総則には、
生徒の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように指導すること。
という文言がありました。もちろん主体的という言葉はありません。
追究の時間から考える新しい潮流
他方、本校では、「追究の時間」というものを始めました。
自分で学習課題を設定し、それについて追究をする。
追求する内容は、生徒の興味関心に沿ってで決めるということにしています。
生徒によっては、「釣りのルアーを作る」とか、「かっこいい絵をかけるようにする」と追究課題を作り、探究の時間は生き生きと取り組んでいます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
生徒の中には、何を探究したらいいのだろうと迷ってしまう生徒もいました。
ただ、この悩みを中学時代の今、経験できたことは良かったと考えています。
社会に出たら、自分でなにか課題(とまではいかなくても「生きがい」とか、「やる気」)を見出して生きていかなければ楽しくありません。
学校では、目標を与えられ過ぎて、自分で決定するということが少なすぎます。
今回の「探究の時間」は、生徒が答えのない社会を生きていくうえで、一つ大事な経験になると考えています。
さて、このムーブも、現代の労働観と関係あるのでしょうか?
先ほど引用した「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の2010年代以降の労働についての見方を見てみましょう。
ノマド、副業、個で生きる
大企業の長時間労働是正がなされる一方、2000年代からはじまっていた日本社会の「やりたいことを仕事にする」幻想は、2010年代にさらに広まることになる。
働き方改革が始まる少し前ー2014年(平成26年)からはじまったYouTubeのCMキャンペーンのキャッチコピー「好きなことで、生きていく」を覚えている人もいるだろう。
そう、会社に頼る代わりに、一方で「副業」や「フリーランス」といった働き方がもてはやされたのだ。会社や組織に頼らず、個で稼げ、と説かれる。「ノマド」という言葉も浸透し、立花岳志の『ノマドワーカーという生き方ー場所を選ばず雇われない人の戦略と習慣』(東洋経済新報社)が出版されたのは2012年(平成24年)のことだった。
この傾向は、働き方改革を経てますます強くなる。つまり会社で終身雇用に頼るのでなく、好きなことや自己実現を果たせることで、ことして市場価値のある人間になるべきだ、というメッセージが日本社会に発信されたのだ。
自分の意思を持て。グローバル化社会の中でうまく市場の波を乗りこなせ。ブラック企業に搾取されるな。投資をしろ。自分の老後資金は自分で稼げ。集団に頼るな。ーそれこそが働き方改革と引き換えに私たちが受け取ったメッセージだった。
ー三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」p217ーp218
それだけ、個に重点が置かれ、日本の社会も大きく変化しているのです。
その波にうまく乗らないといけないから、今の子は大変です。
もしかしたら、全員で同じことやっていた時代は幸せだったかもしれません。
だって、言われたことをやっていればOKだったのですから、考える必要はありません。
小・中学校時代から自分で考えて行動することを、学校現場で実践させるようになってきたのです。
現行の中学校学習指導要領にも、
基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮すること。
とあります。「自主」という言葉も残っていますが、「主体」という言葉の方が圧倒的に使われています。
本校の実践も始まったばかりなので、どう転ぶかはわかりません。
1年通しての生徒の様子は、どこかで報告できたらと考えています。
最後に
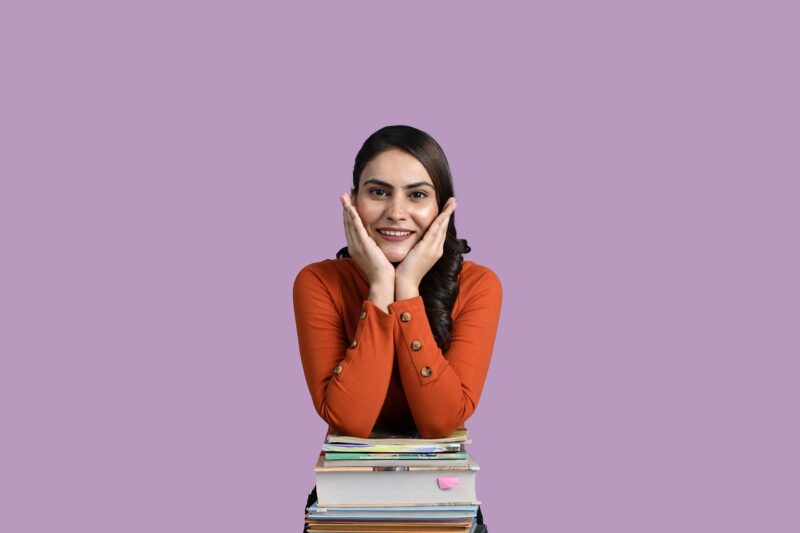
自主性・主体性という言葉をテーマに、最近の労働観も含め、教育のあり方を考える記事にでした。
ついつい、教育と労働は、切り離して考えてしまいがちですが、近年の労働観は教育にもずいぶん反映されていることが見て取れます。
2025年7月4日に次期学習指導要領において、「主体性」の評価は、5段階評価には入れないことが考えられています。
これも、時代でしょうか?
これからどう生きるか。
先生は、生徒を導くというよりも、一緒に考えていくといったスタンスが求められているかもしれません。
皆さんの学校、生徒の様子はどうですか?
ぜひコメントで教えてください!

超実践的幸福論を元に他にも記事を書いています。合わせてご覧ください。
参考文献・参考HP
参考文献
Audibleに入会すれば、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」を無料で聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!
参考HP










コメント