ベテランの先生を見ていて、何であんなにすごい授業ができるんだ。
アイデアの源泉はどこからきているんだろう・・・。
そんなふうに自信を失ってしまったことはないでしょうか?
また、成長したい、すごい授業をしたい。そんなことを1度や2度思ったことは誰しも必ずあるはずです。
仕事でも、趣味でも、できる人というのは、才能なのでしょうか?
実はそんなことはないのです。
用意周到にすることで、どでかいことを成し遂げることができるのです。
今回は「BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらは何をしたのか?」を読んで、考えたことをメモとして残したいと思います。
「ゆっくり考え、素早く動く」、「試作を繰り返すこと」
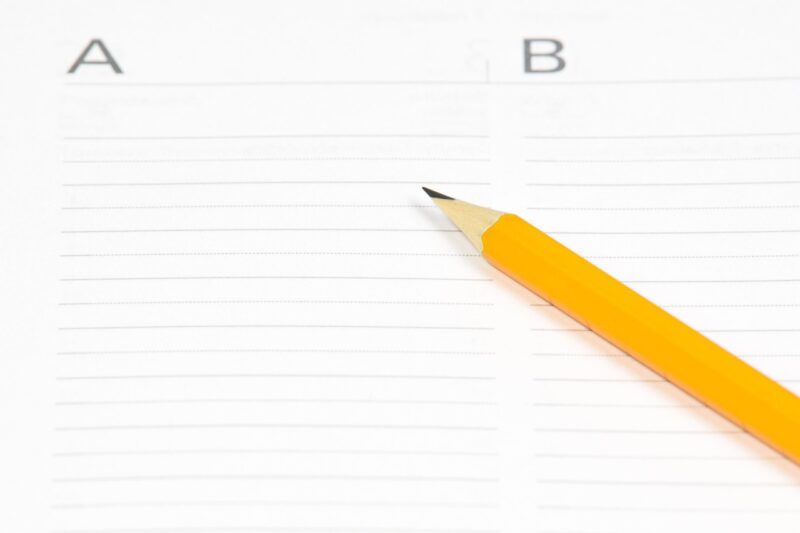
この本の主張はたった2つ。
- 「ゆっくり考え、素早く動く」
- 「試作を繰り返すこと」
たったこれだけです。
当たり前・・・。と思うことも多いでしょうが、いざ仕事の場面になると、できているでしょうか?
それぞれ見ていきましょう。
ゆっくり考え、素早く動く
プロジェクトが進み始めてから、変更を加えるというのは、コストが掛かります。
例えば、悪い意味で有名なプロジェクトとして、「オペラハウス」があります。
オペラハウスは、2003年に建築界の最高の栄誉とされるプリツカー賞を受賞しました。
また、2007年には、ユネスコの世界遺産に登録されています。

ただ、これだけ素晴らしいオペラハウスですが、作った当初は非難轟々でした。
設計者のヨーン・ウツソンは、完成を見ることなく、オーストラリアを後にして、死ぬまでオペラハウスを見ることはなかったのはご存知でしょうか?
それはなぜでしょうか?
最大の原因は特徴的な屋根です。
オペラハウスのデザインが決まったときに、デザインは決まっていたのですが、屋根をどのように作るか、具体的なところは、全く決まっていませんでした。
それでも、デザインが気に入った当時の州知事は、自分の任期中に完成させようとGoサインを出します。
慌てたのは設計者、ヨーン・ウツソン。
結局作っては、うまくいかず、壊す。壊しては作ると作業しているうちに、工期は、当初4年程度の見込みが、14年まで伸びました。
工費は、700万ドルの予定でしたが、最終的に1億200万ドルにまで膨れ上がり、当初の予定の14倍以上となりました。
結局ヨーン・ウツソンは、シドニー・オペラハウスの建設中に州政府との対立により辞任しました。後、ヨーン・ウツソンはオーストラリアに二度と足を踏み入れることはありませんでした。
彼は完成したオペラハウスを直接見ることはなかったのです。
これは、「素早く考え、ゆっくり動いた」ことで、うまくいかなかった事例の典型です。
まだ、オペラハウスは、世界遺産にまで認定され、汚名を返上したと言えるでしょう。
ただ、汚名を返上するに至らず、そのまま負の遺産として残っているものも、記録として残っていないだけで、たくさんあります。
日本のバブルのときに作った施設なんて、99%がそうなっていないでしょうか?
学校での「素早く考え、ゆっくり動いた」事例
これを聞いて、学校現場で似ているものがあると思いました。
それは「キャリアパスポート」。
導入されると聞いて、寝耳に水だった先生は多いハズ。
そして、どんなふうに作ればいいかも分からず、見切り発車したはずです。
調べたら導入されたのは、2020年とのことです。
もう導入されて5年経っていますが、活用されたということは聞いたことがありません。
私の学級もとりあえず作っていますが、、、。小学校から中学校に上がってきた段階で、子どもたちも「これよくわかりませーん」と言っています。
本当にいるんでしょうか?
年間を見通して、「ゆっくり考え、素早く動く」
学校現場は忙しいです。
それでも、各行事、各学習、去年と同じ通りに「素早く考え」たらうまくいかなかったことがありませんか。
計画段階では、ゆっくり動くことは大切です。
もちろん、1ヶ月もかけて提案しようなんてことは言いません。
ただ、事前に昨年の資料を読んでおいて、本当にこれでいいのか?と一度考えることは重要だと思っています。
頭の片隅に置いて、寝かしておくことで、きっとよいプランが1週間後には出来上がるでしょう。
日々の変化が激しい教育現場ですが、「すぐやらなければならないこと」と「計画的に考えなければならないこと」をうまく使い分けて、仕事をしていく必要があります。
こちらの記事でも詳しく話しています。合わせてご覧ください。
試作を繰り返そう「PIXAR Planning」

映画で有名なPIXAR。
「トイストーリー」、「インサイド・ヘッド」、「カーズ」などなど。
誰でも聞いたことのある作品を制作しているアメリカの会社です。
これだけの大ヒット作を作っているPIXARですが、大ヒット作品を作るにはどんな工夫をしているのでしょうか?
実は最初から、トイ・ストーリーのような大ヒット作の具体的なアイデアが監督の頭の中にあったわけではありません。
最初は「おもちゃ、動き出す」みたいな「灰色のモヤモヤ」ものが、監督の頭の中に浮かびます。
そうしたら、最初の一歩として、12ページほどのあらすじを書きます。
「主に、なにが起こるか説明する。舞台はどこか?どういう状況なのか?どんな事が起こるのか?」
このあらすじを他の監督や脚本家、アーティスト、経営陣などの他の関係者に渡すようにするそうです。
ここまでに数ヶ月かけることが許されます。
そうしたら、全員がそれを読んで、「批評や質問、懸念をぶつけます。監督はそれらを持ち帰って書き直す」ことが許されるそうです。
このやり取りを何度か踏むと「120ページ」に草稿を膨らませます。
ここでも、何度もやり取りをして、草稿を形にしていきます。
形になったら、脚本全体の絵コンテを切ります。そこで5人から8人のアーティストを組むそうです。
90分の映画なら、2700枚の絵が必要です。
この動画に社員がセリフを吹き込み、簡単な音響を加え、プロトタイプができます。
そして、プロジェクトに関わっていない大勢の社員を集めて、試作映像を上映して、またもや、様々な意見を集めます。
意見を集めたあと、新しい絵コンテを作り、試作映画バージョン2を机います。
もちろん、バージョン2も、社員の前で上映して意見を集めて、修正をします。
公開される映像の絵コンテになるのはバージョン9ぐらいまで繰り返し作り直すそうです。
つまり、公開版の絵コンテができるのに、実に2万枚の絵を描くことになるのです。
すごい労力をかけてると思いますよね。
けれど、実際に声優や、他の制作協力者を何百人も投入して、完成版をやり直すよりも、よっぽどコストは少なくなります。
「バカバカしいアイデアを試せる自由が必要で、アイデアたいていの場合はうまくいかない」とピクサーの社員は言います。
そこを、「試して、いいものになるまで仕上げていく。そこまで試していくのが大切」というのです。
学校現場で 「研究授業の指導案」、「学校行事」
「研究授業の指導案」なんとなく書いて、他の先生から意見をもらって、やってみるだけ。
それでうまくいかなかったー。そんな苦い経験をしたことのある先生も多いハズ。
そこで、PIXARのように、「小さな試し」をしてみませんか?
指導案の上で進めるのと、実際の授業を進めてみるのでは大きく違います。
例えば、一人、先生を子ども役にしてやってみる「模擬授業」。
道徳のような授業だったら、隣のクラスで「試し」の授業をさせてもらう。
今までの授業で似た授業はないか指導案を探して、試してみる。
こんなふうに、様々な試しができるはずです。
そこで、色んな意見をもらう。
意見をもらうのですが、自分のピンと来たものだけを加えてみる。
そして、もう1回自分でシュミレーションをしてみる。
1回試すだけで、授業の見え方が大きく変わることを実感すると思います。
学校行事でも一緒です。
先生はいろんな学校で、運動会や学校祭などを計画、実施します。
他の学校に移ってきても、基本は同じはずです。
そのような今までの経験を元に、この学校でもうまくいくか、変えるべきところはないかと考えていくことでより良い実践が可能になります。
PIXARほど「ゆっくり考える」事はできませんが、「小さな試し」を何度も経験することで、いいものを作り出せることが可能になります。
よく聞くのがPDCAサイクルです。そこについても、考えたことがありました。合わせてご覧ください。
最後に

ここまで書いてきましたが、いいものを作りには、「時間をかけ、何度も試す」ことが大切ということを当たり前ですが何度も書いてきました。
ただ、現場では、なかなか待ったがかけれず、日々怒涛のように過ぎていきます。
ただ、強みとしては、夏休みや冬休みなど、長期休暇が学校にはあります。
もちろん、色々仕事はたくさんありますが、「ゆっくり考える」時間は持てるはずです。
そこで、一度自分の仕事を見通してみるのはいかがでしょうか?
以下の記事でも、「眼の前の仕事」ではなく、「人間関係や準備計画、勉強」など重要だけれど、急ぎではない仕事をすることが大切ということを提案しています。
この考えは今回の話に通ずるものです。
少し話はズレますが、いつも聞いているポッドキャスト「誰もやらないビジネスの作り方」の「#21 ニッチな新ビジネスのつくり方。『小さな実験を繰り返し、育てる』」でも同じことを言っていました。
ぜひ、ゆっくり考え、自分を成長させてみましょう。
皆さんはどんな工夫をされていますか?
コメントで教えて下さい。

参考文献・参考HP
参考文献
参考HP









コメント