以前、「嫌われる勇気」を読んでの書評を書きました。

この本がもう1つ、教師として、子どもをみていくときに心に残しておきたい言葉が出てきました。
手のかかる子ども、問題のある子ども。
そう聞かれると、皆さんの頭の中にも浮かぶ人が出てくるのではないでしょうか?
なぜ、問題行動を起こすのでしょうか?
そして、その問題行動に悩み、心を痛める先生もいないでしょうか?
ここに関して、「嫌われる勇気」を読んで考えたことがあります。
今日は、その一節を紹介しながら記事にしたいと思います。
「特別な存在」でありたい人が進む2つの道

アドラー心理学では、人間は、「優越性の追求」という欲求を持っていると言われます。
優越性の追求とは、「向上したいと願うこと」や、「理想の状態を追求すること」を指しています。
今のビジネスの言葉で言うと、キャリアアップとか、キャリアマネジメント。
教育の現場では、自己実現とでもいうものだと思います。
これらの気持ちを持つことは何ら悪いことではありません。
むしろ、頑張っているじゃないかと称賛されることだと思います。
さて、教育の現場では、子どもが悪い方向に「優越性の追求」には知ってしまうことあります。
多くの子どもたちは、最初の段階で「特別によくあろう」とします。具体的には親のいい付けを守って、社会性を持った振る舞いをし、勉強やスポーツ、習い事に精を出す。そうやって親から認めてもらおうとする。
しかし、特別によくあることがかなわなかった場合ーたとえば勉強やスポーツがうまくいかなかった場合ー今度は一転して「特別に悪くあろう」とします。
(中略)
特別によくあろうとすることも、あるいは特別に悪くあろうとすることも、目的は同じです。他者の注目を集め、「普通」の状態から脱し、「特別な存在」になること。それだけを目的としてるのです。
(中略)
本来、勉強であれスポーツであれ、なにかしらの結果を残すためには、一定の努力が必要になります。ところが「特別に悪くあろう」とする子ども、すなわち問題行動に走る子どもたちは、そうした健全な努力を回避したまま、他者の注目を集めようとします。アドラー心理学では、これを「安直な優越性の追求」と呼びます。
-岸見一郎.「嫌われる勇気」(P258)
これを読んだときに、今まで担任してきた子の顔が色々浮かびました。
例えば、頭が切れて、カリスマ性もある。けれども、友だちを引き連れて悪さばかりしている生徒。何度も話をして、指導をしましたが、なかなか考えを改めない中学の生徒。
家庭では、とてもいい子と親から聞くが、学校に来ると授業妨害をする生徒。
この子達はなんでこんな行動をするのでしょうか?
ここで大事になるのは、「相手(先生や、クラスメート、果ては親)を困らせることで、注目を集めようとしている」のです。
相手を困らせることで、相手の特別であろうとしているのです。
悪さをすれば、叱られる、かまってもらえる、誰か先生1人が特別につく。
そうすることで、自分は特別だと思うのです。
1人先生がつくということは、思春期の中学生、嫌と思うのが普通ではないでしょうか?
どんな形でもいいので、「特別な存在でありたい」とする心の行動の表れなのです。
普通であることの勇気

実際に、そのような子は、親が忙しくて構ってもらえなかったり、関心が薄いことが多かったです。
学校では、親の愛情不足ではないかとアセスメントをしました。
自分は、親にはなれませんが、その子が少しでも満ち足りるように一緒に遊んだり、かまったりしました。
何年もかけて少しずつですが、問題行動はおさまってきました。
転勤して、最後までその子を見ることが出来ませんでしたが、街中でばったり出会ったときは見違えるほどに落ち着いていました。
誰もが特別な存在にはなれません。
そんな子にはアドラー心理学では「普通であることの勇気」が求められています。
普通であること、平凡であることは本当によくないことなのでしょうか?
なにか劣ったことなのか。実は誰もが普通なのではないか。
そこを突きつめて、子どもと一緒に考える必要がありそうです。
そこで、以前紹介した、「人生での目標」を一緒に考えます。
行動面の目標
- 自立すること
- 社会と調和して暮らせること
この行動を支える心理面の目標
- わたしには能力がある、という意識
- 人々はわたしの仲間である、という意識
これを達成するには、どうすればいいのか。膝を突き合わせて、考える必要が出てきます。
最後に

教育の現場でアドラー心理学を用いることは劇薬ではないかと思うかもしれません。
私もそう思います。
けれど、子どもを見るひとつの見方、見え方として、アドラー心理学的観点から、アプローチすることは有効であると思っています。(生徒のアセスメントについても記事にしています。)
また、「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」という格言を用いて、相手を変える努力はしても、最後は、本人が判断することであり、そこまでの責任は持たないでいいということを説いています。
昨今の教育現場は、さまざまな価値観がクラスのなかで渦巻き、疲弊をしています。
先生の中には、さまざまな手立てをうって、うまくいかず、心を病んでしまったという方もいます。
もしかしたら、ベターな方法が別にあったかもしれません。それを検証することは大事ですが、別問題として捉えましょう。
日々、生徒に真剣に向かっている先生方に敬意を。そして感謝を。
もし困っていることがあったら、この記事のコメント欄をお使いください。

生徒指導について考えていることを色々書いています。合わせてご覧ください。
岸見先生の本を他にも読んでいます。こちらのほうが難しいです。合わせてご覧ください!
参考文献
Audibleに入会すれば、「嫌われる勇気 自己啓発の源流『アドラー』の教え」を安く聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!







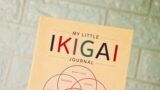


コメント