中学校1年生では、負の数を導入します。そこで、自然数や、整数といった言葉を勉強します。
そして、中3になると、平方根を学習します。今までは、円周率のπしか知らなかったのですが、それ以外の無理数を知ることになるのです。
ここにきてようやく、無理数とか有理数という区別を学び、実数全体を学習を終えることになります。
そうです。「実数」という、身の回りに見える数を全て表現できるようになるのです。
(御存知の通り、高校ではさらに数の世界を広げて、虚数iを勉強していきます。)
ところで、有理数の「有理」。無理数の「無理」って何なんでしょうか?
分数になる理(ことわり)があるから有理数なのでしょうか?
扱いが難しいから「無理!」数なのでしょうか。
今日は数学用語の意味を勉強してみました。
誰が有理数・無理数という言葉を決めたの?

多分ですが、数学者の藤澤利喜太郎や1877年に設立された東京数学会社(現 日本数学会)の訳語会ではないかと言われています。
明治期に明治新政府は国策として和算から洋算への転換を決定しました。
それに伴いドイツをはじめとする西洋の数学が輸入され、訳語を作る必要が出てきたのです。
では、一体なぜ、「有理」数・「無理」数と名付けたのでしょうか?
「有理」・「無理」の意味
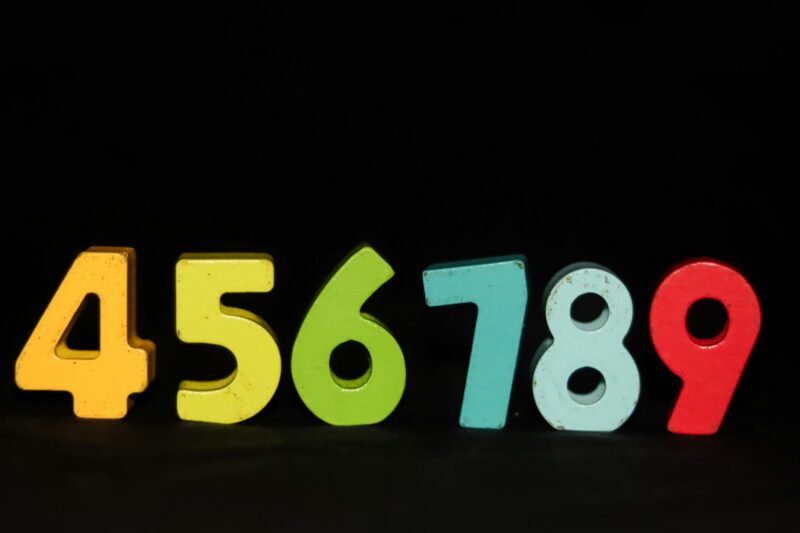
辞典から考えてみる
ゆう‐り〔イウ‐〕【有理】
1 道理のあること。
2 数学で、加・減・乗・除以外の演算を含まないこと。む‐り【無理】
[名・形動](スル)
1 物事の筋道が立たず道理に合わないこと。また、そのさま。「無理を言われても困る」「怒るのも無理はない」「無理な言いがかり」
2 実現するのがむずかしいこと。行いにくいこと。また、そのさま。「無理を承知で、引き受ける」「無理な要求をする」
3 しいて行うこと。押しきってすること。また、そのさま。「もう無理がきかない」「無理に詰め込む」「あまり無理するなよ」ーデジタル大辞泉より
とあります。
「有理」という言葉を見てみましょう。
①の「道理のあること」の道理とは???道理のある数とは?と思ってしまいます。
「道理」・・・物事の正しいすじみち。また、人として行うべき正しい道。ことわり。
数に道理もクソもないので、次の意味を見てみましょう。
②でも、加減乗除以外の演算を含まないといっていますが、端的に有理数を表しているとは思えません(割り算は含んでいますが)。
「無理」についても同様です。
国語の辞典に載っている意味+数という組み立てでは有理数・無理数の意味はピンときませんね。
英語から攻めてみる
有理数のもともとの英語は「rational number」です。
rational・・・理性のある、道理をわきまえた、正気の、気の確かな、合理的な、わけのわかった、推理の、推論の、純理論の、理性主義の
-weblio英和辞典より
rationalはもともと合理的という意味で、ratinal thinkingは合理的思考と訳されます。
他の意味の共通点もみてみると、合理的、推理、理性主義のように「理」という言葉が入っています。
つまりrationalは、「◯◯理的な」という意味を持っている。
理なる数→有理数と当てたのかなと考えられます。
でも、理なる数の「理」とはなんでしょうか?
もう少し突っ込んでみる必要がありそうです。
rationalの名詞形ratioという言葉は「比」という意味です。
ratio・・・比、比率、割合、比例
-weblio英和辞典
つまり、ratioには理という言葉はなく、形容詞に活用されたときに形容詞rationalは「合理的」になりました。
ratioまで遡れば、有理数は「比がある数」→「比で表せる数」→「分数で表せる数」となります。
ただ、日本語的には、通じにくい言葉になってしまいました。
ちなみに無理数は、irrational numberです。
ir-の接頭辞は、否定の意味がありますので「比にできない数」になります。
有理数に対して、無理数にした意味がこれではっきりしますね。
最後に
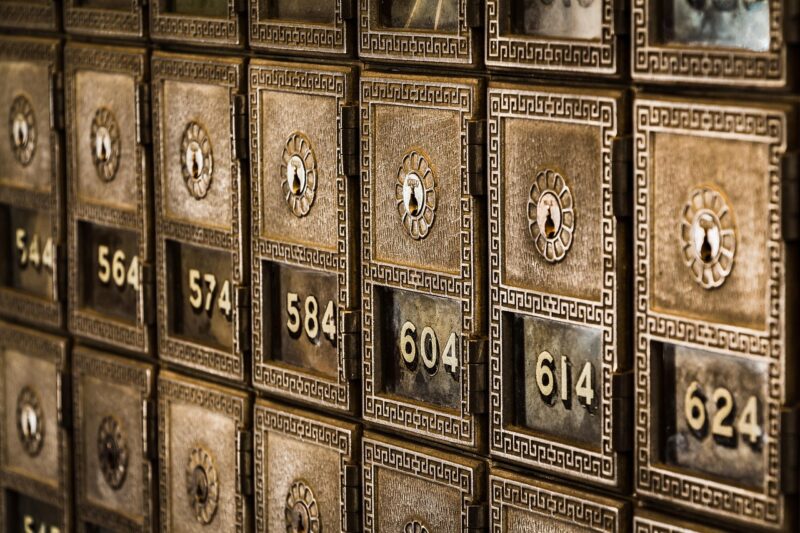
今回のように、数学用語の意味を遡って調べると、面白い発見があります。
自然数natural numberのように直訳されている語句ばかりではありません。
今回は省きましたが、ラテン語まで遡るとより具体的に意味が把握できる場合もあります。
学習で大事なのは、学習内容を思い出すフックをたくさん子どもに作ることだと思っています。
有理数の由来を話すと、今まで数学に興味を持っていなかった生徒にも、何かしら残る事が出てくるかもしれません。
デカルトなどの話もこのブログに残していますが、そうやって、子どもが興味を広げるきっかけをたくさん授業の中に盛り込んで行きたいですね。
皆さんは授業で意識していることありますか?是非コメントで教えて下さい。

数学の歴史小話は、こちらにも話題にしています。
参考HP




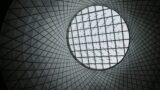


コメント