皆さんの学校は、まだ通知表に所見を書いていますか?
最近は、所見も年に一度しか書かないとか、そもそも所見欄がなくなったということも聞きます。
もちろん、作業量が少なく、省エネ化するのはいいことだと思うのです。
ただ、教師として、子どもたちの良いところを見つけ、そこを伸ばしていくということは外せないマインドです。
実は、私、この所見を書くのが苦手です。
どうにも、その子その子のきらりと光るところを抜き出してあげられなくて、いつも所見を書くときは、苦しんでいました。
結局は、子供のいいところを書けばいいのだけれど、それがうまく見つけられないのが悩みでした。
子供を見る目を鍛えるために、所見の書き方といった教育書も読みましたが、ピンと来ませんでした。
最近、八木仁平さんの「世界一やさしい「才能」の見つけ方 一生ものの自信が手に入る自己理解メソッド」を読みました。
この本は、読者の「才能」の見つけかたに焦点を当てて書かれていますが、これってそのまま、子供の「才能の見つけかた」、もう少し言い方を変えれば「良いところの見つけかた」につながるのでは?と思いました。
今回は、「子どものよいところの見つけかた」をテーマに一緒に考えていきましょう。
子どもの良いところはどんなとこ?

まずは、子どもの良いところとはどんなところかを考えてみましょう。
良いところを見つけるのは自分は苦手としていました。
それは、子どもも、「できて当たり前」と思っていたからです。
自分の中ので「できて当たり前」の基準が高かったので、子どもの良いところをうまく切り取れずに悩んでいました。
また、できて当たり前の基準が高い反面、子どものできないことに対して、すごく悶々としていました。
でもよく考えたら、子どもの良いところって、他人(友達や教師)と比べる必要は一切なかったのです。
子どもがついやってしまっていること、夢中になってやっていること。
それを見つければ、自ずと子どもの良いところが見えてくるのです。
そして、ついやってしまうこと、夢中になってやっていることは短所でも言えることがあります。(例えば、授業のチャイムが鳴っても外遊びから戻ってこない)
授業に間に合わないと、つい短所に目がいきがちですが、そこには、授業に間に合わないほど夢中になっている何かがあるはずです。
短所からも良いところを見つけることができるようになりました。
さて、どんなところに注目すれば良いのでしょうか?
一緒にみていってみましょう。
子どもの良いところを見つける4つの質問 短所の裏返しを考えよう

- 親や先生によく注意されていることは?
- やっちゃダメと禁止されている辛いことはあるか?
- 子どもの短所を「だからこそ」で言い換えるとどうなりますか?
- 他の人は嫌がるのに、子どもが楽しい(率先してやっている)と思えることは?
– 「世界一やさしい『才能』の見つけ方 一生ものの自信が手に入る自己理解メソッド」.P117を改変
子どもの良いところを見つけるのには、この4つの質問を順番に考えると良いです。
なんでこの質問が有効か疑問に思う方もいるでしょう。
一つずつ説明をしていきます。
1 親や先生によく注意されていることは?
親や先生に注意されていることは、それだけその子の目立っている部分です。
例えば、ドラえもんのジャイアンで考えてみましょう。
ジャイアンは、よく「家の手伝いをしなさい!」とジャイアンのお母さんに耳を引っ張られて連れてかれてしまっています。
また、のび太たちを野球に巻き込んでいます。’のび太くんはよく泣いていますが。)
裏を返せば、ジャイアンは「家の手伝いをよくやっている」ということです。
「友達を巻き込めるリーダーシップを持っている」ということができます。
悪いふうに取るのではなく、良いふうに取っていくことで、子どもの良いところがたくさん見つかります。(もちろん、直すべきところは伝えてですが・・・。)
もちろん、声掛けの仕方も叱るのではなく、良いところを伸ばす声かけに先生も変わっていくはずです。
2 やっちゃダメと禁止されて辛いことは?
禁止されると辛いことを考えると、良いところが見えてきます。
「努力」というのは人間にとってしんどいことです。
逆に、ついやってしまうことが、他人に貢献できると、それは良いところに変わります。
その子のついやってしまう行動は何かを見つけてみましょう。
大きな声でよく話す子なら、挨拶も大きな声でできているかもしれません。
合唱が良い声が出てるかもしれません。
お節介な子だったら、友達を気遣う場面がたくさんあるかもしれません。
そうやって、その子その子が「ついやってしまうこと」から広げて、良いところを見つけると見つけやすくなります。
3 子どもの「短所」をだからこそと言い換えると?
人間は、長所よりも、短所に目が行きがちです。
先生も同様、どうしても子どもの短所に目が行ってしまいます。
それはどうしてもしょうがないことなのです。
その見方を利用して、魔法の言葉を使って、「短所」を一瞬で「長所」に変えてみましょう。
魔法の言葉は「だからこそ」です。
例えば「Aさんは人見知りだから、授業で意見が言えない」の「だから」を「だからこそ」に変えてみます。
・Aさんは人見知りだから、授業で意見が言えない
→Aさんは人見知りだからこそ、友達に優しくできる
・Bさんは、突発的なトラブル対応が苦手
→Bさんは、突発的なトラブル対応が苦手、だからこそ、準備をしっかりする。
こんん感じです。短所があるからこそ輝ける。そんな見方があるのです。
4 他の人は嫌がるのに、自分には楽しいと思えることは?
あまりに楽しくて、遊びだと思えるくらいのことが子どもの姿で見つかれば、素晴らしいことです。
例えば、計算ドリルをバリバリ取り組む。
友達の手伝いを率先して行う。
学級の代表を率先して行う。
周りとしては、ウッと思うことを難なくやれる子どもの姿を見つけられたら、それはもう、その子の一番素晴らしい姿です。
そうやって、子どもの良いところを見つけていきましょう。
「良いところ」を見つける学級活動

褒め言葉のシャワー・良いところ見つけ
ここからは、「良いところ」を見つける学級活動を紹介していきます。
菊池省三先生が、「褒め言葉のシャワー」という実践をなさっています。
この言葉を聞いたことのある先生は多いと思いますし、褒め言葉のシャワーと言わずとも、「友達の良いところ見つけ」などの実践をされた先生も多いと思います。
褒め言葉のシャワーとはなにか、メリットデメリットをみていきましょう。
「褒め言葉のシャワー」とは?
子ども同士が互いを認め合う活動
「褒め言葉のシャワー」は、子どもたちが互いに褒め言葉を伝え合う教育実践です。まるで褒め言葉をシャワーのように浴びせるという意味から、この名前がつけられました。
特別な準備は必要なく、どの学年でも応用できるのが特徴です。主に学級活動や道徳の時間などで取り入れられています。
実践の流れ
実施の流れは以下のとおりです。
- クラス全員で円になって座る
- 一人ずつ順番に、中心になる人を決める
- 周囲の子どもたちが、その子の「良いところ」や「素敵な点」を言葉にして伝える
- 褒められた子は、ただその言葉を受け取る(謙遜や否定をしない)
- 順番に中心の子を交代して、全員が体験するまで繰り返す
たとえば、「○○さんは、給食の準備をいつも手伝ってくれてすごいと思います」や「○○くんは、いつも笑顔で挨拶してくれて気持ちがいいです」といった具体的な言葉が飛び交います。
この実践で育つ力
自己肯定感の向上
自分の良さに気づくきっかけになるのが「褒め言葉のシャワー」です。他者から認められることで、「自分には価値がある」と実感できるようになります。
他者理解と信頼関係の構築
他の子の良さに目を向け、言葉にする経験を通して、人との関係性が深まります。クラスの人間関係も自然とよくなっていきます。
表現力・共感力の育成
誰かの良いところを見つけ、それを言葉にして伝える力が育ちます。また、相手の立場になって考える共感力も養われます。
実施時の注意点
無理に褒めさせない
子どもに「無理やり褒めなさい」と強制すると、表面的な言葉になりがちです。自然な気づきと言葉を大切にしましょう。
偏りに配慮する
いつも同じ子だけが褒められたり、ある子だけが褒めにくいという状況が続くと、かえって逆効果になることがあります。全員が平等に参加できるように工夫が必要です。
謙遜は禁止と伝える
褒められたときに「そんなことないよ」と否定してしまうと、せっかくの好意が伝わらなくなってしまいます。受け取る側には、素直に「ありがとう」と言うように伝えます。
自分の経験から
実施上の注意点で書きましたが、子どもの誰かが絶対言うのが「〇〇さんの良いところなんて見つけられないよ」という言葉です。
大抵、当たり障りのない言葉を言ったり、他の子の言ったことを真似をして済ませてしまいます。
- その子のことを関わりがないので、本当に知らない
- 苦手としている友達である
- 良いところの見つけかたがわからない
など、子どもが良いところを見つけられない理由は考えられます。
そんな子どもに、「よく考えてみなさい」と言っても逆効果です。
そのときこそ、今回記事にした「才能の見つけかた」の方法を子どもたちに教えます。
そうすれば、実は友達の嫌と思っている部分がよく見えたり、そもそも、良いところの見つけかたがわかったりという、子ども同士の見方に変化が起こります。
子ども同士の見方に変化が起これば、子どもの関係性の変化にもつながります。
褒め言葉のシャワーの鉄則は、「みんながいいところを見つける」ことです。
一人でも良いところが見つけられないなら、この活動は崩壊してしまいます。
子どもが本気になって良いところを見つけるから、この活動は生きてくるのです。
もし、「良いところが見つけられない」と言う子どもがいたら、「イラッとするところでもいいんだよ。それを良いふうに見方を変えてみよう。」と伝えてみましょう。
きっと、見方に変化が起こります。
友達と一緒に良いところを見つける「私の四面鏡」
他にも、「構成的グループエンカウンター」の手法を使って、「私の四面鏡」という活動があります。(詳しくはリンクを参照)
この活動は、ワークシートを使って行います。
ワークシートには、「優しい」、「意志が強い」といった性格の一面がたくさん書かれています。
まずは、自分で当てはまる項目に○を打っていきます。
そして、友達に、友達から見た自分についても〇を打ってもらいます。
自分の〇を打ったところと、友達の○を打ったところを比べて、自分の姿を知るという活動です。
これも、自分の気づかなかった一面が現れることがあります。
自分では気づいていなくて、友達が○を打ってくれた部分は、先に紹介した原則から考えれば「良いところ」なのです。
教師が気づかなくても、この活動を通して、子どもの良いところも見えてきます。
その切り口で、子どもの様子を追っていけば、たくさん良いところが見つかるはずです。
検査を使って

最後に、診断検査、性格検査を使って、いいところのヒントを見つけることもできます。
ただ、あくまで、検査は、傾向を把握するだけです。
本人の姿と乖離することもありますので、あくまで参考にして、子どもの姿を追ってみましょう。
PASカード(図書文化社)
PASカードは、将来の職業を考えるときに使う性格診断です。
先ほど書いた進路適性検査は、こちらを使っています。
自分の性格の長所から、進路や職業の向いているコースが診断されます。
ここに出てくる、性格を参考に、生徒の性格を追うとヒントが得られるかもしれません。
他にも、ストレングスファインダーやMBTIのようなビジネスに使うような診断もあります。
子どもの気持ちになって、回答をしてみると、その子のいいところにヒントが見つかることもあります。(また、ストレングスファインダーなどはレビューしますね)
MBTI診断
MBTI診断とは、人の性格傾向を16タイプに分類する性格診断で、正式名称は「Myers-Briggs Type Indicator(マイヤーズ=ブリッグス・タイプ指標)」といいます。
心理学者ユングのタイプ論をもとにブリッグス親子が発展させたもので、世界中で自己理解や他者理解のツールとして広く使われています。
MBTIでは「外向(E)か内向(I)か」「感覚(S)か直観(N)か」「思考(T)か感情(F)か」「判断(J)か知覚(P)か」という4つの指標を用いて、人がどのように世界を認識し、判断し、行動しやすいかを分類します。
これらの組み合わせによって、ENTPやISFJといった16タイプの性格が導かれます。MBTI診断は、自分の考え方の傾向や行動パターンを理解する助けになるだけでなく、職場や学校などでのコミュニケーション改善にも役立つとされています。
無料でできて、情報も豊富にあるMBTI診断も面白いです。
実際にやってみた結果を、こちらの記事にレビューしました。
最後に

今回は「子どもの良いところを見つける」というテーマで書きました。
良いところを見つけるポイントは
- 親や先生によく注意されていることは?
- やっちゃダメと禁止されている辛いことはあるか?
- 子どもの短所を「だからこそ」で言い換えるとどうなりますか?
- 他の人は嫌がるのに、子どもが楽しい(率先してやっている)と思えることは?
の4つでした。
また、教師だけが見つけるのではなく、子ども同士で見つける手段として、「褒め言葉のシャワー」や「私の四面鏡」という活動を紹介しました。
子ども同士の「良いところを見つける」見方も豊かにすることで、所見はもちろん、学級経営にも繋がります。
皆さんも、実践してはいかがでしょうか?
そうそう、私の好きなPodcast「二番経営」という番組でも、才能をテーマに一話、話が展開されていました。
ここにでてくるタカチンこと「佐野貴」さんも、才能について研究をしています。
工事中
こんな本も出しているようなので、こっちも読んでみたいなと思います。
皆さんの所見の思い出や、子どもの見方など、ぜひコメントで教えてください!

所見の文章を上手に書きたいと思ったら、こちらの記事をご覧ください!
こちらでは、googleフォームを使って、複数担任で所見をどんどんためていこうという提案をしています。
個人でも、十分活用できるので、ぜひ実践してみてください!特に、タブレットを持ち歩くようになっている学校なら、便利ですよ!
グループエンカウンターについて、気になる方は、こちらも実践を載せています。合わせてご覧ください。
参考文献・参考HP
参考文献
参考HP
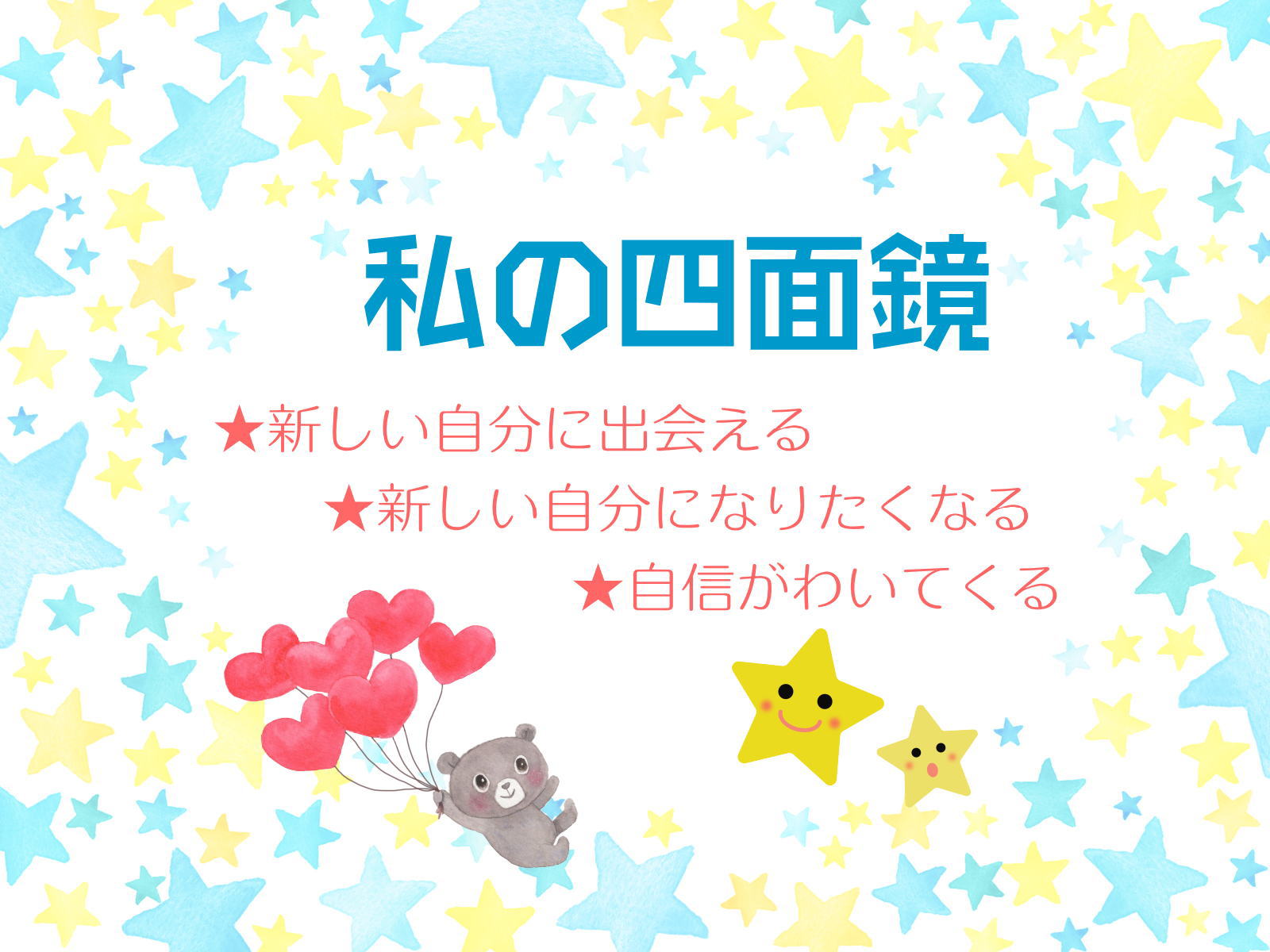











コメント