以前、教育論文の書き方として、「主題・仮説・手立ての設定の仕方」を書きました。
手立てを講じても、子どもの変容をしっかり見取り、記述ができなければいけません。
今回は「授業の実際」の部分で書く、「生徒の変容の見取り方」、「研究のまとめと今後の課題」の書き方を一緒に考えていきましょう。
抽出児童生徒の設定の仕方
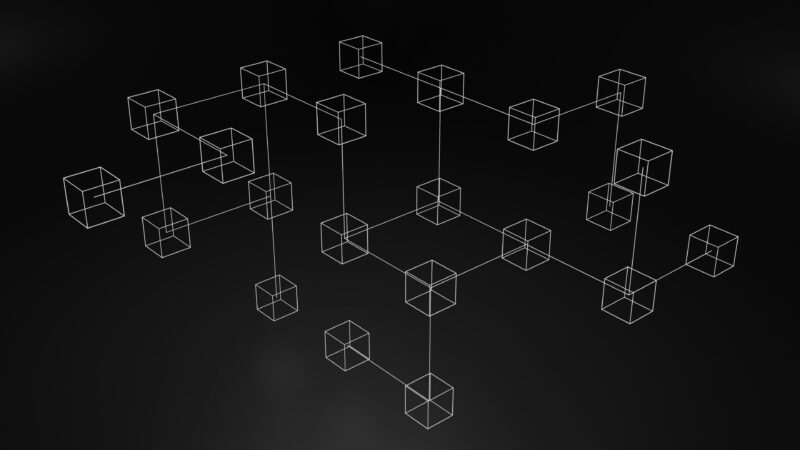
さて、クラス全体の子どもの様子をすべて追うのは難しいです。
そこで、中心的に変容を追う子ども「抽出児童生徒」を設定します。
個の変容を覆うことで、手立ての有効性を検証していくのです。
抽出児童生徒を選ぶ観点
- 学級の実態を浮き彫りにしている子ども
- 「この子をなんとかしたい」という教師の強い願いをかける子ども
人数は、1人~3人程度にします。
また、個の変容を追う中でクラスとの関わりや、クラス全体の変容も出てきます。
抽出児童生徒の変容とかかわらせながら、クラス全体の変容を捉えていきましょう。
授業の実際で生徒の姿を記述するときに用いる「資料の蓄積」

資料の蓄積のために
論文の授業の実際を書くところで、生徒の変容が起きている場面を取り上げ、詳述していきます。
その際に、気をつけなければならないのが、資料の客観性です。
資料は推論の根拠になるものです。
独断や思い込みに陥らないように、信頼性の高い資料を多く収集するようにしましょう。
具体的には以下のものが資料となります。
- 調査・作品・生活等の記録
アンケート・学力テスト・作文・日記・絵・班ノート・学習記録 など - 研究経過の記録
授業中で作った作品・授業記録・活動記録 など - 検証授業の記録
児童生徒の発言・動作・抽出児童生徒の様子・教師の発問、板書・指名・資料の提示 など
資料を使って仮説の有効性(目標の達成度)を検証しよう
研究の最も大切な部分であり、資料を分析して「手立て」の有効性を見ていきます。
- 講じた「手立て」に応じた「子どもの変容」が認められたか。
(手だて以外の要因はなかったか) - 推定や判断に資料(データ・作品等)の裏付けはあるか。
(データの捏造、独断や強引な判断をしていないか) - 実際の子どもの反応は予想と違うことも多い。今後の課題として後日の実践に残すか、修正仮説によって第2次実践によって検証する。
- 失敗の記録も情報的価値をもつ。
「ねらい」に応じた検証方法を採用しよう
結局、変容が見られないと意味がありません。
児童生徒の変容を何で見るか、多様な視点から考え、信頼度のある検証方法を選びます。
検証方法として、様々な方法があります。
- 観察法
- 質問紙法
- 面接法
- 記述法
- テスト法
- 動作、表情、発言、自己評価、相互評価、生活記録(日記)、振り返り、ノート、作文、レポート、作品、演技、発表など
集めた資料を元に検証・考察をする
学級(学校)全体とこの変容をとらえ、両面から検証し、成果を見極めます。
授業の実際の部分が書き上がったら、以下の視点で見直してみましょう。
- 都合の良いデータを利用しすぎてはいないか
- 一面的な視点による少ないデータで成果を見ていないか(生徒の表情だけとか)
- 一クラス、一実践(1時間)だけの成功を一般化していないか。
テストの点数の増加のように、数値データのみで、検証することは不可能です。
指導に反応する子どもの生きた姿を授業分析等で見極め、指導の適否を評価すると説得力が増します。
反対に主観的なデータのみの検証も説得力にかけます。客観的なデータと子どもの生きた姿を記述していくことで、有効性を明らかにしていきます。
記述のときのポイント
事実を述べている部分と、解釈や考えを述べている部分を区別して記述します。
例えば以下のようなフォーマットで記述をしていきます。
授業者は、「このように分析し、」
その結果、「このような事実が現れ、」
その事実に対する「自分の見解、意見はこうです」
このように、明確に述べ、自説を確立するのです。
例:〇〇のような手立てを講じたことで、話し合いの中で「Aさんの意見でわかったよ。」【資料1の下線部】と話していた。さらに、生徒の授業後の振り返りには「解の公式は、2次方程式のそれぞれの係数a,b,cを代入すればい良いことがわかった」【資料2】と記述があった。これより、手立てを講じたことで、抽出生徒は対話的に学んでいると分析できる。
「研究のまとめと今後の課題」の書き方

本論で展開した事柄を完結にまとめ、締めくくります。
論文の構成によっては、本論で結論まで述べてしまうこともあり、その場合は単なる結びとして、展開の要約や今後の課題を述べておくようにします。
そしてまとめでは、この研究を通しての自分に主張を簡潔にまとめます。
今後お課題を、研究の仮説、研究の内容と方法の両面から明らかにします。
何が明らかになり、何が問題として残ったのかを課題を明確にしていきます。
なお、今後の課題の方向性を必ず示したいですね。
最後に
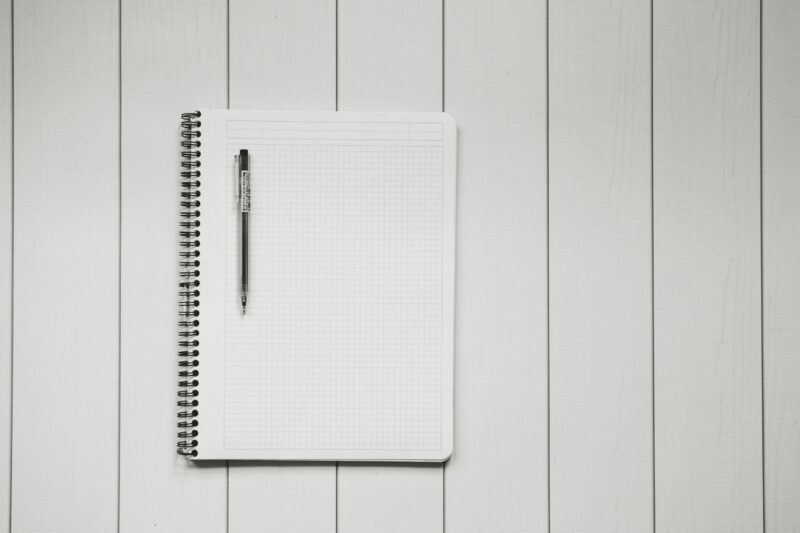
さて、ここまでいくつも教育実践論文の書き方を記事にしてきました。
児童生徒の変容が分析できるということは、普段の授業でも活きてきます。
教育論文というと、どうしてもお堅いイメージですが、「児童生徒目指す姿に向けて、教師がどんな手立てを講じて、その結果、どんな児童生徒が成長をしたか」を記述していくだけなのです。
大事なのは、「どんな手立てを講じたか」です。
様々なアプローチがあります。
そこを自分で調べて、解釈して、眼の前の児童生徒に合う方法で落とし込んでいく。
その営みが大切です。
ぜひ皆さんも教育論文を書いてみませんか?
みなさんの経験、授業への思いを募集しています。是非コメントに書き込みをお願いします!

こちらでは、論文を書くうえでのポイントを端的にまとめました。合わせてご覧ください。
以前書いた教育論文を一部公開しています。参考になれば幸いです。
指導案の書き方はこちらでまとめています。合わせてご覧ください。









コメント