今回は、人を苦しめる「評価」を無視しよう。という話をします。
「誰も知らないビジネスの進め方」を聞いて、思ったことを書きたいと思います。
今回のエピソードはビジネスから離れて、パーソナリティの櫻堂さんの中学生時代の話です。
ビジネスでも、学校でも、家庭でも、「評価」されて生きています。
この上司はだめだ。あの友達はよく勉強できる。うちの子はどうしようもない。
こんな評価を受けて、人間は一喜一憂してしまいます。
ただ、評価ばかりを気にして生きていくと、つらくなりますよね。
「周りの人からの評価」について考えてみましょう。
「評価」ほど、人間が一喜一憂してふりまわされるものはない
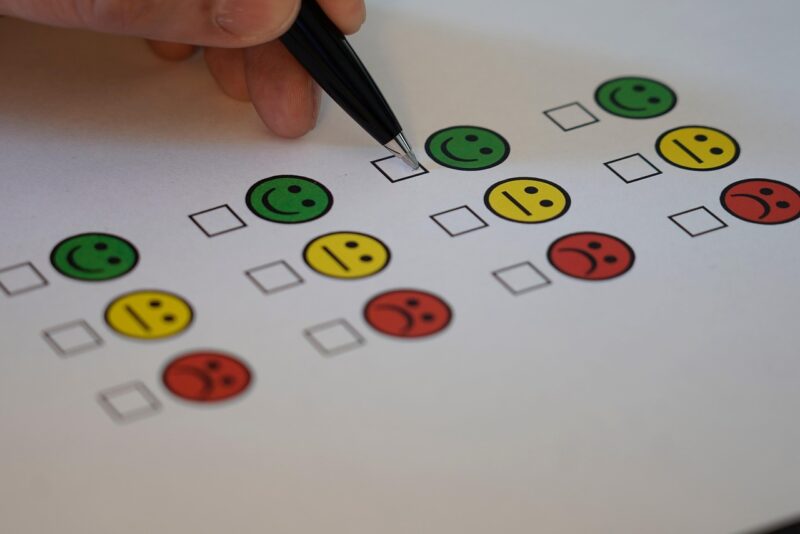
周りからの評価。
これほど自分を一喜一憂させるものはありません。
自分を褒めてもらえたり、仕事を評価してもらえると嬉しいです。
反面、悪口を言われたり、仕事や提案を評価してもらえないと悲しくなります。
子どもが学期末にもらう成績表。テストの順位表。
子どもたちはそれを自分一人で見るだけでなく、友達と見比べたりして、喜んだり、落ち込んだりしています。
教師が仕事をするうえでも評価で苦しんでいることを聞きます(評価が悪くても首を切られることはないのに!)。
よくあるのが部活動。
「部活を指導している先生は偉い」
「夜遅くまで学校に残って仕事をしている人が偉い。」
こんな評価軸で評価され、苦しんでいるという先生をよく聞きます。
ただ、部活動は2018年の文科省が学校の業務だが、担任が担う必要がない業務と整理しました。
また、働き方改革を全面に出し、仕事を整理して、先生たちが早く帰られるようにしましょう様々な自治体と進めているところです。
それでも、長く働いている先生が偉いといったな価値観で評価する人がまだまだいるのが学校現場です。
もちろん手伝いたいんだけれど、子育てがあったり、体調を崩していたりとして、みんながみんな、上記のような評価基準で動けるというわけではありません。
そんな中、周りと合わせないとと思うとしんどいです。
どういった心構えでいればいいのでしょうか?
「評価」を気にしないこと 自分が打ち込めることを見つけること
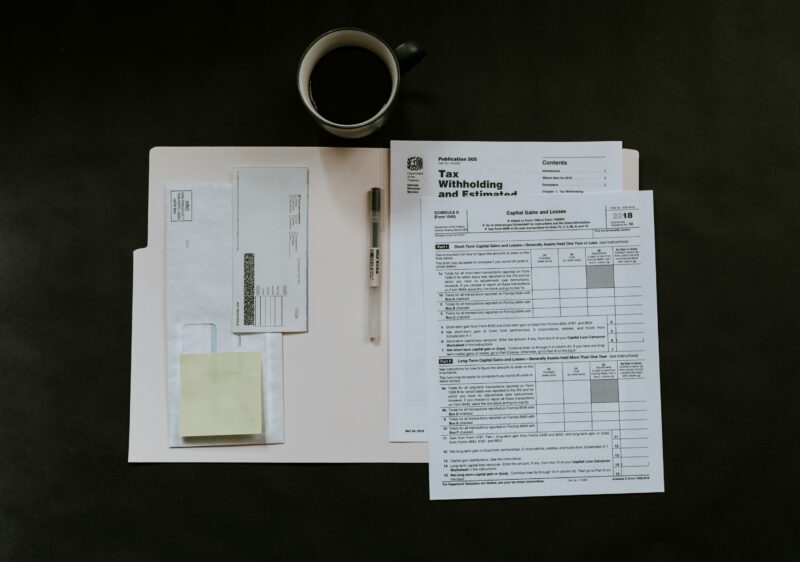
人の評価や価値観は変えられません。
まずは、自分が他人の評価から違った軸で自分を見られるようにすることが大事だと思います。
私の話ですが、自分は学会に所属し、論文を書いています。
でも、周りの先生で話題にすると、「難しいから読めない(笑)」と引っかからないことがほとんどです。
個人的には、教育の研究をしているのだから、教師の本分にのっとったことをやっていると思うのですが。。。
そこは評価されないんですよね。
ただ、そこは「まぁいっか」と思っています。
自分が続けていて研究していて楽しいし、もし強制になったらつらいだろうと思うからです。
もちろん、評価してくれる校長先生もいます。(その校長先生とは共同で研究することもありました)
大事なのは、自分のしたいことを楽しく続けること、そして、評価を気にしないことです。
パーソナリティの櫻堂さんもこんな事を言っていました
成績って結局組織が作った一つの評価基準の中の評価点でしかない。
世界はそれで規定されるわけではない。
・・・(中略)
どうしても世の中のルールとか、会社の中でルールでやっていけなくて、だめだと思う時がある。
全然関係ない。
できるできないは、たしかにその会社ではあるけど、土俵を変えたらそうじゃなくなる。
そこに一喜一憂しない。
自分の好きなことを進めるのが大事
ー19分頃 櫻堂さんの言葉より
学校で苦しいなら、まずは別の学校に異動をしてみたり、他の校種に異動をしてみるといいかもしれません。
どうしても苦しいなら、民間の仕事を探すというのも一つです。
いまの勤務している学校とは異なる評価軸で動いていることに気づくはずです
最後に

評価は、本当に人を苦しめます。
そして、その評価を気にしないというのはとても難しいことです。
私の周りの先生で、とてもできる先生がいます。
その先生は、いつ管理職になってもおかしくないのに、全く管理職に上がらず、定年を迎えました。
ある時、そのへんの話を聞いたところ、こんな話をしてくれました。
「2回、出世コースの誘いがあった。一個は、県の附属学校への異動。もう一つは、県の教育医委員会への出向。どちらも断ってしまった。そして、家を立てるために別の自治体へ異動した。そしたら、そのままになっている。
今思えば、出世コースの誘いのときに、のればよかったのかなぁ。」
そんなボヤキを聞きました。
やっぱり評価は人を苦しめるのです。
また、ある別の先生は、自治体の指導主事などを歴任、管理職になりました。その中でも研究を続け、国立大学の教授として着任された先生もいます。
現場の校長まで勤め上げて、国立大学の教授として着任する例は殆ど知りません(私立は聞きますが)。
これは、自分のやりたいことを続けた結果であると思います。
教授になった先生に、「教授なろうと研究続けたんですか?」と聞いたら、
「いや、好きなことを続けてたら、ここまでこれた。研究を評価されたら、それに伴って、学校でも研究関係の仕事もたくさんふられたけれどね。(教授になれたことは)ラッキーだったね。もっと研究できるよ。」
とおっしゃっていました。
研究に対して、とにかく周りの評価を気にせず打ち込んだからこそ、仕事でも生きた好例だと思います。
いまも生き生きと大学で研究をされています。
もう一つ例を上げましょう。
同僚の音楽の先生も、ニューヨークまでコンサートに招かれて弾いてくる力を持っている先生とも働いています。
夏休みになると、海外の師事している先生のところにレッスンを受けに行くのです。
周りの先生も「がんばっておいで!」と応援をしています。
大事なのは、誰に何を言われようと、自分の好きなことをも見つけること、そして打ち込むこと。
そうすれば、きっと評価をしてくれる人が現れ、道がひらけます。
そんなことを考えさせられるエピソードでした。

「誰もやらないビジネスの始め方」を扱った他の記事はこちら!
参考HP

https://www.mext.go.jp/content/20231010-mxt_soseisk02-000030032_6.pdf







コメント