自分は、授業をするのが大好きです。子どもたちのできた、わかったという声を聞けるととても嬉しいからです。
ただ、生徒指導・学級経営というのは実は好きになれませんでした。
授業と違って、「計算をできるようになる」といった具体的な目標があるわけではありません。
担任をしていく上で、「生徒の人格を高める。」「社会人としてふさわしい行動や考え方をできるようにする」のが目標になってくると思うのですが、授業の目標と比べると、だいぶふわっとしています。
学級経営ってこれでいいのかなと今でも悩んできました。
学級崩壊までは至りませんでしたが、うまく学級がいかなった年もたくさんありました。
できれば、授業だけやっていけたら先生っていいのになーなんて思ったこともあります。
最近「担任学入門」という本を手に取りました。
そこに書いてあったのは、「授業者として必要なスキル」と、「担任として必要なスキル」は違うものだということです。
二つの全く違う分野のスキルを一緒にして仕事をするから、教師の仕事は複雑で難しいとわかって、心が楽になりました。
もちろん先生として仕事を続けていくので、2つのスキルは今後とも高めたいと思っています。
ただ、「今、うまくいかないな。」「私、先生向いていないかな?」と思っている人に読んでほしいと思って、今日は記事にします。
授業する上で必要なスキルは見えやすい「授業者スキル」

授業を安定させるには、「子どもがわかる授業が大事」とよく言われます。
ここでは、この授業する上で大切なスキルを参考図書に倣って「授業者スキル」ということとします。
授業において、子供達は、ある事項を学習する、できるようになることが最大の目標だからです。
たくさんの授業書、教育書で様々な方法が今まで提案されてきました。
私のブログでも、いろいろ紹介してきました。
いろいろ話しましたが、授業を安定させるための鉄則は、「授業の流れを安定させること」です。
私の授業は、次のような流れで流れていきます。
- 本時の問題を解くために必要な知識の復習(前時の内容、1年前の内容)
- 本時の問題の提示
ー問題を解く上での見通しをもつ
ーここを乗り越えれば解ける「課題」を明確にする - 1人で考えをまとめる
- 隣同士考えを交流する
- 全体の場で考えを話す
ー複数の考えが出る場合は比較する
ー複数の考えが出る場合は、どこが一緒考える。 - 問題演習をする
- 振り返りをする
オーソドックスな一斉指導の学びは、基本的にはこれでOKです。(「個別最適化の学び」の必要性が裂けばれていますが、勉強不足です。また挑戦したら報告します)
また、授業を検討する際には、1〜7のそれぞれの各場面において、子どもにフィットした手立てを講じられていたかが焦点になります。
講じた手立てについては、授業録画や授業見学で見ることができるので、「授業者スキル」として見えやすいのです。
日本では授業研究と題して、どの学校でも盛んに行われ、日本式の授業スタイルが戦前から確立されてきました。
外国では、授業研究のような概念はなく、各先生が独力で授業を進めることが多いようです。
一部の外国の学校では、日本の授業研究を真似て「Lesson study」という名前で取り入れる動きもあるようです。
見えない部分が多い「担任スキル」

「授業者スキル」に対して、担任として学級経営していく上で必要なスキルを「担任スキル」と言うこととします。
この「担任スキル」は、「授業者スキル」よりもスキルとして確立しづらいのが特徴です。
その理由は、先ほどの授業の流れのように、同じ指導をすれば、ある程度同じ結果を得られることは到底ないからです。
例えば、「体育の授業になると、気持ち悪いと訴える子ども」がいたとします。
原因はどんなことが考えられるでしょうか?
- 運動が苦手でやりたくない
ー太っているから苦手、今まで上手くできたことがないという精神的なもの - 同じグループの子に、冷やかされ嫌な気分になるからやらない
- 実は怪我をしていて隠している
さっと、思いつくだけでもこれだけ考えられます。
さらに、これが複数同時に起きていて、複雑化している場合があります。
これだけいろいろ原因が考えられるのに、どの子どもにも問題行動の背景を考えることなしに同じ指導をしても、改善に向かうわけがないのは皆さんも納得いくことでしょう。
ある子どもの問題行動に対して「指導・支援」をしていくのですが、その指導・支援を講じるまでの過程は、授業だけにとどまらず学校生活全体のどこかで行われます。
さらには、個別への働きかけはもちろん、全体に働きかけする中で、個を変えていくことをねらったりするので、「授業者スキル」よりも「担任スキル」は顕在化しづらいです。
当然、録画や見学も難しいので、各先生の個人的な経験に基づく指導になることがどうしても多いのです。
また、問題行動が改善したというのはテストの点数のように数値では測りにくいので、結果が目に見えてわからないというのも「担任スキル」の特徴です。
もちろん、学校現場では、「いじめ不登校対策支援会議」や「特別支援の生徒対策委員会」のような名前で、全体で問題を共有し、その子に対しての対策を様々な教師の知見や視点から、少しでも改善に向かえるようにしてきました。
「授業者スキル」と「担任スキル」の混同が問題

学校現場では往々にして「授業者スキル」と「担任スキル」を区別せずに、「教師力」という言葉で一括りにされてきました。
例えば、「学級経営が上手い先生は授業が上手い」とか、「授業が上手い先生は子どもをよく見ている」なんてことを聞いたことはないでしょうか?
つまり、授業者スキルよりも担任スキルの熟達ができれば、授業力が向上できるということがよく語られます。
本当でしょうか?
前章でも書いた通り、「担任スキル」は伝達されにくいものです。対して、「授業者スキル」はある程度伝達可能で形にしやすいものです。
「授業者スキル」を向上させることで、「担任スキル」は向上できないのでしょうか?
私は、この「担任スキル」がどのように向上させていいかわからず、苦しみました。
「担任スキル」が無いも先生は、授業も上手くならず、いい先生にはなれないと思ったからです。
もちろん、「授業者スキル」と「担任スキル」は先生という仕事を支える2つの重要な車輪です。
ただ、二つの力を混同して「教師力」と括ってしまっていることが、教師を続ける中で苦しくなってくるのではないかと思っています。
最後に

今回は、教師として必要な力を「授業者スキル」と「担任スキル」とすることで明確になるのではないかという提案でした。
この2つが混同して「教師力」としているから、先生の仕事はとても複雑になっているのではないかなと思っています。
「教師向いていないのかな?」と悩んでいる先生は一度立ち止まって考えて見て下さい。
今、自分に必要な力を見直してみましょう。
きっと突破口が見えてくるはずです。
「授業者スキル」については、こちらにまとめました。御覧ください。
これからに向けて
アメリカでは、先生は授業をして、カウンセラーが進路指導、生徒指導は校長・教頭先生の役目と分業制で行われています。
対して、日本は、担任の先生が全て抱え込みます。小学校の先生は特に顕著ですよね。
できれば、アメリカほどでないにしても、日本も授業を主に行う先生、担任業務(学活・道徳・行事など)を行う先生と分かれるともう少し先生の仕事がハッピーになるのではないかと考えています。
ただ、なかなかそうはなりません。
そこで、「担任スキル」をわかりやすく整理していこうと思います。こちらの記事をご覧ください。
工事中

参考文献・参考HP
参考文献
参考HP
http://niigata-rikyo.jp/pdf/reference_lessonstudy.pdf
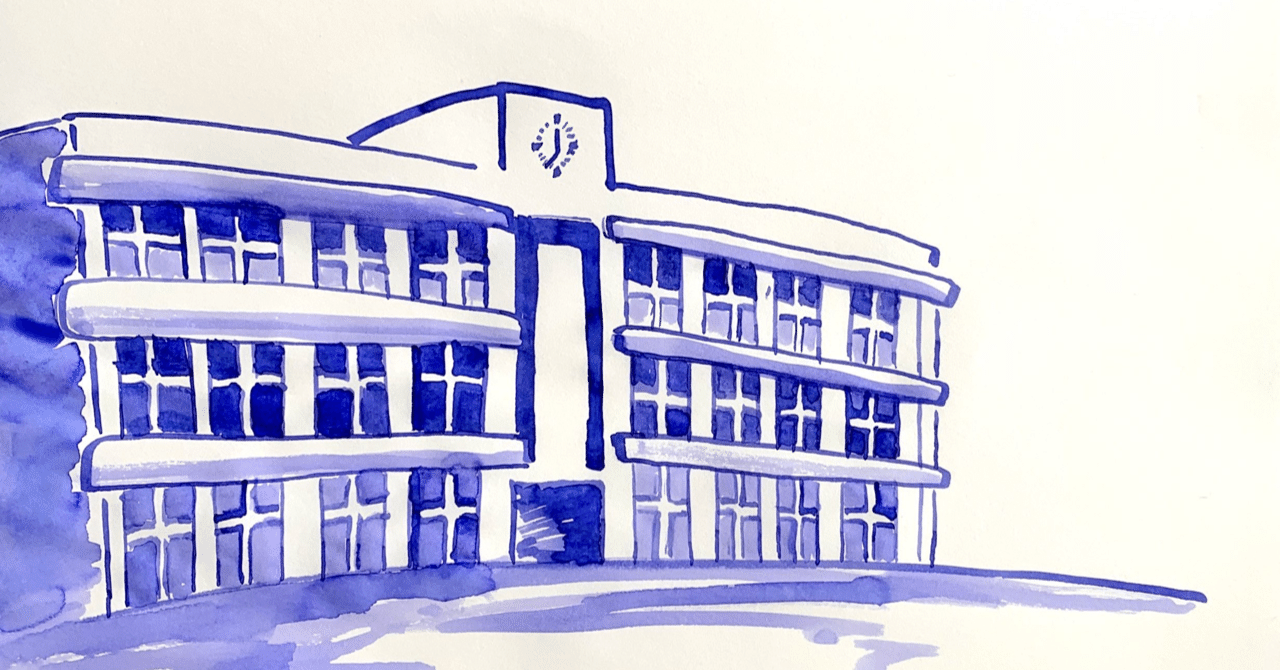





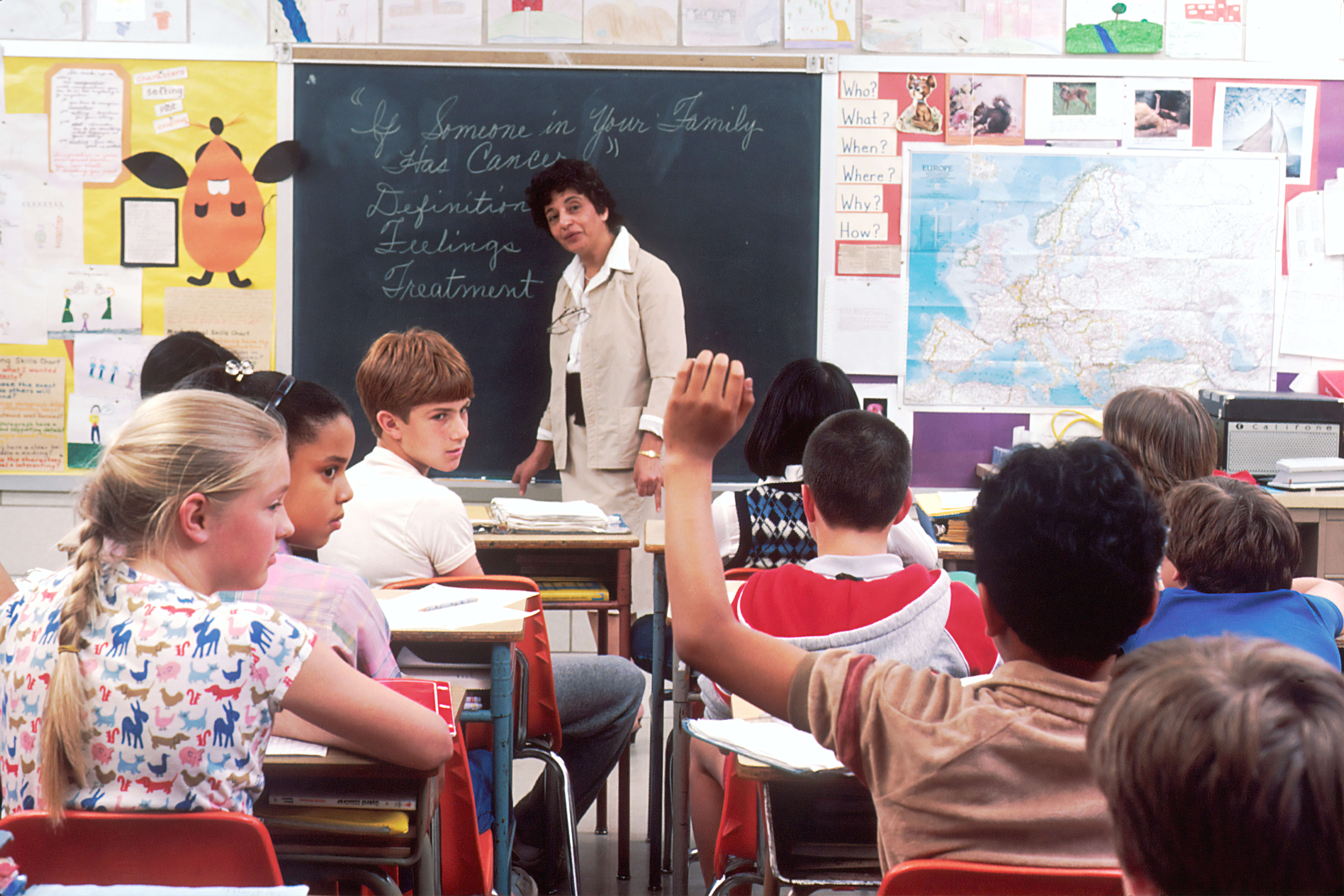



コメント