そろそろ、自己啓発本、ビジネス書で一番有名と言って良い「7つの習慣」を読んでみようとついに思い立ちました。
私の奥様も会社勤めをしています。
そこでの研修で「7つの習慣」についての研修を受けてきたと言うではありませんか。
丸1日合った研修で、この本だけをテーマに講演を聞いてきたそうです。
ビジネス書の中でも金字塔的なこの本。これは私も負けずに読まないと!と思いました。
と言っても、今回は、そのエッセンシャル版。
「まんがと図解でわかる スティーブン・R・コビーの7つの習慣」というエッセンシャル版を読もうと思います。
ちゃんと原作も買ったのですが、思ったよりも厚い・・・。
こういうのは、解説本を読んでから、原作を読むと、理解が早くなると言うことを以前、別の本で勉強しました。
今回は「7つの習慣 エッセンシャル版」だけを読んでの感想をまとめます。
また、原典についての本を読んだ感想は、別の記事にしてまとめます。
結果を求めるために過程を重視しよう 「P/PCバランス」という考え方
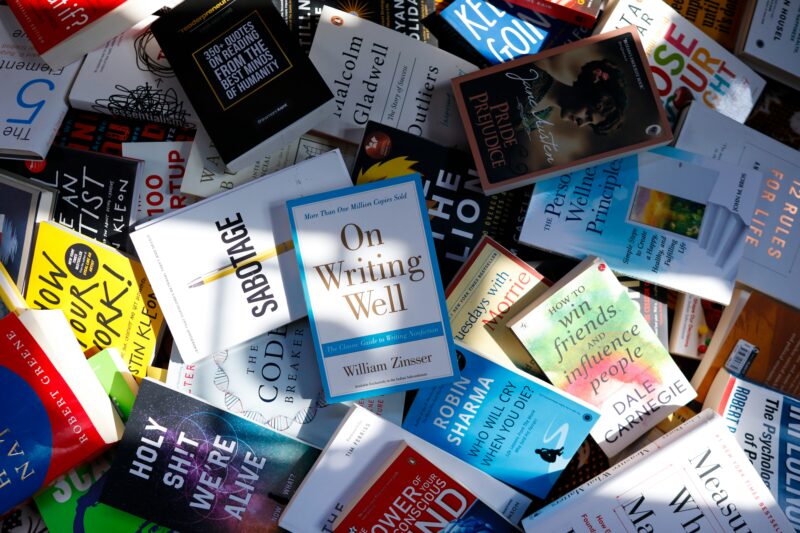
さて、我々は努力をすると、結果をつい求めてしまう。
それは仕方がないことだと思います。
努力したからには、何かしらの成果がついてきてほしい。そう思ってしまうのはしょうがありません。
誰だって報われたいのですから。
頑張っているのに、結果が出なくてイライラしてしまう。
学校だとそんなことばかりです。
テスト勉強したのに、点数がついてこない。
部活の練習頑張ったけれど、選手に選ばれなかった。
受験で、志望校に受からなかった。
義務教育の時から、そうやって競争の中で生きています。
ただ、その成果を急いで求めるために、いろいろ損をしていないでしょうか?
私の経験から
今振り返れば、自分も受験勉強で同じようなことをしていたと思うのです。
高校3年生になり、受験の年。
毎日、志望校合格に向けて、休日は10時間、平日は学校から帰って4時間は勉強すると決めて、勉強をしていました。
ただ、勉強の仕方が不味かった。
理系だったので、数学や物理の勉強を必死こいて勉強をしていましたが、点数が上がりませんでした。
なぜなら、解答を丸暗記して、他の受験問題に応用しようと考えていたからです。
そんなことをしていたのでは限界がありました。(英語は素晴らしく点数が伸びましたが)
受験問題で使用する定理や考え方の原則を洞察することなく、解答を丸暗記していたのでは力がつきようがありません
他の問題に出会った時も、定理や考え方の原則がわかっていなかったので、結局解けない。
解けないので丸暗記する。
他の問題も解けない。
丸暗記する。。。。という悪循環に。
ある程度までは対応できるのですが、難関大の問題は手も足も出ませんでした。
今思えば、しっかりと教科書を読み、なぜこの定理が導出されたのか。定理そのものにどんな意味があるのか、解釈ができるのか。
そこをしっかり考えて身につければ、もう少し点数が上がったのかな、なんて思います。
結果を求めすぎるあまり、焦って、勉強の内容はお粗末なものでした。
PerformanceとPerformance Capability
本の中では、PをPerformance(望む成果)。望む結果や、目標達成のこと。
PCとはPerformance Capability(望む成果を生み出す能力や資源)。目標達成のための能力やそれを可能にする資源のこと。
この2つのバランスを常に考え、努力をすることが大切にすることが大切であると述べられていました。
先ほどの私の例でも述べたが、人間は物事の結果を得ることを急ぎすぎている。本当は、それを可能にする能力や資源を育てる長い目を持つことが重要です。
常に「何のために努力をするのか」を考える。結果ばかりに目を奪われると方法の過ちに気づかない恐れもあるので、上手に、PとPCのバランスを考えていきましょうというわけである。
結局、受験を突破するには、自分を高めるしかないのです。高めると言うのは暗記をするではあありません。
数学の公式や解法を丸暗記するのではなく、その裏に潜む数学の思考を考える。
時間をかけて育てるしかないのです。
志望校に合格するという目標に固執するあまり、間違った方法(暗記)を選んでしまったというわけです。大失敗でした。
大人になった今の方が、自分にあったペースで成長できる。
さて、先ほど自分の失敗談を述べたが、間違った方法を選んでしまうのも無理はないとも思います。
受験に日は決まっていて、のんびりなんてしていられないからです。
逆に、大人になったからこそ、ゆっくりPCを高めることができると思います。
例えば、今、自分は学会論文にチャレンジをしている。
学会論文を投稿して、受理されれば、自分の学びを日本の教育に還元できるからです。
もしかしたら、新しいキャリアやつながりが見えてくるかもしれません。
最悪、論文が認められなくても、仕事はしているし、稼ぎも問題はありません。
何度もチャレンジして、成果が出たらラッキーだと思っています。
リミットといえば、自分が死ぬまで・・・。自分の興味や情熱がなくなるまで続ければいい。
もし挫折してしまっても、論文を書くために勉強したことや経験は、絶対教員人生で生きるところがあるとおもっちえます。。
だから、周りに合わせるのではなく、自分のペースで、コツコツ進んで、成長をしていきたいと思います。
学校だからこそ、卒業後までを見据えて、社会に出た時を見据えて子どもを育てたい
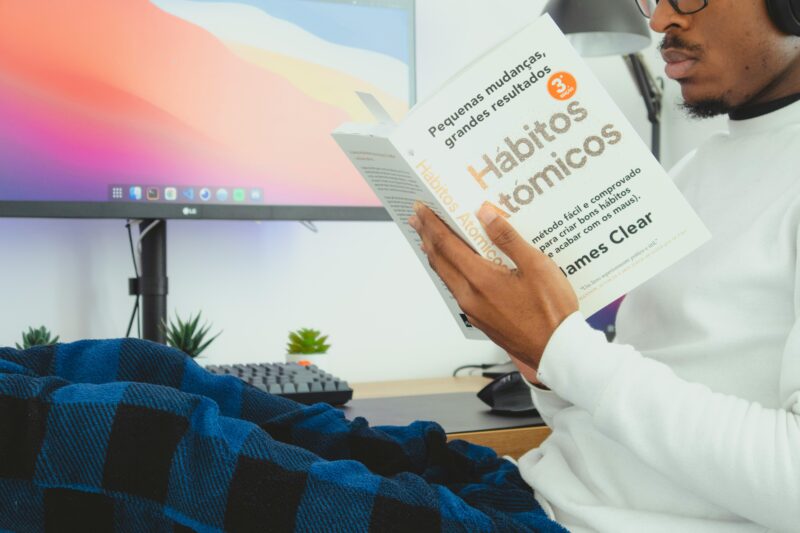
話は少し変わりますが、中学校で、一つ大きなハードルが高校受験です。
自分の学校がド田舎なので、高校の選択肢も多くはありません。高校から、下宿をするという生徒もいます。
ただ、都会よりも受験に限って言えばのんびりとした学校です。
たまに、都会の方から、勉強で疲れて、人間関係に疲れて、こっちの方に転校してくる生徒もいます。
なかなか大変だっただろうなと思いますし、こっちの空気に触れて、ノンビリ復活していく生徒の姿を見ます。
さて、ここで皆さんに問いたいのは、「学校はどういう力を伸ばすとよいのか?」です。
勉強ができることに越したことはないが、中学校段階では職業と勉強が結び付かず、必要感が少ないという点は否めないと思います。
最近の教育の流行や、子どもの課題などを考えて、自分は「自分で決断する。」力をもっと育てたいと思っています。。
文系・理系どっちがいい?レベルの話ではない。
「自分の将来を見据えて、今、何を勉強すべきなのか」それを考える力である。
たとえば絵が好きで、「イラストレーター」になりたいという子がいたとします。
絵が好きなら「上手に描く方法」を学ぶ。
上手に絵が描けてから、同人誌を作ってコミケで売りたいなら、印刷会社に問い合わせて、本にできる方法を知る。
Xで投稿してフォロワーを増やしたいなら、SNS運用の方法や印刷方法を学ぶ。
儲けがでたら、確定申告や、節税の方法を勉強する。
学校でノートの上で勉強するだけが勉強じゃない。
そうやって、社会で生きていくために必要なことを自分で学ぶ事が大事なのではないかなと思っています。
必要感があるから、生徒は前のめりになって勉強をする。
そんな壮大な人生の実験場に学校はできないかなと考えています。
ブレイディみかこの「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー2」にも、主人公が音楽を仕事をするために、ライブハウスに電話をして、舞台装置などの勉強をして、レポートを出すといったエピソードがありました。
こういう教育も外国ではある見たいです。
難しい!という声もある。今の詰め込み教育では難しいところも重々承知してます。
けれど、そんなことも必要なんだろうなと頭の片隅におきながら授業をしていくことで、今やっている授業も変わっていくんだろうなと思っています。
「ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー2」の感想はこちらを御覧ください。
最後に
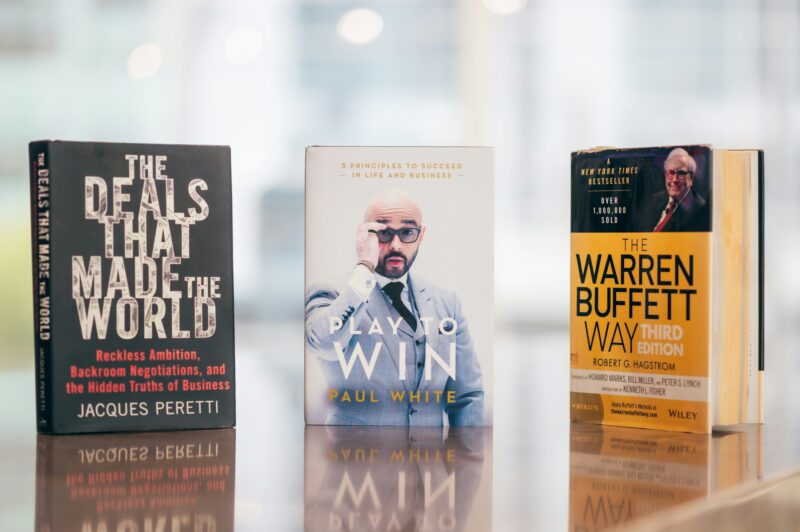
7つの習慣から、「大人の成長」「子どもの成長」について考えを書きました。
私の勤務している学校では「探究の時間」と言うのを始めました。
夏休みの自由研究的なことを学校でやれればと思っています。
今の子どもは何に興味をもって研究をするのか。
その興味を探るだけでも、とても面白い試みだと思っています。
生徒の個性を伸ばしつつ、自分も成長できるそんな機会にしたいと思っています。
探究の時間の概要は、こちらの記事に詳しく載せました。合わせてご覧ください。

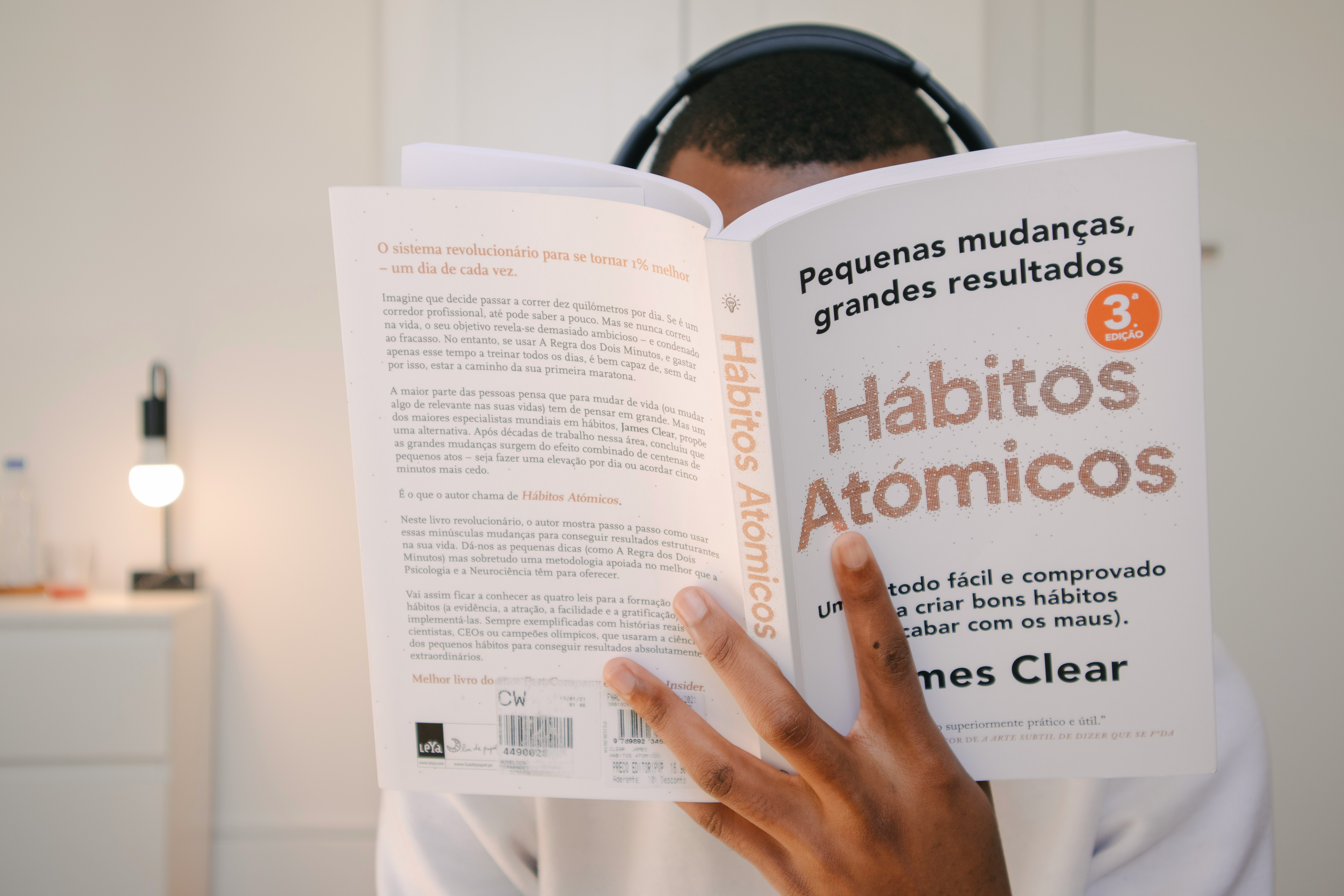
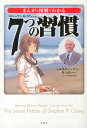






コメント