教員の多忙化解消のために、「勤務間インターバル」を導入しよう!という話が出ています。
東洋経済オンラインで連載されている教育研究家 妹尾昌俊のコラムにも「勤務間インターバル」の導入を訴えるコメントがありました。
そもそも勤務間インターバルってなんぞ?
学校現場にあうものなのか?
よくわかりません。
今日はそこについて、調べて学んだことを書いておきます。
「勤務間インターバル」とは

1993年EUで発令された「労働時間指令」をお手本にしたもので、「勤務間インターバル」「勤務時間インターバル」と呼ばれます。
EU指令は「24時間のうち11時間は休息時間をとらなければいけない」というもので、簡単に言えば、何時間もぶっ通しで働くことを禁じ、一定時間の休憩をはさむことを義務付けています。
(中略)
休息の11時間には、当然、睡眠や食事の時間、家族で過ごす時間、プライベートの時間も含まれます。
この勤務間インターバルは、日本ではまだ義務化まで至っておらず、努力義務にとどまっています。とはいえ、最近少しずつですがこの言葉を広がっており、推奨する企業や官公庁も出てきています。このような形でハードワークが改まることを期待しています。
ー片野秀樹.「休養学 あなたを疲れから救う」.P202 ~P203(蛍光部分は原文ママ)
とのことです。
前日遅くまで残業したら、次の日は、遅く出社していいということですね。
ヨーロッパで勤務間インターバルが導入される背景にはキリスト教がある
ドイツでは「連邦休暇法」という法律があり、従業員に年間24日以上の休暇を与えないと雇用者が罰せられてしまうそうです。
なので、年度始まりは、いつ、だれがバカンスを取るのか、休みを取る日取りから決め始めるそうです。
だから、1カ月バカンスなんてことができるんですね。
そもそも、こういう考えになる背景には宗教上の理由があります。
日本では「勤勉」なことは評価されますが、キリスト教の考えでは働くことは「罰」なのです。
苦役としてやらされているという発想だから、欧米の方は一緒に働いていても「早く帰りたい、会社には可能な限りいたくない」という感覚を持っているそうです。
また、みんな休暇やバカンスをとるのが当たり前なので、「仕事に穴が出てもしょうがない」と会社も取引先も考えるようです。
休んだ時はお互い様という考えが浸透しているのです。
(アメリカはそれ以上にお金を稼ぐことが宗教上美徳(日本で言う善行)とされるので、バリバリ働くという背景があるそうです。)
妻も、外資系の会社で働いているので、欧米の同僚が1週間バカンスでいないということがあります。
連絡しようにも絶対相手はパソコンを見ないからしょうがないなんてことをいつも言っています。
日本では、勤務間インターバルは浸透するのか?

ここまでまとめると、休暇を取ることが、欧米では容認されている。
働くことは罰であり、前日長く働いたなら、しっかり休んでから仕事をするべきという考えが浸透していることがわかります。
翻って、日本を見てみましょう。
ちょっと体調を崩したくらいだったら、仕事をするのは当たり前ではないでしょうか?
仕事に穴をあけるのは申し訳ないと考える人は多いです。
また、長く働くことも美徳と考えている人はいまだにいます。(昭和時代は特にそうだったでしょう)
さらには、「ほかの人が変わりをしないと困る」という話にもなります。
学校で欠員が出ても、いる人員で回してしまいますよね。
それで、学校がまわらないとクレームを受けるなんてこともあります。
群馬県高崎市では、朝7時から学校をあけて、子供の面倒を学校で見るといったことを始めようとしています。
もしトラブルが起こったときは、だれが対応するんだともめにもめています。
人がいないから(サービス低下は)しょうがない、そういうふうに顧客(学校で言えば保護者や地域)が理解がないと、勤務間インターバルは絵に描いたモチになりそうです。
最後に
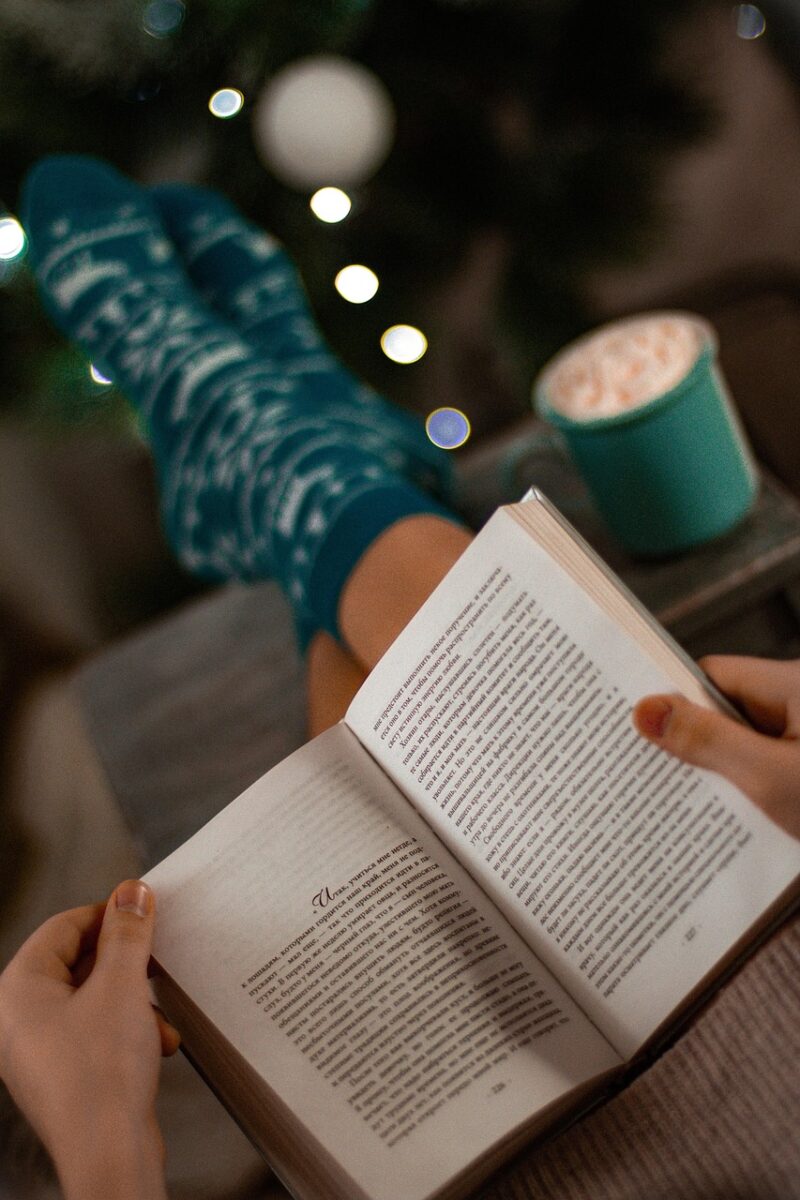
勤務間インターバルの導入は、残業代の出ない教員には必須だと思います。
昨日残業して、出てくるのが遅くなっても、定時になったら勤務が解かれるような制度にならないと意味がないとも思いました。
ただ、今の日本の文化や、周囲の学校への理解を考えると、なかなか難しいだろうなという気がします。
先生の勤務も、保育園みたいに「遅番・早番」にするとか、そもそも人員をもっと増やす必要もありそうで宇s。
そういえば、オーストラリアに行ったとき、学校は教員がストライキを行っていて、授業なし。
生徒はどうしていたかというと、だれもいない学校(用務員さんはいたのかな)の校舎で好きに過ごして帰るということをしていました。
もしトラブルがあったらどうなるんだろうと思いましたが、そういう風土や保護者の理解があるから、勤務間インターバルもできるんだろうなと思いました。
ちょっとずつ実装していって、完全に理解を得られるには20年以上の月日がいるんだろうなと思いました。
みなさんの学校では、斬新な改革ありますか?ぜひ教えてください。

自分の行っている働き方改革については、こちらにまとめています。併せてごらんください。
筆者の片野秀樹さんを参考に書いたブログ記事はほかにもあります。併せてごらんください。
参考文献・参考HP
参考文献
参考HP

https://news.yahoo.co.jp/articles/65667ea6838dd54f47aa42269286caff35fa6711









コメント