授業をするにあたって、盛り上がっている授業が一番いい!
そんなことを思っていた時期がありました。
そもそも、いい授業とはなんでしょうか。
いい授業を達成するためにはどんなことを気をつければ良いのでしょうか?
今日はそんなことを考えてみましょう。
いい授業ってどんな授業?

いい授業ってどんな授業でしょうか?
私が初めてすごいなと思った授業は、大学4年生の時に卒業旅行で見に行った筑波附属小学校の算数の授業を見たときでした。
算数・数学教育のレジェンドともいえる先生達が、つい考えたくなる発問をして、子ども達が考え、活発に意見を交流する。
そんな授業に憧れました。
先生になって、最初の1年目。教科書の内容を追うので精一杯。
筑波附属小学校の先生の足元にも及ばない授業でした。
授業をしても、子供は混乱するばかり。
その中で、「いい授業ってなんだろう?」と思いました。
今の自分の力では筑波附属の先生のような授業はできない。
けれど、目の前の子供達が勉強して良かったと思える授業はできるようにしなければならない。
そこで、「そうか、いい授業とは、筑波附属のような活発な授業ではなく、目の前の子ども達が、『勉強して良かったな』と思える授業をすればいいんだ。その先に、意見が活発にでるクラスとか、先生の発問からドンドン考えを出し合うクラスになる。まずは、子どもが『勉強してよかった』と思える授業を作ろう。」と目標を改めました。
子どもと語るときに大切にした、ネガティブ・ケイパビリティ

新人の頃、私の研究授業の協議会でよく指摘されたのが、「先生、喋りすぎ」という言葉でした。
教師が発問する→子どもが黙って考える→教師が付け足す→さらに子どもが黙る→授業が進まない
こんな悪循環を起こしてしまっていたのです。
さて、そんなことを思い出したのが、以下の一節でした。
インタビューを書籍化・要約することを仕事にしている筆者が、インタビューをしていく上で、以下のことが大切と語っていました。
少し長いですが、引用します。
特に、インタビューやヒアリングで、少し聞きにくいけれど本質に迫る問いを投げかける場面もあるでしょう。そうした時は勇気がいるのですが、冒頭で「差し支えない範囲で良いのですが」などとクッション言葉を入れつつ尋ねます。
相手が沈黙することもあります。単に「答えにくい質問」と思っているケースもあれば、「今まで考えたことがなかったから、逡巡している」というケースもあるでしょう。
そんなときには「ネガティブ・ケイパビリティ」の出番です。
作家で精神科医である帚木蓬生さんの著書『ネガティブ・ケイパビリティ』(朝日出版)によると、ネガティブ・ケイパビリティとは、「事実や理由を性急に求めず、確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力」を意味するそうです。
簡単にいえば、「わからないことをわからないまま、宙ぶらりんの状態で受け入れ、耐え抜く」ことです。
相手が沈黙していると、ついこちらから何かを話さなくてはと焦ってしまいがちですが、そのときに「宙ぶらりんの状態でも、受け入れて待つ」という姿勢を思い出すと、落ち着いて相手から出てくる言葉を待てるようになります。
ー松尾美里.「読む・聞く、まとめる、言葉にする」.p103-p104(太字は原文ママ)
引用の「インタビュー」の部分を「授業での発問や、生徒指導での生徒への聞き取り」と置き換えて読んでみましょう。
そのまま、学校で生きる一言になっていると思いませんか?
私は、授業ではよく子どもから言葉が出てくることが大切だと思っていました。
たくさん意見が出てくることで、盛り上がっているように見えるからです。
でもよく考えれば、授業は盛り上がっていればいいわけではないのです。
大事なのは、今日学習したことを理解することなのです。
それは、雑談のように考えている中で、出てくることもあれば、じーっと考えて出てきた一つの言葉、それでクラスの全員がハッとする。そんな授業もあるはずなのです。
生徒が全くとっかかりがつかめず悩んでいるのか、それとも、引用のように「先生の質問は、考えたことのない視点の質問だぞ。よくよく考えなければ」と思っているのか。
そこを教師として見極めなければならないのです。
そのときに大事な合言葉が「ネガティブ・ケイパビリティ」なのです。
生徒指導もネガテイブ・ケイパビリティが大事

ちょっと話がそれますが、生徒指導の場面でもネガティブ・ケイパビリティは大切だと思います。
生徒指導の時に、生徒からいろいろ聞き取ったり、指導をしたりする場面があります。
生徒が、黙って答えなくなるということもよくあります。
原因は、自分が不利になる話になるから、その時のことを思い出しているからのように色々考えられますが、やっぱりここでも大切なのは「ネガティブ・ケイパビリティ」です。
子どもが黙っているところを、先生が追い討ちをかけると、先生の主観が入ってしまい、きっちりとした聞き取りや指導ができなくなってしまいます。
もし、子どもが嘘を言うようだったら、それについて矛盾を指摘できます。
思い出しているなら、しっかり思い出して話してもらった方が、教師の主観が混じることが少なくなります。
子どもに質問をしたら、待ってみる。
これはよほど自信や経験がないとできません。
先生でさえ、沈黙の時間は辛いですから、子どもは沈黙の時間をもっと辛いと感じることでしょう。
しっかり待って、子どもの言うことを聞くのが大切です。
この営みが丁寧な生徒指導につながっていきます。
最後に

今回こんな話を思い出したのも、記事の途中で引用した、松尾美里さんの「読む・聞く、まとめる、言葉にする」の本を読んで、インタビュアーとして心掛けている部分を読んだからでした。
インタビュアーと教師、全く畑が違う職業ですが、「話を聞いて、それに対してコメントを返して、授業、生徒指導やインタビューを作っていく」という中には通じるものがあることを感じさせられました。
皆さんは、授業で意識していること、大切にしていることはありますか?
ぜひコメントで教えてください。

松尾美里さんの本を参考にした記事がまだあります。合わせてご覧ください。
「いい授業」について考えている記事もあります。私の教育論にも関連しています。合わせてご覧ください。

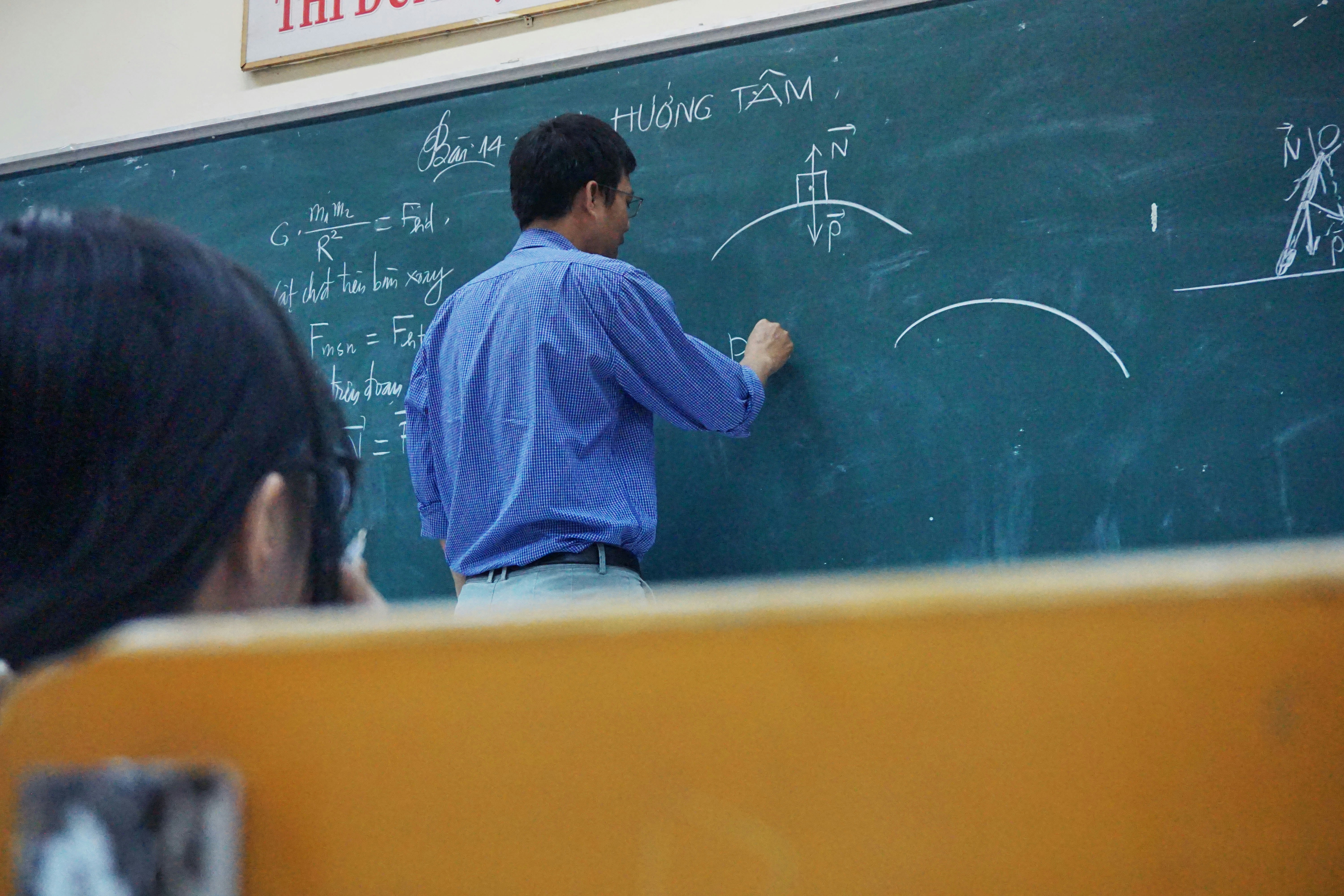







コメント