みなさんは授業を磨くためにどんなことをやっていますか?
研究授業では、指導案を作って、授業をして、事後検討会をして、みっちりやっていると思います(ただ、そういう風景も少なくなりましたね)
研究授業は、力を入れますが、毎日の授業をそこまで気合をいれてやることはできません。
本当は、日々の授業で、色々試行錯誤をして、研究授業では試行錯誤の成果を出すというのが理想だと思うのです。
本当に大事なのは日々の授業なのです。
なかなか忙しいですが、日々の授業を振り返り、本当の授業力を高めたいですね。
今回は、自分がやっている「3分でできる授業振り返り術」を紹介します。
準備
- ノート(おすすめはA4、B5でも可)
- 授業の板書
「3分授業振り返りノート術」のやり方

気づきを箇条書きする
授業で気づいたことを羅列します。
- いつも発言しないAくんが発言できた。
- グループワークが盛り上がった
- 反面、クラス全体の場で意見を言うときは手が上がらなかった
- Bくんが理解できていなかった。
こんな感じです。そこから、今回考えたいテーマを2つまで選びます(多すぎると、振り返りが大変です。)
もちろん、箇条書きをくっつけたり、分けたりして、一番考えたいテーマにしても構いません
今回は、「いつも発言しないAくんが発言できた。」と「グループワークは盛り上がったのに、全体の場では手が上がらなかった。」ということを考えたいと思います。
気づきを問いに変える
気づきだけでは、授業の振り返りになりません。
気づきを問いに変えていきます。
気づきの最後に「のはなぜか?」という言葉を入れていけば問いに変わります。
先程の例だったら、「いつも発言しないAくんが発言できたのはなぜか?」、「グループワークは盛り上がったのに、全体の場では手が上がらなかったのはなぜか?」というふうに問いに変えていきます。
問いに対しての理由を考えよう
問いが立ったら、振り返りノートに書いていきます。
ノートの書き方は以下のような感じです。

ノートの左上に、先程の「問い」を書きます。
その下の板書の写真を貼ります。
そしてその下に、問いに対する理由を書き出します。
箇条書きで結構です。
いつも発言しないAくんが発言できたのは、
- 虫が好きでよく観察をしている
- 自分の知っていることだったから自信を持って発言しようと思った
- 事前のグループワークでも、友達がAくんの話をよく聞いていた
→やっぱり自信がもてた - 虫の写真を黒板に貼ったので、「何について考えるかが」Aくんが理解しやすかった
というふうに書いていきます。
結論を書く
理由を元に結論を書いていきます。
いつも発言しないAくんが発言できたのは、
- Aくんが興味のある内容だったから
- 写真を貼って視覚支援をしたから、Aくんは何を考えればいいかがわかった。
- グループワークでAくんの話を聞いてもらえたから
となります。
結論を一般化する
ただ、この結論は、他の子にも当てはまるはずです。
Aくんだけの結論にするのではなく、一般化することでさらに、授業力を高めることができます。
一般化するには、Aくんという固有名詞を「生徒、児童」に変えればOKです
いつも発言しない生徒が発言できたのは、
- 生徒が興味のある内容だったから
- 写真を貼って視覚支援をしたから、生徒は何を考えればいいかがわかった。
- グループワークで生徒が話を聞いてもらえると自信をもてる
こうなると、授業で何を大切にすればいいかが、自分でまとめることができますね。
さらに問いを深めよう
前回の振り返りで、「興味のある内容を提示すること」、「視覚支援をすること」、「グループワークが大切であること」がわかりました。
授業を続けていくと、グループワークがうまく行かない時が出てきます。
そうなると、「いままでグループワークがうまくいっていたのに、今日うまく行かなかったのはなぜか?」という発展した問いが生まれてきます。
そうすると、「発問の仕方」、「発問の提示方法」、「生徒の体調」などなど、様々な視点でグループワークについて考えられます。
そうすると、以前の問いよりもさらに発展した問いになってきますよね。
これを続けることで、自分の中に、授業の芯ができてきます。
大切なのは「授業の芯」を作ること

自分なりの「授業の芯」を作ることはとても大切です。
芯を作るということは、「先生はこんな授業を毎日するんだ」と子どもが安心して毎日の授業を受けられるようになるからです(毎日奇抜な授業をやっていたら子どもも疲れちゃいますよね)。
そして、芯を作ることは、他人の授業を見るときの考える軸になります。
自分の授業を相対化することによって、授業の良し悪しを考えることができるようになるのです。
芯は変えてはいけないものではありません。
良いところをどんどん盗み、自分の授業力を高めていきましょう。
「振り返りノート」は自分の授業だけでなく、他人の授業を見て、考えたことを書いてももちろんOKです。
きっと自分の中にはなかった視点が見えてくることでしょう。
最後に
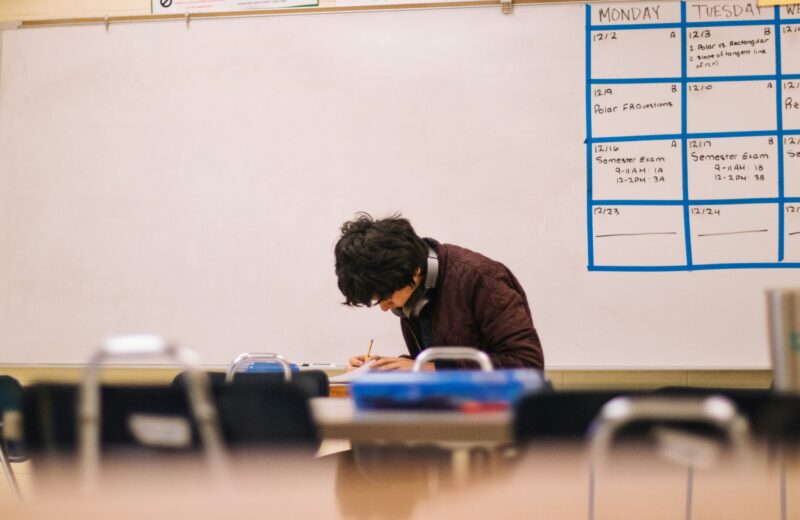
今回紹介した「授業の振り返り」の方法。
実は、このやり方は荒木俊哉さんの「こうやって頭の中を言語化する。」に紹介されている「言語化ノート」の技を真似をしています。
大事なのは、自分で問いを作り、結論を出し、次の授業に活かす。
この一連の営みだと思うのです。
自分で考え、自分で改善する。
その中で、自分の授業力をどんどん高めていきましょう。
また、問いが自分の中で明確になると、教育書を読んで頭に入ってくる量が劇的に増えますよ!
自分は、その様子を、ブログに掲載するという感じで、ブラッシュアップを図っています。
みなさんはどうやっていますか?是非コメントで教えて下さい。

以下の記事は、この振り返りノートを使って、振り返りをした授業記録です。併せてごらんください。
指導案の作り方も紹介しています。合わせてご覧ください。
教育実践論文にも、この方法を応用して挑戦できます。
参考文献
Audibleに入会すれば、「こうやって頭のなかを言語化する。」を99円で聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!











コメント