今回は速読、多読・選書に力を入れすぎることは大切ではない!って話をします。
巷には、速読、多読をしましょう!選書が大事!っていう煽りの本がたくさんあります。
速く読むことができれば、たくさん本を読むことができる。たくさん読めば知識が増やせる。
さらに良書を選ぶことができれば、知識の溜まる速度が速くなる。
結果、キャリアアップにつながるということが言われます。
あのね、10年間で本を10000冊読んだんですが、そんなことないんですよ。(私の読んだ本はこちらで見れます)
そしたら私はもっと出世できているはず・・・。

今日は、そんな話です。
前回の話はこちらです。
速読という幻想
速く読めるようになれば、読書量が増え、人生に役立つ読書ができるようになる。
こんなことがよく速読指南書に書かれています。
速読の技は大体、「本を写真みたいに読む」とか、「斜めに文章を読んでいく」という方法が書かれています。
一応私できるんですよ。「写真みたいに読む方法」は、漫画でよくやります。
全体のコマの割り振りとセリフを斜めに読んでいくことで、ジャンプコミックス1冊5分で読むことができます。
「斜めに文章を読む方法」は、普通の文章の本でやっています。
ただどちらの読み方も、読んだ瞬間に内容を忘れています。読んだあとの余韻は残りますけどね。
速読にとらわれると、内容が全く頭に残らない。つまり、全く知識が身につかないのです。
2008年に速読の世界チャンピオンにハリーポッターの最新刊を読んでもらう実験をしました。
チャンピオンは47分で本を読み切ったそうです。チャンピオンの感想は、
「最高傑作の小説だよ。子どもたちに人気があるのもわかる。子どもたちの創造力をかき立て、また子どもたちが心を悲しませるシーンもあった。でも、この作品は最高だ」
というものでした。
・・・これじゃぁ何の本の話かわかりませんよね。
どんな本にも当てはまるような当たり障りのなさすぎる感想です。
こんな感想文を出したものなら、先生に大目玉でしょう。
実際に、最近の研究だと、速読をしても頭に内容が残らないことが明らかになってきています。
要約すると、
- 読むスピードを上げると、読んだ気になるだけで内容の理解度はむしろ下がる(理解とスピードはトレードオフの関係にある)
- 読書のスピードと時間を決める要素の中で、目の動きある周辺視野が占めるのは10%イカしかない
つまり、テキストを写真のように眺める手法にはほぼ効果が認められず、速く読むことに特化した読書法では、本の内容のほとんどが頭に残らないというわけです。
読むスピードとの難易度
「読むスピードを上げると、理解度はさがる」は、別の見方をすると、「速く読める本は、内容が簡単である」ということができます。
反対に丸一日かけても読みきれない、歯応えのある本を読み切ることができれば、すごい学びがあります。
ただ、丸一日かけても読みきれない本を読み切るには、相応の覚悟がいりますし、血肉にするにすごく大変で、普通は挫折します。
本当に自分の学びになるのは「ちょい難」の本を読むことです。
詳しくはこちらの記事に紹介したので、自分に合った本を探してみてくださいね。
多読という幻想
「本が好きな人は、たくさんのジャンルの本を同時並行でたくさん読んでいる。多読をするから、興味が拡がり、読書の習慣が途切れないのだ。」
というのが、多読をお勧めするよくある理由です。ただ、それは勘違いです。
英誌「エコノミスト」が「過去10年間で最も影響力のる経済学者」と評し、読書家としても知られるタイラー・コーエンは、「読めば読むほど、1冊あたりの情報の価値は低下する。」と言っています。
最近、私は読書術の本を5冊ほど読みました。
ただ、5冊読むと、大体同じことが書いてあるなと思うようになりました。
それもそのはず、巻末の参考文献を読むと、大体同じ文献や論文が参考文献に挙げられているのです。
著者の体験による書き方や、著者の書きっぷりが違うだけで、言いたいことは一緒なのです。
だから本は大量に読む必要はありません。
知りたいことを明確にしておくのが大事
本を読んで自分はどんなことを知りたいかと目的を明確にすることも大切です。
人間の脳は、目標が定まると、その情報はないか効率的に探すようになります。
逆を言えば、目的のない読書はなかなか頭に入ってこないということです。
ぜひ、本を読むときは何を知りたいかを明確にして読むようにしましょう。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
もし、娯楽で読む場合でも、「誰かに伝えるつもりで読む」ことで、知識や記憶の定着率が上がることがわかっています。
読んだ本を友達や家族にはなすつもりで読むことで、さらに読みを深めることができます。
あるジャンルがマンネリ化したら、他のジャンルを読もう
先ほども述べましたが、ある程度1つの分野の本を読むと、知識の基盤ができてきます。
大体、理解してきたなと思ったら、次のレベルに行くために2つの進路があります。
もっと難しい内容の本にチャレンジすることと、違う分野の本にチャレンジすることです。
難しい内容の本は、一般的に古典と言われるものに挑戦することになります。
読書だったら、ショウペンハウエルの『読書について』を読んでみるとよいでしょう。
また、他のジャンルを読むことで、共通する考えの基盤があることに気づいたりします。
最近私は、読書術と勉強法について本を読んでいます。
学校の先生として、子どもたちに勉強の楽しさや効率化、読書の楽しさを伝えるためです。
2つのジャンルを読んでいて、勉強を楽しくする方法も、読書を楽しくする方法も根幹には脳が関わっていることに気づきました。
そこから脳科学に依拠した勉強法や読書法を伝えることで、子どもたちに具体的な話をすることができるようになりました。
こうやって別のジャンルを行き来することで、より学習の深みが増します。
新しいアイデアを出すには、掛け合わせが大事ということもビジネスの世界ではよく言われます。
自分だからこそできる掛け合わせが見つかるといいですね。
こちらでも、話題として取り上げています。ご覧ください。
選書という幻想
「いい本を選んで読むこと。それが最も効率がよくて、身につく読書法は違いない。」
この言葉はある側面からは合っていますが、ある側面では間違いです。
どういうことかというと、最近こんな本を買いました。
全国数学教育学会が最近出したハンドブックです。
この本は全国数学教育学会の前組織から今までの研究を概観して、その軌跡と今後の展望をまとめた本です。
この本を見れば、各研究分野の今後の研究のニーズや、方向性がわかる一冊になっています。
現場の先生も、これをもとに授業を提案すれば新規性のあるとても素晴らしい授業になること間違いありません!
・・・読めないですよね。私も必要な分野は読みますが、勉強不足で全てはまだ読めません。
きっと大学の先生だったら、ふむふむとこの本を活用してどんどん新しい研究をしていくでしょう。
つまり「いい本かどうかは、読み手次第なのです。」
読み手にとって知っている情報ばかりなら、きっとハズレ本でしょう。
読み手にとって、知らない情報が多いけど、難しすぎて読めなくてもハズレ本になってしまうでしょう。
だからこそ大切なのは、1冊の本から自分にとって役に立つ知識や情報を選んでいくことなんです。
いい本は教科書として読み、ハズレ本は問題集として使う
大体10冊読んで、いい本は1冊2冊です。
ハズレ本はじゃぁ読んでも意味がないのかというとそうではありません。
ハズレ本は、今持っている知識と相対化をするために使いましょう。
例えば、ハズレ本を読んで、ここは違うなと思ったら「ハズレ本にはこう書いてあるけど、こういう説明の方がわかりやすいな」「この本には研究データが載っていないけど、こういう研究データがあったぞ」とというふうに読んでいくのです。
こうすることで自分の知識を活用しながら本を読んでいくことができます。
この読み方は、学会の論文を読み方に似ています。自分の持っている知識と相対化することで、さらに読みを深めることができるのです。
最後に
今回は、速読・多読・選書は幻想であるということを述べました。
大切なのは、
- 自分にあった1冊を選ぶこと
- ゆっくりでいいから、しっかりと1冊を読んでいくこと
その中でだんだん速く読めるようになってきますし、確実に知識がついていきます。
速読・多読という言葉ばかりに惑わされないようにしましょう。
It is books that are the key to the wide world. If you can’t do anything else, read all that you can.
広い世界への鍵となるのは本である。もし他に何もできないのなら、出来るだけ本を読みなさい。
ージェーン・ハミルトン(アメリカの小説家)

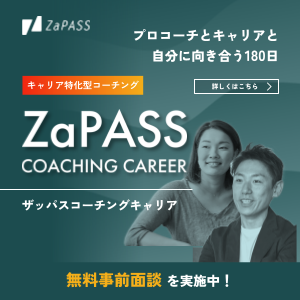
参考文献・参考HP
参考文献
Audibleに入会すれば、「知識を操る超読書術」を無料で聞くことができます。
月額1500円ですが、30日は無料!
キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。
飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。
この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!
Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!
参考HP




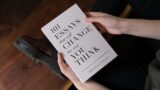








コメント