2023年、日本で生成AIが話題になった時、自分は使えない・・・。と正直思いました。
命令文(以下プロンプト)がちょっと違うだけで、出てくる回答が全く違うからです。
当時の生成AIの説明本は、プロンプト例がたくさん載っているだけで、プロンプトの一般的な約束は何かというのが全く見えませんでした。
そこで一度わたしは生成AIから離脱をしてしまいました。
2025年この記事を書いている現在、とてもプロンプトが扱いやすいものになりました。(2024年6月のChatGPT-4oがリリース以来大きく改善されたようです。)
また、プロンプトの一般的な法則も出てきました。
これからもシステムは進化するでしょうが、プロンプトの基本は大きく変わらないでしょう。
大原則を一緒に勉強しましょう。
※今回使用しているのはChatGPT-4oを使用しています。CopilotもChatGPT–4をベースとして開発されているので、同じように挙動をします。
他社のサービスAIも基本的なところは一緒ですので、試してみてください。
以下 緑枠・・・筆者のプロンプト(命令) 水色枠・・・生成AI回答とします。
生成AIそのものについて知りたいからは、まずこちらの記事から御覧ください。
プロンプトの良い例と悪い例
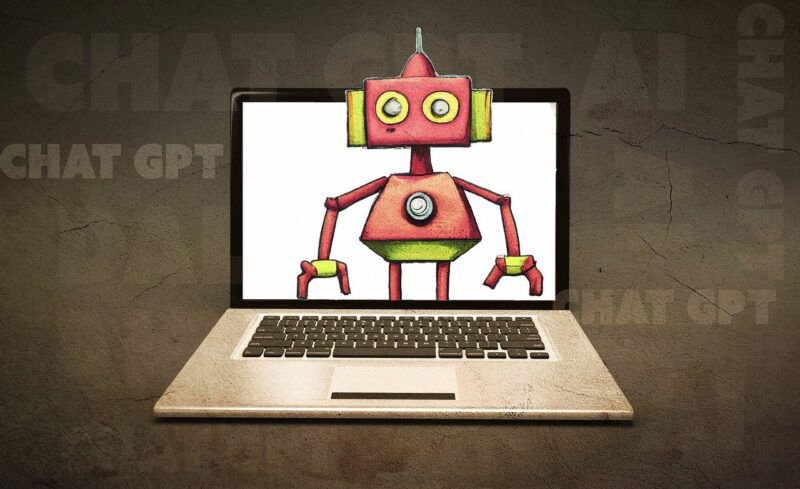
プロンプトの大原則
生成AIは、人間ではありません。
例えば、Aさんに、飲み会の企画を頼んだとします。
Aさんは、いつぐらいが都合が良さそうか、どこのお店ならみんな満足するか。集合時間から、2次会のセッティングまできっと上手に段取りを組んでくれることでしょう。
A Iは「飲み会の企画をして」と頼んでも動けません。みんなに出欠をとる。2次会のセッティングをする。などなどAIが混乱しないように、全ての命令を事細かにすることでやっと動いてくれます。
小学1年生の子どもに、「飲み会の企画はね・・・」と教えてあげるイメージぐらいに思ってください。
そこで、こんなことを意識してプロンプトをしていきましょう。
- 指示を詳細にする
- プロンプトの最初に簡潔な指示をする
- 参照する文章に区切り記号を入れる
- 生成結果の条件を明確にする
1.指示を詳細にする 悪い例・良い例
・悪い例
遠足の計画を立てて
どんな遠足を計画したいですか?
- 行き先: 山、公園、動物園、博物館など
- 参加者: 小学生、友人グループ、家族など
- 日程: いつ頃?日帰り?宿泊あり?
- アクティビティ: ハイキング、お弁当、ゲーム、見学など
ざっくりしたイメージがあれば、それに合わせて具体的な計画を作ります!
イメージ湧いたでしょうか?生成AIが回答を出すのに必要な情報を求めてくれるようになりましたが、これだけ打ち込む必要があるのです。
次のようにプロンプトを変えてみましょう。
・良い例
神奈川に住んでいる。家族4人(父・母・5歳・2歳)で遠足に行きたい。日帰りで、電車で行けるところを教えて
電車で行ける日帰り遠足スポットをいくつか紹介します!
1. こどもの国(横浜市青葉区)
- アクセス:東急こどもの国線「こどもの国駅」徒歩すぐ
- ポイント:広大な公園、動物ふれあい、遊具、ピクニックが楽しめる
2. 新江ノ島水族館(藤沢市)+江ノ島散策
- アクセス:小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩3分
- ポイント:イルカショーやクラゲ展示が人気、江ノ島で海遊びも◎
3. 野毛山動物園(横浜市中区)
- アクセス:京急「日ノ出町駅」徒歩10分 / JR「桜木町駅」徒歩15分(バスあり)
- ポイント:無料で楽しめる動物園!コンパクトで小さい子でも歩きやすい
4. 鎌倉・長谷寺&由比ヶ浜
- アクセス:江ノ電「長谷駅」徒歩5分(長谷寺) / 由比ヶ浜まで徒歩10分
- ポイント:お寺観光+海遊びができる、食べ歩きも楽しい
5. 上大島キャンプ場(相模原市)
- アクセス:JR相模線「橋本駅」からバスで約30分
- ポイント:相模川沿いの広場でピクニックや川遊びができる(無料)
小さいお子さんがいるので、駅から近くて移動しやすい場所を選びました。
どんな雰囲気の遠足が理想ですか?
2.プロンプトの最初に簡潔な指示を出す 悪い例・良い例
・悪い例
学芸会の劇のアイデアが出なくて困っています。子供達は元気な子でみんなの前で劇をするのが好きな子もいれば、嫌いな子もいます。歌を歌うのが好きな子もいれば、戦隊モノが好きな子もいます。ただ、みんなが満足するような劇の演目にしたい。困ったー。図書館で調べてもいい題材ないんだよね。
みんなが楽しめる劇を作るなら、オリジナルのストーリーを考えるのもいいかもしれません。例えば:
① 「うたって!たたかって!みんなのヒーロー」
- 歌が好きな子は主題歌や挿入歌を歌う
- 戦隊モノが好きな子はヒーロー役でアクション
- 劇が苦手な子はナレーションや小道具係などの役割で参加
- ストーリー例:「町のみんなが元気をなくしてしまった!そんな時、音楽の力を持つヒーローたちが立ち上がる!」
② 「おとぎ話のヒーロー大集合!」
- 赤ずきん、桃太郎、シンデレラなどがヒーローとして活躍する
- 戦隊風の展開で敵をやっつける
- 途中で歌や踊りのシーンを入れる
③ 「ぼくらのへんてこミュージックランド」
- いろんな音が飛び出す不思議な世界を探検する話
- 歌やダンスがメインで、戦隊風のアクションも少し入れる
- それぞれの個性を活かせる役割を作る
オリジナルだと、子供たちの好みに合わせてカスタマイズしやすいし、みんなが活躍できる役を作りやすいですよ。どうでしょう?
なんとか付き合ってアイデア出してくれました。優しいですね。
最初に簡潔な指示を出して、もう少し方向性を定めて見ましょう。
・良い例
あなたは小学校の先生です。学芸会で劇をやりたい。30人程度が出演する。昔話の劇をやりたいが、途中みんなで歌える合唱曲があるといい。アイデアをください。
昔話をベースにした劇で、途中に合唱を入れられるアイデアをいくつか提案します。
①「ももたろう 〜仲間とともに〜」
あらすじ:
桃太郎が鬼退治に向かう話ですが、途中で「協力することの大切さ」をテーマにした合唱を入れます。
合唱曲の例:「世界がひとつになるまで」「ビリーブ」など
工夫ポイント:
- 桃太郎、犬、猿、キジ、鬼など役が多く取れる
- 村人や鬼役の子もセリフがあり、全員に出番がある
- 鬼ヶ島到着前に「仲間っていいね!」的な合唱シーンを入れる
②「さるかに合戦 〜みんなで力を合わせて〜」
あらすじ:
悪さをしたサルをカニと仲間たちが協力して懲らしめる話。友情や助け合いがテーマ。
合唱曲の例:「にじ」「ともだちはいいもんだ」
工夫ポイント:
- さる、かに、くり、はち、うすなど、個性的なキャラが多く、大人数でできる
- 「いじめはよくない」など現代的なメッセージも入れられる
- みんなでサルをこらしめる場面で歌を入れると一体感が出る
③「ブレーメンの音楽隊 〜みんなでつくる音楽〜」
あらすじ:
年老いて捨てられそうになった動物たちが協力して新しい居場所を見つける話。音楽がテーマなので合唱シーンを入れやすい。
合唱曲の例:「ドレミの歌」「小さな世界」など
工夫ポイント:
- 動物役(ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリ)+泥棒役+村人役で大人数に対応できる
- 劇中に楽器を持たせたり、手拍子やダンスを入れたりして音楽劇にできる
- 旅の途中で「楽しい音楽を作ろう!」とみんなで合唱する場面を作る
昔話をアレンジして、歌と組み合わせると盛り上がります!
どの話がクラスに合いそうですか?
生成AIのプロンプトの有名なもので、「役割を与える」というものがあります。
そうすることで、生成AIの回答の方向性が一気に決まるのd、生成AIリリース当初は、よく挿入すると良いと言われた有名プロンプトです。
今でも、「役割を与えるプロンプト」は有効です。どんな回答を生成AIに出して欲しいのかがはっきりするので、とても便利です。
3.参照する文章に区切り記号を入れる 悪い例・良い例
この記事の第 1章を要約してもらいました。
ただ、最近は生成AIが進歩して区切り記号は別の用途で使われるようになりました(後の章参照)
・悪い例
次の文章を要約してください。
速読という幻想
速く読めるようになれば、読書量が増え、人生に役立つ読書ができるようになる。
・・・以下略
速読は読書量を増やす手段として推奨されるが、実際には内容の理解や記憶には結びつかない。速読の方法として「写真のように読む」「斜め読みする」といった技術があるが、どちらも読んだ内容が頭に残らない。実験でも、速読の達人が本を短時間で読んだものの、感想は抽象的で具体性に欠けていた。研究によると、速く読むほど理解度は下がり、目の動きや周辺視野の影響は読書スピードにおいてわずか10%以下しか占めないことが分かっている。
・良い例
次の文章を要約して下さい
“”速読という幻想・・・中略
- 読書のスピードと時間を決める要素の中で、目の動きある周辺視野が占めるのは10%以下しかない“”
速読は読書量を増やす手段とされるが、実際には内容の理解や記憶には結びつかない。「写真のように読む」「斜め読み」といった方法では、読後の余韻は残るものの、知識として定着しない。実験では、速読の達人が短時間で本を読んだものの、感想は抽象的で具体性に欠けていた。研究によると、速く読むほど理解度は下がり、読書スピードを決める要因のうち目の動きや視野の影響は10%以下であることが明らかになっている。
4.生成結果の条件を明確にする 悪い例・良い例
・悪い例
先生という職業をアピールする文章を考えてください.
未来を育む仕事――先生という選択
先生という仕事は、単なる「教える」職業ではありません。子どもたちの可能性を引き出し、成長を支え、未来をつくる仕事です。
教室では、知識を伝えるだけでなく、考える力や協調性、挑戦する心を育てます。子どもたちが「できた!」と目を輝かせる瞬間は、何にも代えがたい喜びです。
また、先生は子ども一人ひとりの人生に関わる存在です。学ぶ楽しさを伝え、自信を持たせ、時にはそっと背中を押す――そんな役割を果たします。
未来を担う子どもたちとともに学び、成長する。先生という仕事には、大きなやりがいと無限の可能性があります。あなたも、誰かの未来を照らす先生になりませんか?
文章としては素晴らしいですが、ポスターに使うのかSNSに使うのかはっきりしません。
もう少し条件をはっきりさせて、AIに文章を作ってもらいましょう。
・良い例
先生の仕事の魅力をSNSでアピールする文章を考えください。条件は以下の通りです。
・100文字前後
・仕事は楽しいこと
・働き方改革が進んでいること
・子育てしやすい職業であること
先生の仕事は、子どもたちの成長を間近で感じられる楽しい仕事!働き方改革が進み、ワークライフバランスも向上。育休や時短勤務も充実していて、子育てしながら働きやすい環境です! #先生って楽しい #働き方改革
ちょっと、質問がブラックジョークですかね。
修正指示を繰り返して欲しい回答を手繰り寄せる
もちろん生成AIは一発でこちらの欲しい回答を出してくれるとは限りません。
そこで、回答を修正するプロンプトを出せばこちらの意図した回答を引き出しやすくなります。
人間相手に何回もダメ出しするのは、気が引けますが、生成AIは嫌な顔ひとつせず、何度も修正に付き合ってくれるので偉大です。
- 新たな条件を出す
「同じ条件でさらに3つアイデアを出してください」 - 具体的な指示を出す
文章が短い(長い)ので、もっと長く(短く)して - 対話しながら修正をする
文章中の「〇〇」という言葉を詳しく説明してください。 - 足りない点を事前に確認する
回答の前に必要な情報を私に聞いてください - 繰り返し改善を行う
〇〇について、私がよくわからないので詳しく(中学生にもわかるように)説明してください。 - 段階的に質問する
1回目:ランニングで必要なものはなんですか
2回目:ランニング初心者はどんなトレーニングをするべきですか
3回目:提示してくれたトレーニングがどの種類を週に何回実施すべきですか?
5W1Hを指定する
作文の基本である5W1Hを明記することで、生成AIがわかりやすいプロンプトになります。
5W1H
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(誰が)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
5W1Hを意識して研修会の案内状の文章を生成AIに作ってもらいました。
校内の先生方に向けて研修会の案内を作りたいので文面を考えてほしい。
いつ:2月14日
どこで:理科室
誰が:ICTに興味のある先生、働き方改革を進めている先生
何を:ChatGPTの校務利用研修会をする
なぜ:学校の在校時間を短くするため
どのように:各自の学校パソコンを持ち寄って
校内研修会のご案内
先生方へ
日頃より教育活動にご尽力いただき、ありがとうございます。
このたび、「ChatGPTの校務利用研修会」 を開催いたします。ICTの活用や働き方改革に関心のある先生方とともに、ChatGPTを活用して校務の効率化を図り、在校時間の短縮につなげる方法を学ぶ機会としたいと考えています。ぜひご参加ください。
◆日時:2月14日(〇)〇時~〇時
◆場所:理科室
◆対象:ICTに興味のある先生、働き方改革を進めている先生
◆内容:
・ChatGPTの基本的な活用方法
・校務(文書作成・教材作成・情報整理等)への応用
・実践ワークショップ(各自の学校パソコンを使用)
◆持ち物:学校パソコン
実際に操作しながら学べる実践的な研修となりますので、ぜひ学校パソコンをお持ちの上、ご参加ください。
参加を希望される先生は、〇月〇日までに〇〇までご連絡をお願いいたします。
担当:〇〇(研修担当者名)
皆さまのご参加をお待ちしております!
あとは適宜、必要な部分を加除修正すれば、一瞬で案内文ができますね!
必要な情報を設定する
5W1Hとは別に「目的」「役割」「入力データ」「条件」「出力形式」という形でChatGPTに必要な情報を与えて見ましょう。
特定の条件下において、独自の回答がほしい場合に有効です。
- 目的
どんな行動や結果を求めているのか? - 役割
どのような立場か? - 入力データ
参照する情報は何か? - 条件
希望する成果物や制約条件を指定する - 出力形式
生成結果をどのような形式にするか
例えば、ブログで、数学のある分野の解説をしたい。数式入りで一発で出せるように、生成AIに文章を考えてもらいましょう。
文字式の展開について解説文章を作りたい。
役割:中学校の先生
入力データ:中学生でも数学の苦手な生徒にわかるように
条件:展開公式のまとめ文章を最後に入れる
出力形式:html形式
以下のHTML形式で解説文章を作成しました。
このコードをウェブページに貼り付ければ、そのまま表示できます。
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>文字式の展開の解説</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 20px;
}
h1 {
color: #2c3e50;
}
h2 {
color: #16a085;
}
.formula {
background-color: #ecf0f1;
padding: 10px;
border-left: 5px solid #3498db;
margin: 10px 0;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>文字式の展開とは?</h1>
<p>文字式の展開とは、かけ算の形になっている式を、たし算・ひき算の形に直すことです。例えば:</p>
<div class="formula">(a + b) × c = a × c + b × c</div>
<p>このように、かけ算を分配して計算しやすい形にすることを「展開」と言います。</p>
<h2>展開の基本</h2>
<p>以下のような場合に、分配法則を使って展開できます。</p>
<ul>
<li><b>単項式 × 多項式</b>:<br>
<div class="formula">2(x + 3) = 2x + 6</div>
</li>
<li><b>多項式 × 多項式</b>:<br>
<div class="formula">(x + 2)(x + 3) = x² + 3x + 2x + 6 = x² + 5x + 6</div>
</li>
</ul>
<h2>展開の公式まとめ</h2>
<p>展開をスムーズに行うために、以下の公式を覚えておきましょう。</p>
<ul>
<li><b>分配法則</b>:<br>
<div class="formula">(a + b)c = ac + bc</div>
</li>
<li><b>平方の公式</b>:<br>
<div class="formula">(a + b)² = a² + 2ab + b²</div>
<div class="formula">(a - b)² = a² - 2ab + b²</div>
</li>
<li><b>和と差の公式</b>:<br>
<div class="formula">(a + b)(a - b) = a² - b²</div>
</li>
</ul>
<p>これらの公式を使うと、計算が早くなります!最初はゆっくり練習して、少しずつ慣れていきましょう。</p>
</body>
</html>このHTMLでは、数学が苦手な生徒でも理解しやすいように、シンプルな説明と具体例を加えています。
また、展開公式を最後にまとめているので、復習にも使えます。
htmで出力してみるとこんな綺麗に出力されます。
文字式の展開とは?
文字式の展開とは、かけ算の形になっている式を、たし算・ひき算の形に直すことです。例えば:
このように、かけ算を分配して計算しやすい形にすることを「展開」と言います。
展開の基本
以下のような場合に、分配法則を使って展開できます。
- 単項式 × 多項式:
2(x + 3) = 2x + 6 - 多項式 × 多項式:
(x + 2)(x + 3) = x² + 3x + 2x + 6 = x² + 5x + 6
展開の公式まとめ
展開をスムーズに行うために、以下の公式を覚えておきましょう。
- 分配法則:
(a + b)c = ac + bc - 平方の公式:
(a + b)² = a² + 2ab + b²(a – b)² = a² – 2ab + b² - 和と差の公式:
(a + b)(a – b) = a² – b²
これらの公式を使うと、計算が早くなります!最初はゆっくり練習して、少しずつ慣れていきましょう。
展開公式の導出を知りたいのなら、追加で聞いてみましょう。
ChatGPT-4oにおいて有効なプロンプト

今まで開設したプロンプトは、2022年Chat-GPT3.5(無料で使えたもの)において有効なプロンプトです。
2024年5月にリリースされたChatGPT-4oにおいてノウハウが変わりました。
詳細な指示を出さなくても、最適な回答が得られやすくなりました。
- 最初の 1行で指示を簡潔に書く
- 役割がなければ指定をしない
- 回答結果について条件をしていすつ場合は、文字数や形式などを具体的に指定する
- 文章の構造として項目を指定する場合、記号を使う
大項目は「##」 小項目は「###」 箇条書きは「-」を付与
記号の後ろには半角で空白を入れる - 回答に対して修正を行う場合を想定して、理由を併記するように指示をする。
回答に問題があった場合、理由から修正点を探る
作成例
次のことを段階的に論じて下さい
#勉強の重要性について
#国語の読解力
##読解力をつけるためのトレーニング方法
ー3つ述べて
1. 勉強の重要性について
勉強は、知識を得ることだけでなく、思考力や判断力を育む重要な手段です。特に現代社会では、情報を適切に理解し、活用する力が求められます。勉強を通じて培われる論理的思考や表現力は、日常生活や将来の仕事にも役立ちます。
2. 国語の読解力
その中でも、特に国語の読解力は、すべての学問の基盤となります。文章を正しく読み取る力がなければ、数学の文章問題や社会・理科の資料を理解することも難しくなります。また、読解力があれば、ニュースや契約書などの実生活に関わる文章も的確に読み解くことができます。
読解力をつけるためのトレーニング方法
読解力を鍛えるためには、以下の3つの方法が効果的です。
- 要約練習
文章を読んだ後に、その内容を短くまとめることで、文章の本質をつかむ力が養われます。最初は短い文章から始め、慣れてきたら長文でも試してみるとよいでしょう。 - 質問を作る
読んだ文章について「この文章のポイントは?」「筆者の主張は?」などの質問を自分で作ることで、文章の構造や意図を意識的に捉える習慣がつきます。 - 音読と再話
音読することで文章のリズムや構成が自然と身につきます。また、音読後に内容を自分の言葉で話す(再話する)ことで、文章の理解度を深めることができます。
これらの方法を継続することで、読解力が向上し、学習全般に良い影響を与えることができます。
様々な文章の作成
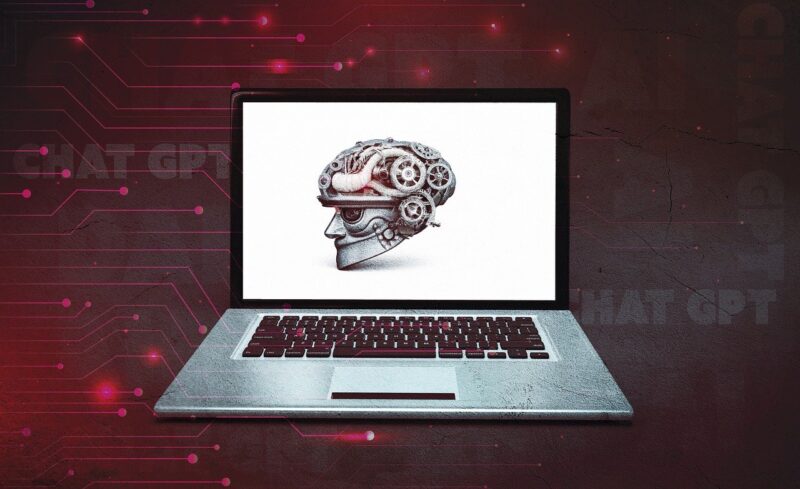
プロンプトを工夫すれば、様々な文章を作成できます。
例えば「SNSに投稿をする」ことを条件にすれば、ハッシュタグを入れてくれます。
口コミやレビュー、企画書のアイデア出しも可能です。
初めて書く文章(報告文など)や、気の進まない文章(謝罪文)など、最初のフォーマットを生成AIに依頼すると良いでしょう。
ただし、契約書など専門性が求められる文章も作成できますが、「ハルシネーション(生成AI特有の間違い)」の危険性もあります。必ず専門家の確認を取りましょう。
ハルシネーションについてはこちらに詳しく書きました。
最後に

ChatGPTなど生成AIに慣れるにはとにかく使ってみることです。
ChatGPT-4o以降、とても的をいた回答が返ってくるようになりました。
また、足りない情報を忖度して、こちらの意図に沿った回答を出してくれます。
文章作成だけでなく、情報収集、質問、企画のアイデアだし、翻訳、壁打ちなどなんでもしてくれます。
どんどん使って、自分にあった使い方を見つけてくださいね。
プロンプトについて、もっと知りたい方は、「プロンプトエンジニアリングガイド」で勉強してみましょう。

もう少し専門的なプロンプトを組みたいという方は、以下の記事にお進みください。
さらに研究や演算に使えるようなプロンプトもあります。









コメント