2回に分けて生成AIについて取り上げてきた。
1つ目の記事では、生成AIの得意なこと・苦手なことを整理をした。
2つ目の記事では、生成AIの起こす間違い「ハルシネーション」について、どう避ければよいかについて学んできた。
これからの社会においても生成AIはますます隆盛していくことが予想される。
第3のこの記事では、生成AIが当然の社会においての学校の役割について考えたい。
生成AIが隆盛する社会においての学校の役割

学校が変わらないといけないこと
1つ目の記事で、生成AIの性能はどんどん上がり、中学・高校教科書程度の基本的な知識の伝達については対応可能であることを書いた。
反面、「豊富秀吉が天下を取れたわけは何か?」のような論述形式の問題や、「円周率が3.05以上になることを証明せよ」といった入試問題までは完璧な解答を返すことができないことも確認した。
ただ、教科書レベルのものについては十分対応できる(社会においても、「本能寺の変で織田信長を討った人物は?」と尋ねれば「明智光秀」と返ってくる)ので、基礎事項の理解だったら、生成AIを使えば十分なのではないだろうか?
巷には、動画学習をすれば、教師の役割はいらないのでは?という論調の人も一定数いる。
さて、ここからAIが当たり前になり、学校はどう変わるべきかを綴りたい。
たしかに、生成AIはとても進歩して、自分の知りたいことを対話形式で詳しく教えてくれることが可能になった。
ある問題に対して、現在は文章だけでの返答しかしてくれないが、そのうち図形やイラストをつけてくれながら、さらに分かりやすい解説をしてくれるようになることは容易に予想できる。
ハルシネーションの問題もあるが、2つ目の記事でも指摘した通り、使い方を理解すれば、問題はなくなるはずである。
現に20年前、インターネットが出現した時の教育現場も同様の混乱があっただろうが、、今はそこまで使用について学習に限っては問題視されていない(SNSなど生徒指導てきなものはあるが)。
現代においてはGoogleやWikipediaの登場に伴い、ある程度信ぴょう性が高い情報が入手しやすくなった。
生成AIもこれから人間が使い続けることで、技術そのものも、使う人間の心構えもブラッシュアップがなされるだろう。
精度がさらに高まりハルシネーションについても十分人間は対応可能になってくるだろうし、使うならば、学校できちんと指導をしていくべきだし、できると思っている。
私は生成AIを学校現場に取り入れることは、学校できちんと指導をする前提で何ら反対意見はない。
学習が豊かになるようにむしろどんどん使っていきたい。
その中で、教師が学習する中で不要になるかというと全くそうは思わない。
理由を
- 児童生徒の年齢の壁
- カリキュラムの編成
- 個別最適な学びに向けて
の3つに分けて論じよう。
児童生徒の年齢の壁
単純に小学校1年生や2年生などでは、生成AIを使いこなせない。
言語がまだ未発達であり、子どもの辿々しい言葉をうまく取り入れながら授業を展開できるのは人間である教師しかできないだろう。
精神的に自立してくる中学校においても、適切に生成AIを使いこなせるかは不透明な部分が多い。
生成AIを学校で取り入れるとしても、熟達できるようになるには、教師の支援を受けながら使い方を身につけることが導入初期では必須であると考える。
カリキュラムの編成
学習は系統だって学習しなければ、どこかで破綻をきたす。
例えば、足し算を習っていない子どもが、いきなりかけ算を学習するのは無理である。
生成AIは「かけ算って何?」と聞かれれば答えてはくれる。ただ、質問者の学習状況をを踏まえながら回答してくれることはない。
教師が子どもにあったカリキュラムを作成することは必須になるだろう。
個別最適な学びに向けて
昨今「個別最適な学び」という言葉がよく聞かれる。
これは、今までの一斉授業の反省的な動きであると考える。
従来、30人、40人、1クラスの子どもたちに対して同じ課題を与え、学習を進めてきた。
これは、とても効率がいいのだが、どこかでつまづいて、学習についていけなくなった子どもはなかなか追いつけないという弊害があった。
その対策として、学級を半分に分けて少人数授業や、習熟度別授業。または、教員の複数体制での一斉授業(いわゆるチーム・ティーチング TT)が行われてきた。
文科省の調査からも一定の成果は報告されている。
ただ、教員の成り手不足は深刻で、複数の教員を一つのクラスの授業に配置するのも厳しい状態になっている。
少ない教員で対応しながら個に応じた学びを実践するためには、一斉授業と、生成AIを取り入れた学習をうまく組み合わせることである。
例えば、基礎事項(基本的な計算・暗記事項 九九の暗記 戦国時代の外観など)は全体で行う。
応用問題や調べ学習については(戦国時代の本能寺の変について詳しく学習するなど)、生成AIを使いながら学習に取り組んでいくというスタイルである。
今まで一斉授業では、レベルの低い子に合わせざるを得なかった。ただ、生成AIがあれば、レベルの高い子に対しても対応が可能になる。
低位の子は、先生と一緒に学習し、上位の子は、自分で生成AIと共に学習をより深めていく。
そうすることで、それぞれの子どもの力に応じた学習が可能になると考える。
家庭学習の変革
生成AIは貧乏な子への味方になる
個人的には、学校での学習の変革ではなく、家庭での学習において使い方次第で大きな変革を起こすポテンシャルを秘めているのではないかと考える。
例えば、今まで裕福な子は、習い事や塾、家庭教師などをつけることで、家庭でも学習をバックアップしてくれる状態が整っていた。
反面、貧乏な子は、そのようなバックアップが得られない。学習をしようと思ってもできないということがあった。
実際に全国学力学習状況調査のアンケートから「貧困と学力は相関関係にあること」が報告されている。
ただ、生成AIの出現により、生成AIの活用すれば自分でどんどん学習を深めていくことが可能になった。
また、Youtubeなどでも無料の学習動画がどんどんアップロードされている。
この2つを用いることで、子どもの意欲次第でどこまででも学びを広げることができる基盤は整ったのである。
児童生徒1人1台のタブレット端末が実現できた今だからこそ、家庭学習に革命を起こしていけるようにしたい。
また、学校としては、一斉授業だけでなく、自分で学びを深めるのはどうすればいいかに主眼を置いた学習指導を取り入れる時期に来ているといえよう。
学校が変わってはいけないところ
個人が社会の一員としての役割を果たすために学校が果たすべき役割として、つぎのようなことが挙げられる。
第1に、異なる背景や価値観を持つ生徒たちの交流の場となり、コミュニケーション能力や協調性を養う機会を提供する。
第2に、社会の基本的な価値観や倫理観、そして公共の福祉に対する意識を養う。
第3に、異なる文化や背景を持つ生徒との交流を通じて、多様性を尊重する態度を育む。
第4に、自分自身の興味や能力を理解し、それを表現する方法を学ぶ。
第5に、学校のルールや規範を守ることによって、社会全体のルールや規範に従うことの重要性を理解する。
ー野口悠紀雄.「ChatGPT『超』勉強法」.p275,276
今回、生成AIを勉強する中で参考にした文献の中から引用した。
人間関係を作る、社会的規範を学ぶ、エンパシーなどといったコミュニケーションや社会的なもの(いわゆる非認知能力)は、生成AIを使っても学べないものである。
だからこそ、学校での経験はとても大切なものであるということが書かれていた。
これについても全くの同感である。
イギリスでは、パブリックスクール(全寮制の私立高校)があり、そこはエリートの養成校となっている。
イギリスでは、全寮制での生活について、生徒を人間的に成長させるといった社会合意があるのである。
日本では、このような制度をとっているところは少ないが、学習以外の生活でも、生徒同士の交流で成長していくという理論はみんな納得であると思う。
ここについては、さらに力を入れていかなければならない。
日本の学校は一杯一杯になっている
ただ、ここで一言だけ申し上げたい。
日本の学校の先生はとても頑張っていると思う。
日本の学校の先生は、生活指導・生徒指導の部分と、学習指導を1人の先生が丸抱えしてきたところに素晴らしい面である。
ただ皮肉なことに、長時間労働などの問題から不人気の原因となっている部分が出てきてしまった。
この点については、こちらの記事で言及をした。
学校としては、学習をうまくAIを用いながら効率化を図っていく一方で、より人間関係の指導をきめ細やかにしていくことができると思っている。
そこで、学習指導を専門にする先生と、生徒指導・生活指導を専門に行う先生の分業を提案した。
イノベーションを起こしながら学校の労働環境をより良いものにしていくのが現役教師としての責務だと感じている。
最後に

今回は生成AIで学校はどう変わるのか、どう変わるべきかを述べた。
『不易流行』
ー松尾芭蕉
これは、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅で体得した概念であり、教育の現場でもよく言われる。
コロナ禍以降の学校は、戦後学校制度が始まって以来の大改革が迫られていると感じている。
その中で我々が何ができるか。何を残し、何を変えていかないといけないか。
よく考えていかなければならない。
生成AIが教育の新たな光を灯す道標になりますように。

プロンプトの書き方をもっと勉強したい方はこちらを御覧ください!
以前ICTの使い方というテーマで記事を書きました。これをAIに置き換えても同じことが言えるのではないかとも思っています。合わせてぜひご覧ください。
参考文献・参考HP
参考文献
参考HP
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/03/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1259912_1_1.pdf



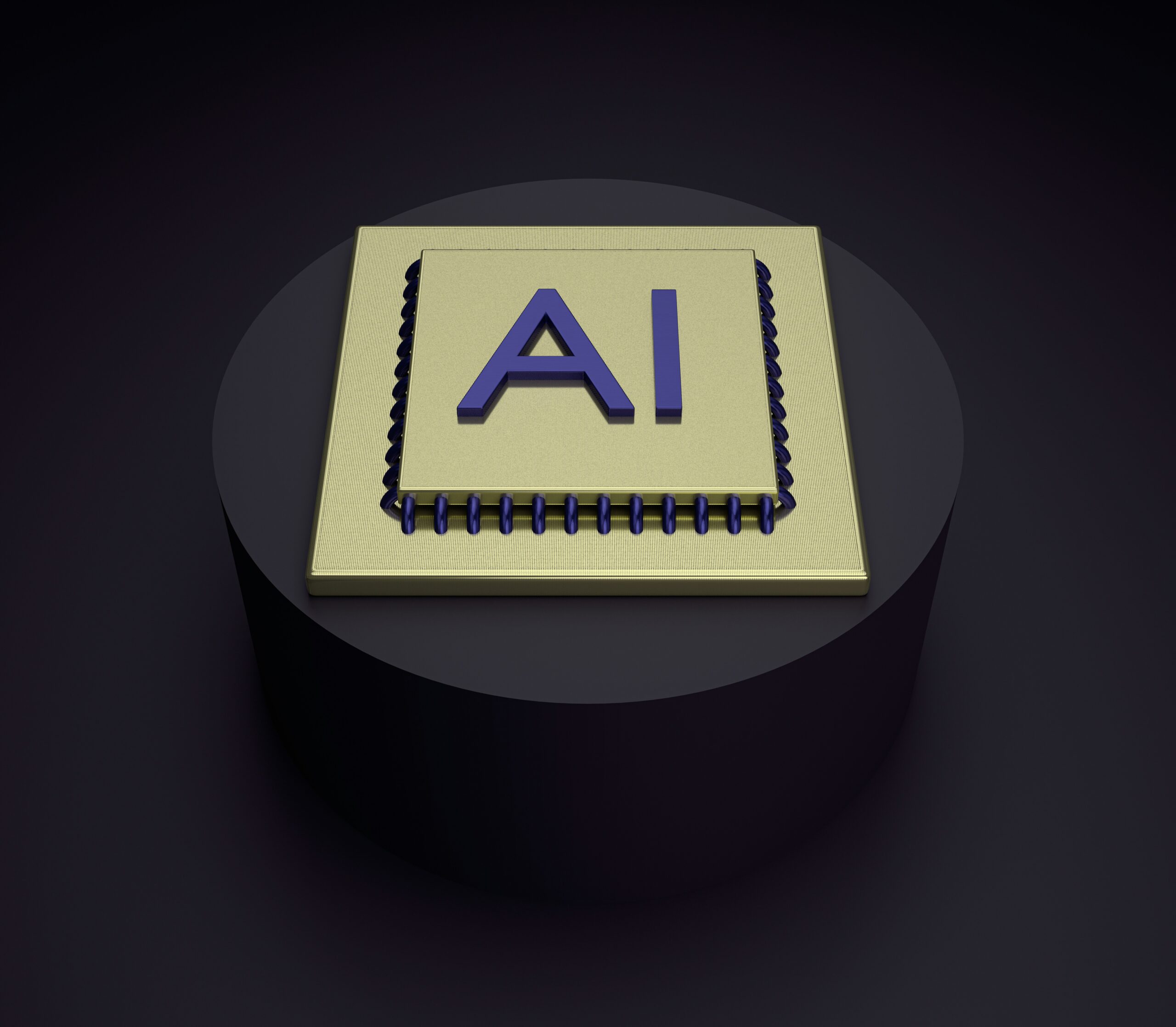








コメント